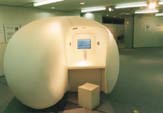“モダン”がひしめく資料館
資生堂企業資料館
1872(明治5)年、大火で焼け野原になった銀座が再建された。日本で初めて車馬道と歩道とを分けた道路の両脇には、レンガ造りのビルが建ち、東京に西洋風の街が現れる。この新しい西洋の街には、洋食屋、パン屋、洋服屋など新しい商売屋が入り、「資生堂」も日本初の西洋風調剤薬局として、銀座の街に登場した。

現在、静岡県掛川市の工場隣に、明治期からの同社の製品や資料が集められた企業資料館がある。調剤薬局からスタートした資生堂だが、その後、つぎつぎと事業を拡大して現在に至ったわけで、ここには、日本初の練り歯磨き、化粧品、香水、ソーダ水など、その足跡を物語る展示品がずらりと並ぶ。
 例えば、資生堂パーラーで使用されていた銀食器。よく見ると茶漉しの部分が、資生堂のシンボル花椿のマークになっていて、なかなかしゃれている。
例えば、資生堂パーラーで使用されていた銀食器。よく見ると茶漉しの部分が、資生堂のシンボル花椿のマークになっていて、なかなかしゃれている。
資生堂パーラーは、1902(明治35)年に銀座の資生堂薬局内に開設された「ソーダ・ファウンテン」に端を発する。創業者が欧米視察の際、アメリカで見たドラッグストアにヒントを得たのだという。
 現在の商品のルーツもわかっておもしろい。
現在の商品のルーツもわかっておもしろい。
1897(明治30)年に発売された「高等化粧水オイデルミン」(←写真)は100年以上経った現在も販売されている超ロングセラー商品だし、大正時代の「FLOWLINE(フローリン)」なる、ふけ防止の美髪剤は、今日の「薬用不老林」だ。
 出版物の展示もある。ケース越しにしか読めないが、大正15年の『資生堂月報』(『花椿』の前身)には「Modern Girl」と題された座談会が載っていて、「モダンガールの将来はどうなる」というような討論がなされている。
出版物の展示もある。ケース越しにしか読めないが、大正15年の『資生堂月報』(『花椿』の前身)には「Modern Girl」と題された座談会が載っていて、「モダンガールの将来はどうなる」というような討論がなされている。
参加者が「(モダンガールが)歌舞伎座へゆくのに島田を結うというのはモダンガールの本質に悖る」などと真剣に議論していて、時代性がうかがえる。
また、明治から大正、昭和、そして現在に至るまでの髪型の移り変わりや、宣伝制作物(ポスター)、パッケージデザインの変遷も。過去の展示ばかりではない。「あなたに合う香水」を調べてくれるマシーンもある(下左)。
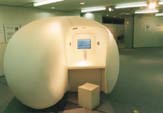

資生堂は、1920(大正9)年に新聞広告で「私達は今、景気不景気を考へるより、流行を考えねばならぬ立場にあります。そうしてどうかして何か新しいものを生み出して、流行界に多少の貢献をしたいと思って居ります」という宣言文をだしたことがある。これらの展示品を見ていると、銀座の風を絶妙に読みながら、時流にあったものを生み出してきたとの自負がうかがえる。
文明開花から大正モダン、そして消費者社会までの時代を、商品から読み取ることも可能だし、美容の歴史として見てもいい。もちろん、純粋なノスタルジーに浸ることもできる。
どの世代にとっても、様々な楽しみ方を見つけることのできるスポットだ。親や祖父母と一緒に行くと、また違った発見があっていいかも知れない。
―DATA―
静岡県掛川市下俣751-1/TEL0537-23-6122
10:00〜17:00(入館は16:30まで)
毎週月曜日と盆と年末年始は休館/無料
◆CONTENTS◆MUSEUM◆


 例えば、資生堂パーラーで使用されていた銀食器。よく見ると茶漉しの部分が、資生堂のシンボル花椿のマークになっていて、なかなかしゃれている。
例えば、資生堂パーラーで使用されていた銀食器。よく見ると茶漉しの部分が、資生堂のシンボル花椿のマークになっていて、なかなかしゃれている。 現在の商品のルーツもわかっておもしろい。
現在の商品のルーツもわかっておもしろい。 出版物の展示もある。ケース越しにしか読めないが、大正15年の『資生堂月報』(『花椿』の前身)には「Modern Girl」と題された座談会が載っていて、「モダンガールの将来はどうなる」というような討論がなされている。
出版物の展示もある。ケース越しにしか読めないが、大正15年の『資生堂月報』(『花椿』の前身)には「Modern Girl」と題された座談会が載っていて、「モダンガールの将来はどうなる」というような討論がなされている。