
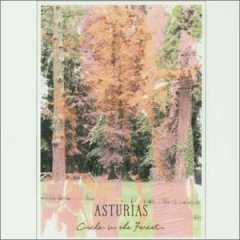 Asturias / Circle In The Forest (1988)
Asturias / Circle In The Forest (1988)
�@Ryu-Hyo / Clairvoyance / Angle Tree / Tightrope / Circle In The Forest�@
���{��Mike Oldfield�Ƃ�����Asturias�̂��̒��ł��ł�Mike���ӎ����Ă���Ƃ������i���Ĕ����ꂽ���߁A���肵���B���肵���̂̓f�W�p�b�N�d�l�Ńt�����X�ՁB���[�_�[����Mike�̂悤�ȉ��y���ӎ����č�����Ɩ������Ă���B���ɍŌ��Circle in the Forest��20�����̑�ȂŁA�Ȃ̃N���C�}�b�N�X�̕�����Ommadawn��Incantations�̗Z���̂悤�ȓW�J�������B�A���o���S�̂̕��͋C�͍ŋ߂̃q�[�����O�n�̕��͋C������A�v��������Mike�F�������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B1�Ȗڂ�Ryu-Hyo�i���X�j�͓��ɐS�n�ǂ��B�����b�N�X���ĕ�����G��B
Circle in the Forest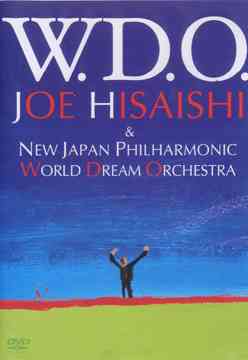 JOE HISAISHI & NEW JAPAN PHILHARMONIC WORLD DREAM ORCHESTRA (2006)
JOE HISAISHI & NEW JAPAN PHILHARMONIC WORLD DREAM ORCHESTRA (2006)
World Dreams 2004 / ���̒J��ų�� (���̓`��) / �V��̏郉�s���^ / �A�C�A���T�C�h TV�V���[�Y�w�S�x�����ݻ��ށx��� / ���̂����₫ �f��w�ؗ�Ȃ�q���x��� / Raging Men �f��wBrother�x��� / HANA-BI �f��wHana-Bi�x��� / ���~�I�ƃW�����G�b�g /
�j�Ə� / �������l���� / �L��������I�u��Uޥ�x���Y / ���V���t�H�[���̗��l���� / �{���� /
�J���~�i��u���[�i�������^���̏��_�� / �W�E�I�[�P�X�g����`���[�u���[�E�x���Y�@�p�[�g1 �f��w�G�N�\�V�X�g�x��� / �f��w�E���̃h���X�x��� �e�[�}�� / ���N�C�G����{��̓�� / ����̂̂��P��g��
/ �J���~�i��u���[�i��A���F����̏�Ȃ��p����������`�J���~�i��u���[�i�������^���̏��_��
/ World Dreams 2006
�X�^�W�I�W�v���̃T���g���ŗL���ȋv�Ώ����A�}�C�N�̃t�@���A���邢��Tubular
Bells�ɉe������Ă��邱�Ƃ́A�t�@���̊Ԃł͏펯�������B�\�i�`�l�̃T���g���̎��́A�܂���Tubular
Bells�̃J�o�[�Ƃ�������̂ł���A�e���r�ʼnf���CM������邽�тɁA�т����肵�����Ƃ����ł��L�����Ă���B����DVD����������AThe Orchestral Tubular Bells�����t���Ă���Ă���̂�����A����������Əؖ����Ă��ꂽ�Ƃ����邾�낤�B���ԍ��Ԃ��J�b�g�����V���[�g���@�[�W�����ł͂��邪�A������Part1���Ō�܂ʼn��t���Ă���Ă��āA��ςɊ������Ȃ��璮�������ł����B�t���I�[�P�X�g���ŁA�����Ȗ��Ȃ����Ă���Ă���A�}�C�N�̋ȈȊO���\�����͂������Ȃ���y���߂�B�C���^�r���[�̒��ŁA���̐l�̋Ȃ������̒��Ɏ�荞��ŁA�����ʼn��߂��ĉ��t����̂��D���Ƃ����R�����g������A�܂��Ƀ}�C�N�̋Ȃ��܂܂�Ă���̂��낤�Ǝv�����B
���̐l�̉��y�͂Ƃ���ǂ���Ń}�C�N�ɒʂ��镵�͋C�������邱�Ƃ��ł��A���S���ĕ�����B���̒J�̃i�E�V�J�́A���Ȃ��Ǝv���B���ꂩ����}�C�N�ɒʂ��閼�Ȃݏo���Ă����ė~�����Ɗ肢�܂��B
GRYFFINDOR Classic Songs Vol.1 (2003)
Orabidoo / Falling Into You / Tubular Bells / ����5�� / �����Ɩ�b / To
France / Because / Moonlight Shadow / London Town / White Christmas
GRYFFINDOR Classic Songs Vol.2 (2004)
Scarborough Fair / Come Back / Here there and everywhere / The top of the
morning / Sally Garden / Little boy's eyes / Song of Bernadette / Christmas
medley 2003
��錧�����s�����_�Ɋ���Ă���]������ƍ�������̃��j�b�g�BOMS�S�ł̓}�C�N�̃J�o�[�����C�u�Ŕ�I���Ă��������A�}�C�N�̋Ȃ����C�u�Œ����Ƃ����t�@���̊�]�����Ȃ��Ă��������܂����B���̍�i�WCD�ł��B��ʂɔ̔�����Ă���CD�ł͂Ȃ��̂ł����A���̐����͂Ƃ��Ă������A�}�C�N�t�@���ɂ͗܂��̂̃J�o�[�W�ł��B�}�C�N�̃J�o�[��Vol.1�ɂ͂S�ȁAVol.2�ɂ�1�ȓ����Ă��܂����ǂ���K���B���l�Ƃ��Ă̓}�C�N�����ɃJ�o�[���Ă������{�̃o���h�̓o���҂��]��ł����̂ł������̖������̂���l�Ŏ������܂����B����CD�̓z�[���y�[�W����\�����ݏo���܂��B�z�[���y�[�W�͂�����Bhttp://www11.ocn.ne.jp/~gryffin/index.html
Black Is the Colour / Donald Of Glencoe / Craigie Hill / Green Grows The Laurel / Lark In The Clear Air / The Lonesome Scenes Of Winter / Blue Mountain River / I Wish I Was / The Maid Of Culmore / She's Like The Swallow / I Am A Youth That's Inclined To Ramble
Tubular Bells �V��Man In The Rain�őf���炵���̐������Ă���Ă���Cara�̂��Ԃ�t�@�[�X�g�\���A���o���B���Ԃ�Ƃ������̂́AMan
In The Rain�ł̉̐������܂�ɑf���炵�����߁ACara�Ƃ����l�ׂĂ݂����A�܂����������Ȃ��������炾�BTubular
Bells�V�ł�Cara From Polar Star�Ə����Ă��������ACara�{�l�͂��Ƃ��APolar
Star�̏�猩����Ȃ������B����Ƃ������ă\���A���o������肷�邱�Ƃ��ł����B�S�҃g���b�h�Ȃ̂悤�����A�����͕��������Ƃ̖����Ȃ���B�A�C���b�V���g���b�h�̓��������A�����Ƃ�Ƒf�G�ȉ̐������Ă���Ă���BMan
In The Rain�̂悤�ȃA�b�v�e���|�̋Ȃ͂Ȃ��A�������Ƃ����Ȃ����S�ŁA�Â��ɕ�����B���Ғʂ�A�f�G�ȉ̐��ŁA�A���o�����̂��̂̃��x���������Ǝv���B������u���C�N���邩������Ȃ��B�}�C�N�͂悭����������ނ������Ă�����̂��B�W���P�b�g�̎ʐ^���Ƃ��Ă����l�ŋ������B�I�t�B�V�����T�C�g��
http://www.caradillon.co.uk/ ���{�l�ɂ��t�@���l������ɂ��T�C�g�� http://www.diana.dti.ne.jp/~yutakahi/cara/cara_top.html
���A���̌�l������͎��ۂɃC�M���X�܂ŃJ���̃R���T�[�g�����ɍs����Ă���B���̎��ɂ͎��ۂɃJ���Ƙb������@�����A�z�[�X�K�[�Y�ł̓J���Ƀ��H�[�J���Ƃ��Ă̏o���v�������������̂́A�_���̖��Ő������Ȃ������Ƃ����R�����g��{�l���������Ă���B���̍ۂɁA�M�d�ɂ������̃T�C���Ǝʐ^�Ƃ������肪�������y�Y�Ղ�������łȂ��u���{�ōŏ��ɂ��Ȃ��̃f�r���[�Ղ��E�G�u�ŏЉ�ꂽ���ł��v�Ǝ��̂��Ƃ��Љ�Ă��������������ł��B���̂Ƃ��̎ʐ^�ƃT�C���́A�������B
Interview With The Angel / The Kiss / Faith In Love / Sacred Touch Of Beauty / Out Of The Woods / Calming The Sea / Burden / Interview With The Angel Part �U / In Your light / Interview With The Angel Part �V / Darkening Hour
Cara Dillon��2�ȖځA3�ȖڂɃQ�X�g�Q�����Ă��邱�Ƃ���A�Љ��ĕ����Ă݂��̂����A�v���������㎿�̍�i�Əo����ƂɂȂ����B�j��2���A�����P���ɂ��C�M���X�̃O���[�v�����A�ߋ���i��������[�X���Ă���A���ꂪ2��ځB�S�҃g���b�h��ł͂�����̂Ƀ|�b�v���̋Ȃ������Ȃ���A�Â��ɗ��������ĕ����邵�A�Ȃ��̂��̂������f�B�A�X�ŕ����₷���B���ł�Cara
Dillon�̉̂�Faith In Love�̓A�b�v�e���|�ł���Ȃ���A����C�̂���ȂŁA�v�킸Man
In The Rain���v���o���Ă��܂��B����ȊO�ɂ�Sinead O'connor���̂��Ă�����ABrian
Eno���L�[�{�[�h�ŎQ�����Ă����肷��B�}�C�N�̋Ȓ��ɂȂ���Ƃ���͐��������肨���߂����A����͍�����B
Dunga / The Flower Of Magherallyo / The Clumsy Lovers / P. Stands For Paddy / Liz Carrolls's / Girls Put The Fags Out /Green Grasses Grow Bonnie / Slow Boat To China / The Weaver / The Mountain Road / Bushes And Briars
Cara Dillon���v���Ƃ��ăf�r���[�����̂����̂n�������Ƃ����O���[�v�ł͂Ȃ����Ǝv����B�j��3�l��Cara��4�l�Ґ��ŁA�t���[�g�A�t�B�h���A�M�^�[�A�A�C�������h�h�����̊y���Cara�̃{�[�J���B�g���b�h�̉��t��Cara�̉̂��قڌ��݂Ƃ����\���ŁACara��5�Ȃł��̉̐����I���Ă���B�V���v���ȉ��t��Cara�̉̐����Ƃ��Ă��[�����킢���o���Ă���A���ɖ����t��Cara���̂�Green
Grasses Grow Bonnie�͂܂��������������قǂ̑f���炵���̐��B���C�u�Ƃ͌����A���������������̃R���T�[�g�ŁA���t�̐����������Ɗ�����B�}�C�N�͂���CD���āACara�F�����̂��낤���H
�`���[�u���[�x���Y�U���������ꂽ���ɁA�}�M�[�E���C���[�̃\���A���o�������\���ꂽ�B�W�O�N��}�C�N�E�I�[���h�t�B�[���h�̖��Ȃ������ɉ̂��グ�Ă��ꂽ���C���[�̂��̃A���o�������炵����i�ɂȂ��Ă���B�P�Ȗڂ�Everytime We Touch����������ȁB�Ȃ̏o���ɑ����P�������͂�����̂́A�}�C�N�E�I�[���h�t�B�[���h�̃t�@���ł���ǂ�ǂ�������܂�Ă������낤�B����What About Tomorrows Children �ɂ͒E�X�B
�}�M�[�E���C���[�̂Q��ڂ����Ȃ�͂���ꂽ�݂����ŁA�W���P�b�g�f�U�C�����炵�Ă����Ă���B�A���o���͂��U���Ȉ�ۂ�������̂̕�����������B����ς胉�C���[�̐��͂��炵���Ɖ��߂Ċ�����B�����O��Ɣ�ׂ�ƁA���C���[�̉̐��̑f���炵���������o����̂̓I�[���h�t�B�[���h�̋ȂłȂ���Ƃ��������B����͊y�Ȃ̏o���ɑP���������ǂ����Ă����邩�炾�낤�B
�}�C�N�E�I�[���h�t�B�[���h�̃��H�C�W���[���������ꂽ���Ƃقړ������ɔ��\���ꂽ�R��ڂŁA����͂��Ȃ�v���C�x�[�g�I�ȃC���[�W�������A�O�Q��Ɣ�ׂ�Ƃ��Â��ɗ���Ă����B�ۂ����ėD�ꂽ�Ȃ�����������Ȃ��B�I�[���h�t�B�[���h��To France��ʂ̃A�����W�ʼn̂��Ă���A���̂P�Ȃ��ɒ[�ɖڗ����Ă��܂��Ă���B�@������̃A�����W�̓g���b�h�F���������Ă���A�I�[���h�t�B�[���h�ՂƂ͂܂�������������͋C�����̂ɐ������Ă���B�܂��I�[���h�t�B�[���h�̃��H�C�W���[�ɓ����Ă���g���f�B�V���i����She Moves Through The Fair�����C���[�͉̂��ʼn̂��Ă���̂������[���B
���߂Ẵ}�M�[�E���C���[�̃x�X�g�B�ǂ����I�[���h�t�B�[���h�̐V�삪���������Ɠ����Ƀ��C���[�̂b�c�����������p�^�[���ɂȂ��Ă���B�����Tubular Bells �V�̔����ɂP���������x��Ă��Ȃ��B���̃x�X�g�͐V��One Little Word���P�ȂƁAEverytime We Touch�̃����C�N�ƃI�[���h�t�B�[���h���̂��̂��R�Ȏ��^���Ă���B�iTo France�̓��C���[���@�[�W�����j���C���[�̋Ȃ������Ȃ�����̂����A�I�[���h�t�B�[���h�̋Ȃ������Ă��܂��ƁA�����Ă��܂����������Ă��܂��B���C���[���@�[�W�����Ń����C�N����Ηǂ������̂ɂƎv���BEverytime We Touch�͑O�̃A�����W�̕����悢�B�I�Ȃ͖���ȂƂ��납������Ȃ����A���X�s���B���C���[�͂�͂�P��ڂ�Echoes���D��Ă���B
�v���Ԃ�̃��C���[�̐V��́A�����ɂ��`�n�q�A���邢�̓\�t�g�|�b�v�X�Ƃ��������ŐÂ��ȋȂ�����ł���B�����̍�i�����Ȃ�}�C�N�̌X�����ӎ����Ă����悤�Ɏv����̂ɑ�����A�Ǝ��̍D�݂̉��y�ɌX�|���Ă����Ă��邩�̂悤�Ɏv����B�m���ɍŏ����烉�C���[�̃I���W�i���Ƃ��Ē�������Ȃ�̕i���Ȃ̂�������Ȃ����A�����}�C�N�̌X�������҂��Ă��܂��}�C�N�t�@���ɂ́A���X��������i���肻����Ă���Ɗ����Ă��܂���������Ȃ��B�����������A�����Ǝv����悤�ȋȂ��������Ă��Ă������Ƃ͎v���̂����B�����A���C���[�̐��͐̂ƕς�邱�Ɩ����A���������͂ǂ����Ă������Ă��܂��B
�܂�������Ȃ������̂����A�f���}�[�N�^���Ŗk�������Ń}�M�[�E���C���[�̐V�삪�����[�X����Ă����B���܂��ܐ��V�h�̂b�c�X�Ŕ����BNeil Young�ACarole king�Ȃǂ̃J�o�[�Ȃ��肾���A���s���ŏڍוs���B����ł�Cyndi Laupe��Peter Cetera�̃J�o�[�܂ł���̂ŋ������B���X�̏��ł̓o�b�N�~���[�W�V���������ׂĖk���̐l���肾�������B�S�̂ɗ������������[�h�ł����Ƃ�̂��Ă���A�J�o�[�Ȃƈӎ������ɒ�����B���ς�炸�̔����B�܂���������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�ŋ߂ł͒��ړx���傫���������Ă���̂��낤���B���X�₵���B
Maggie Reilly / Rowan (2006)
Away wi' the Faeries / Once I Had a Sweetheart / Heartsong / The Star / Promises / All Things are Quite Silent / Who Knows Where the Time Goes / The Trees They Do Grow High / Cam Ye O'er frae France / Miss You / Wild Mountain Thyme
�}�M�[����C���[�̐V��̏��͂قƂ�Ǔ͂����A���̍�i���o�Ă��邱�Ƃ��A���܂��ܒm�����B���肷����@���Ȃ��Ȃ������炸�A���ǐ��V�h�̃g���b�h���X����̍w���ƂȂ����B�ڍׂ͕s�������A���[�x�����v���x�[�g�ɋ߂����̂ŁA���܂�Z�[���X�����҂ł��Ȃ����̂ɂȂ��Ă���Ǝv���A���X�₵�����������Ă��܂��B�������W���P�b�g�ŁA�f�U�C�����������A���J�ɍ���Ă���Ƃ�����B��i���e�����A���̐���̘H���͑��炸�A�g���b�h�ƃI���W�i������荬���A�Â��ɕ���������̂ɂȂ��Ă���B�������A����͂Ƃ����y�Ȃ������A�n���Ȋ����͔ۂ߂Ȃ��B
Maggie Reilly / Looking back, moving forward (2009)
It's a Lonnely Day / Everytime We Touch / Lucy/ Family Man / Stones Throw From Nowhere/ Hold Me / True Colours / Moonlight Shadow / Fifth Moon / Canada / To France / Lilith
�}�M�[����C���[�͒���I�ɐV����o�������Ă��邪�A���̔������̐��̓}�C�N�ɎQ�����Ă�������Ɣ�ׂĂ����F�Ȃ��A����������������X�ɗ^���Ă���邱�Ƃ͊���������B�������ŋ߂̐���i�Ɍ�����X�������A�y�ȁA���邢�͊��Ɍb�܂�Ă���Ƃ͎v�����A�ۗ����ē����̂��閡�킢���o����i�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�@�dchoes���f���炵�����������ɁA���̉̏��͂����Ɉ����o����v���f���[�T�[�͂��Ȃ����̂��낤���B�{��ɂ����ẮA�}�C�N��i�̃J�o�[���܂܂�Ă��邪�A��͂�}�C�N���g�̉��t�Ɣ�r����A���̐����̒Ⴓ�͔ۂ߂��A������ƕ��������Ă��܂��ɉ߂��Ȃ��B���̗ދH��Ȃ�̎�̔\�͂��ł������o�����̂́A��͂�}�C�N�����Ȃ̂��낤�B
�t���A�[�N�ƌ������̃I�����_�̃v���O���b�V�u�o���h�B�Ƃ����Ă��Ƃ��Ă��V���t�H�j�b�N�B���̃A���o���ɂ̓}�M�[�E���C���[���S�ȃQ�X�g�Ń{�[�J����S�����Ă���B�i�P�C�Q�C�T�C�X�j���̑��͂��ׂăC���X�g�B�@�|�b�v�ł���Ȃ���V���t�H�j�b�N�ł���A�ƂĂ������₷���B�}�M�[�̃{�[�J���������̃I���W�i��������i�Ɖ��t���ǂ��������ƂĂ��f�G���B�}�C�N�̃A���o���̂悤�Ƀ��C���e�[�}�ƂȂ�t���[�Y���Ƃ���ǂ���g���Ă��āA�A���o���R���Z�v�g�Ƃ��Ă��ǂ��܂Ƃ܂��Ă���B�}�C�N�̃f�B�X�J�o���[���N���V�J���ɂ����炱��Ȋ����ɂȂ�悤�ȋC������B�Ȃ��A���̃A���o���͌��ݔp�Ղł���A��ςɓ��荢��BLP�͏��L���Ă������ACD��������Ȃ������Ƃ���A�t���A�[�N���g�ɂ�鎩�吧��CDR�ōĔ����ꂽ�B�����ɂ�����Ƃ����������̂��̂����A���͂����炭�}�X�^�[�e�[�v���痎�Ƃ��Ă���A�\�����̂Ȃ������ŁA����CD�{�̂ɂ͒��M�ɂ��i���o�����O�ƁA�t�@���ւ̃��b�Z�[�W�t�̃��������Ă���B�}�M�[�̐����D���Ȑl�Ȃ��ɂ������߁B�݂�������킸�����܂��傤�B
Islands���ł̃{�[�J����S�������A�j�^�E�փW���[�����h�̃\���A���o���B�����炩�Ƀ}�C�N��Earth Moving�̌X���P���Ă���A�|�b�v���̋Ȃ������B�^�C�g���Ȃ�Voices��Moonlight Shadow�̃e���|���v���o������B���C�i�ɂ̓}�C�P���E�f�E�I�[���h�t�B�[���h�ɑ��A�����ŋȂ����E�C��^���Ă��ꂽ���Ƃ̊��ӂ̌��t���L�ڂ���Ă���B
�I�[���h�t�B�[���h�̃t���C���O�X�^�[�g�������̃A���o���ʼn̂��Ă���̂ŁA�����������Ĕ����Ă݂��B�t���C���O�X�^�[�g�͂���ς�I�[���h�t�B�[���h�Ղ̕����������A�����S�̓I�ɂƂĂ��a���A���o���ōD�����B
�����Đ������K�v���Ȃ��قǂ̑�q�b�g�A���o���B���{�ł̓}�C�N�E�I�[���h�t�B�[���h���L���B���݂܂łɂR�̃A���o���\���Ă��邪�A���̍�i����ԃI�[���h�t�B�[���h�ɒʂ���Ƃ��낪����BThe Eyes Of Truth�Ȃ�āA�I�[���h�t�B�[���h�̃C���[�W���̂܂܂����A�A���o���S�̂̕��͋C���ƂĂ��悭���Ă���B����Michal Cretu�͂��ăI�[���h�t�B�[���h�̃A�C�����Y�̐���Ɍg����Ă���B�I�[���h�t�B�[���h�t�@�����y���߂�P���B
�L�������̖��O�����\�m���Ă���B���̃L�������̌��݂ł̍ŐV��B���[�_�[�̃A���h�����[�E���e�B�}�[�̃A�C�������h�l�̕��e�̂��Ƃ��e�[�}�ɂ����A���o���B�S�̂ɃA�C���b�V���g���b�h�̕��͋C���`���A�̂��̂ƃC���X�g�������郁�h���[�^�̖{��̓I�[���h�t�B�[���h�̐��E�ɋ��ʂ�����̂������B���e�B�}�[�́u�����v�ŗL���ȃM�^�[���I�[���h�t�B�[���h���v���o���Ƃ��낪����A�{��Ɍ��炸�L���������̂��̂��I�[���h�t�B�[���h�ɋ߂��B���ɏo�����̃A�C���b�V���G�A�͍ō��B�L�������̃L�[�{�[�h���X�gMickey Simmonds(�~�b�L�[�E�V�����Y)�́A�I�[���h�t�B�[���h�̃A�C�����Y���ŃQ�X�g�Q�����Ă���B
�L�������̃x�[�V�X�g�A�R�����E�o�X�̃\����i�B�������A�M�^�[�̓A���h�����[�E���e�B�}�[���S�����A�L�������̃C���[�W����傫������Ă��Ȃ��B�C�y�ɒ����邢���|�b�v��i�ɂȂ��Ă���B�^�C�g�����u�����̕��Q�ҁv�Ƃł������̂��A�}�C�N�́uIslands�v�ƁuOutcast�v�̓�̍�i�����킹���悤�ȃ^�C�g���Ɏ䂩��Ĕ����Ă��܂������A�������������B
Marillion�Ƃ����v���O���b�V�u�o���h�̃M�^���X�g�A�X�e�B�[�u�E���U���[�̃v���W�F�N�g�o���h�A�E�C�b�V���O�g�D���[�̃A���o���B�{�[�J���Ƀn���i�E�X�g�o�[�g�Ƃ������Ƃ��d�������͋C�Ɛ������������N�p�B�A���o�����S�̓I�ɉ������������悤�Ȗ��ȃ��[�h�ŕ�܂�Ă���B�I�[���h�t�B�[���h�Ƃ̋��ʓ_�Ƃ�����Ɛ������ɂ������A�����Ă����f�B�X�J�o���[������Ƀ��[�f�B�ɂ����Ƃ������Ƃ���B���o�I�ɏЉ�������������A���o���B
���̃��C���{�[�A�f�B�[�v�p�[�v���̃��b�`�[�E�u���b�N���A�̃v���W�F�N�g�A���o���B����ǂ��u���b�N���A�̃n�[�h���b�N�̃C���[�W�͂܂������Ȃ��A�O�ɂӂꂽ�E�B�V���O�E�g�D���[�ɂƂĂ��悭�������͋C�̍�i�ɂȂ��Ă���B�u���b�N���A�̍���҃L�����f�B�X�E�i�C�g�̃��H�[�J����S�ʂɏo���A��V���l�A���l�b�T���X���e�[�}�ɂ����Â��Ń����f�B�A�X�Ȍ���B�����炭�u���b�N���A�t�@�������̂b�c�����Ƃ��͂т����肵�����Ƃ��낤�B�����I�[���h�t�B�[���h�t�@���ɂƂ��ẮA�܂��ɂ������ߍ�i�ɂȂ��Ă���B���m�F���ł͂��邪�A�L�����f�B�X�E�i�C�g���I�[���h�t�B�[���h�t�@���ŁA�u���b�N���A�������n�߂��Ƃ���I�[���h�t�B�[���h�̗��ɂȂ��Ă��܂��A���̃A���o���̃^�C�g�����u���[�����C�g�V���h�E�v�ɉe�����ꂽ�Ƃ����B�������̃u���b�N���A���܂�ŃI�[���h�t�B�[���h�̂b�c�ł͂Ȃ����Ƃ��������i���o�����ƌ������Ƃ́A���̖��m�F�����{�������m��Ȃ��B�܂����l�b�T���X�̃I�[�V�����E�W�v�V�[���R�s�[���Ă���A���l�b�T���X�̃A�j�[�E�n�Y�����̓��[�����C�g�V���h�E���R�s�[���Ă���̂�����A���̊֘A�͂������낢�B ���̏��ł��̂b�c�ɋ����������Ă������A�u���b�N���A�̃C���[�W�Ŕ���Ȃ������Ƃ���A���̃z�[���y�[�W�����������烁�[�������������A�������߂��ꂽ���ƂŔ����Ă݂��B���������܂łƂĂ��悢�b�c�����Ƃ��ł����B���̌㒆��T���v���U�ł̌��������ɍs�������A���炵���R���T�[�g�������B������̊C���Ղ��w�����Ă��܂����B�Ђ���Ƃ����烉�C�u�Ń��[�����C�g�V���h�E������Ȃ����Ǝv��������ǂ���͎������Ȃ������B���C�u�̕����u���b�N���A�̃A�R�[�X�e�B�N�M�^�[�̉����Ⴆ�n���Ă���B���[�����������������̏��ɂ��ƍŋ߂̃R���T�[�g�ŁA�J���O��BGM�Ƀ}�C�N�̋Ȃ��������炵���B
�u���b�N���A�Y�E�i�C�g�̂Q��ځB�O�̍�i��肳��Ɉ�w�A�R�[�X�e�b�N�F�����߂Ă���A���[���b�p�̖������y�W�I�ȗv�f�������Ȃ��Ă���B�u���b�N���A�̃A�R�[�X�e�b�N�M�^�[�̉��͎��ɂƂĂ��S�n�悭�A�L�����f�B�X�E�i�C�g�̉̐����{���Ɏ��R�Ɏ��ɓ����Ă���B�O��Ɠ��l�ɕ������ނɒl�����i���Ǝv���B���̒��̋Ȃ̂������͂��łɃc�A�[�̒��Ŕ�I����Ă���A�C���Ղŕ������Ƃ��ł������A������߂ăX�^�W�I�^���ŕ����ƐV���Ȋ������o����B�u���b�N���A�͍���C���ς��Ȃ�����A�u���b�N���A�Y�E�i�C�g�̘H���������炵���B�]���̃��C���{�[�t�@���ɂƂ��Ă͂���͗ǂ����ƂȂ̂��A�c�O�Ȃ��Ƃ������ɂ͂悭�킩��Ȃ����A�I�[���h�t�B�[���h�̉��y�̃��[�c�ɂȂ���悤�Ȉ�ۂ��������邱�̍�i�Q�́A�����ɂƂ��Ă͂����ւ}�������Ƃ���B
�{���ɗD�ꂽ�~���[�W�V�����̍���i�Ɖ��́A���Ƃ��w�r�[���^���ł����Ă��A�R�[�X�e�b�N�ł����Ă��A�N���b�V�b�N�ł����Ă��A����͂ЂƂ̉��t�̎�i�ł����āA�ǂ̃A�����W�ɂ��ς�������̂ł���̂�������Ȃ��B���C���{�[�̊y�Ȃ��A���̃u���b�N���A�Y�E�i�C�g�̉��t�X�^�C���ɕς��Ă��Ȃ�ɂ���a�����������낤�B
���\�t�g�E�}�V�[���̃J�[���E�W�F���L���Y�̃v���W�F�N�g�A�A�f�B�G�}�X�̃t�@�[�X�g�A���o���B���̍�i�ȍ~������I�ɃA���o�����o�Ă���A���{�ɂ�����CD�X�ł̈����̓}�C�N���������Ɨ͂������Ă���B���̃t�@�[�X�g�A���o���͂��܂��ܓX�ł������Ă����ȂɁA�ǂ��ƂȂ��}�C�N�̓����������Ĕ��������́B���������A���̌���V�삪�o�邽�тɔ������߂Ă��邪�A���̃A���o������ԍD�����B�ŋ߂͂��̃q�[�����O�~���[�W�b�N�̃W�������Ƃ��Ĉ����Ă���ʂ�A�����y�c�ɂ�鉉�t�ɏ����{�[�J���ɂ��R�[���X���������������͋C�́A������𗎂��������Ă������̂�����B���Ƀ^�C�g���Ȃ�Adiemus���U�Ȗڂ�Cantus Iteratus�Ȃǂ́A���H�[�J���X�g�̃~���A�� �E�X�g�b�N���[�̔������R�[���X���������̗̂܂������邭�炢�̌��삾�Ǝv���B�����A�w�������Ƃ��̓}�C�N�̓��������������̂́A�}�C�N�Ɣ�r����ƃN���b�V�b�N�F����������Ɗ����Ă����̂����A�~���j�A���E�x���������o��ƁA�ǂ����Ă����̍�i�Ɣ�r������Ȃ��B�܂��Ă◼��i�ɓo�ꂷ��~���A�� �E�X�g�b�N���[�̃R�[���X���A���̍�i�ƃ}�C�N�̂��̂ƕ�����ׂ���̂��y�����B�}�C�N�t�@���ɂ͂�₨�ƂȂ������邩������Ȃ����A��ςɕi���̍�����i�ł���A�������l�͏[���ɂ���B
��q��Adiemus�Ń��H�[�J���A�R�[���X��S�����A�}�C�N�̃~���j�A���E�x���ł��Q�����Ă���~���A���E�X�g�b�N���[�̃\���t�@�[�X�g�A���o���B���̐l�̐��͂܂��ɓV�ォ��̓V�g�̐��Ƃ����ǂ��g����\�����҂�����Ȃ̂����A�A�f�B�G�}�X�ł����p����Ă����A��ςɃG�L�]�`�b�N�Ȑ����o�����肵�āA���ꂪ�܂��Ƃ��Ă����킢�[���B���̃\���̓A�f�B�G�}�X�Ɣ�r����ƂقƂ�ljp��̉̎��ɂ��Ȃł���A�~���A���̐����ƂĂ��킩��₷���\������Ă���B����1�Ȗڂ���3�Ȗڂ܂ł͂܂��ɓV��̐��������f�B�A�X�Œ����₷���Ȃ��̂��Ă���Ă���悤�Ɋ�����B�i3�Ȗڂ̓s�[�^�[�E�K�u���G���̃R�s�[�j�l��Adiemus���D�������A���x���J��Ԃ��Ē��������Ȃ�ǂ���i���o���Ă��ꂽ�Ǝv���B�}�C�N�̍�i�ł��O�ʂŃ��H�[�J��������Ă��������Ǝv���B
�~���A���E�X�g�b�N���[�̃Z�J���h�A���o���B�\���A���o���ȑO�ɐ��X�̃Z�b�V���������Ȃ��Ă����x�e�����ł��邾���ɁA�t�@�[�X�g�̐������\�������������A�t�@�[�X�g�����|�b�v�X�H���������̂ɑ��A���̃Z�J���h�A���o���́A�ޏ��̖{�����߂鉹�y��O�ʂɏo�����悤�ȋC������B�o�g�̓�A�t���J�̉��y�����[�c�Ƃ���悤�ȃG�X�j�b�N�ȃe�C�X�g���悭�o�Ă��邵�A�ޏ��̓Ɠ��̃R�[���X���ϋɓI�Ɏg���Ă���B�}�C�N�t�@���Ƃ��Ă͂�����̍�i�̂ق����e�ߊ��������Ǝv���B���N�A�A�f�B�G�}�X�̗����R���T�[�g�ɍs�������A�~���A���̐��̓��C�u�ł́A����ɂ��̖��킢���[���A���������B�}�C�N�̃R���T�[�g�ł��~���j�A���x���ŏI��邱�ƂȂ��A�܂��o�ꂵ�Ă��炢�������̂��B
�^�C�^�j�b�N�̉f�悻�̂��̂ɂ��Ă͑S�������s�v�Ȃقǂ��炵�����̂ł��邱�Ƃ́A���Ԃ��F�߂Ă���B���ɂ��̃��X�g�V�[���͍��܂Ō����f��Ƃ͑S���قȂ��@�ɂ�銴���V�[���������Ǝv���B�f������n�߂Ă܂��C�������̂��A���̃T�E���h�g���b�N���S�̂ɃA�C���b�V�����[�h��Y�킹�Ă���A�I�[���h�t�B�[���h�̋Ȓ��ɋ��ʓ_�����������Ƃ������B���炵���f��ƍD�݂̋Ȓ������܂��}�b�`���āA�f��ɂǂ�ǂ�������܂�Ă������B�I�[���h�t�B�[���h�̐����閼����{�C�W���[�̃A�����W�ł�����炱��Ȋ����Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B��ɐG�ꂽ�L�������̃n�[�o�[�I�u�e�B�A�[�Y�̋Ȓ��Ƃ��ƂĂ��悭���Ă���B�S�̂ɗ���郀�[�h�̓V�Z���E�V���V�F�u�[�̔������R�[���X�ɂ��Ƃ�����傫���B�Z���[�k�E�f�B�I����My Heart Will Go On���ƂĂ������������o���Ă���B�f��̈�V�[���ɃW���b�N�ƃ��[�Y���R���q�����ƃ_���X��x��V�[�������邪�A�I�[���h�t�B�[���h���R�s�[���Ă���|���J�ł��������Ƃ��������Ȃ��B(���̋Ȃ����^����Ă���̂́A�ォ�甭������Ă���hBack To Titanic�h�B�������CD�̕�����i�Ƃ��Ă͗D��Ă��邩���B�j�I�[���h�t�B�[���h�t�@���̕��ł܂��f������Ă��Ȃ����A��ɂ����߂ł��B�f���������A�b�c�������~�����Ȃ�܂���B
�t�����X�̂S�l�̃~���[�W�V�������W�܂����O���[�v�B���̂b�c�����Ƃ��͖{���ɋ������B�P���g���y��S�ʂɉ����o�����|�b�v�ȉ��ł͂��邪�A�I�[���h�t�B�[���h�̉e����傫���Ă��邱�Ƃ͖��炩�B���̃M�^�[�̃t���[�Y��t�B�h���̓�����ȂǁA�v�킸�͂��Ƃ��Ă��܂���ʂ������B�ɂ߂��̓��X�g�̋ȁB����͂܂��Ƀ��[���V���C�����̂��́B�I�[���h�t�B�[���h�̉������������y�����āA�G�j�O�}�̗v�f��������Ƃ���Ȋ����ɂȂ�Ƃ����悤�B�������T�E���h�I�ɂ̓I�[���h�t�B�[���h�����t�@���ɂ͕�����Ȃ������邩������Ȃ����A�\���y���߂�ꖇ�B���{�Ղ��o�Ă��邩��傫��CD�X�Ȃ獡�ł���ɂ͂���Ǝv���B
��ɏЉ���X�g�[���G�C�W�̂Q��ځB�S��ȏ�Ɉ�w�I�[���h�t�B�[���h��f�i������Ȓ��ɂȂ��Ă���B�S�̂̋Ȓ��̓A�b�v�e���|�̋Ȃ��������A�قƂ�ǂ��ׂĂ̋ȂɃo�O�p�C�N�A���邢�̓t�B�h���̉������傤�ǃ��b�N�̃��[�h�M�^�[�̖����������Ă���B�{�[�J������ƃC���X�g�������^���̋Ȃ�������A�{�[�J���͈ꕔ�p��̋Ȃ������A�t�����X��ɂȂ��Ă���B�ŏ��̋Ȃ�Lines Of Stone�͂Ȃ��Ȃ��̖��ȁB�`���[�u���[�x���Y�V�̃T�E���h�ɒ�R���Ȃ����ɂ͂������߂̈ꖇ�B
�n���\���E�t�H�[�h�͍��ł����A�a�����Z�h�o�D�����A�����̓X�^�[�E�H�[�Y�̃n���E�\���A�C���f�B�A�i�E�W���[���Y�̃C���[�W�������A�A�N�V�����n�̔o�D�Ƃ��Ă̈�ۂ����������B���̉f��uWitness�v�͖M��ł́u�Y���W�����E�u�b�N�E�ڌ��ҁv�Ƃ����^�C�g���ŁA�n���\���E�t�H�[�h�����x�͌Y�����ɒ���Ɖf����J�O�ɐ�`����Ă����̂��o���Ă���B�Ƃ��낪�A���̉f��͂��̌�̃n���\���E�t�H�[�h�̉��Z�͂�����I�ɂ������ɖ��킢�̐[�����u�X�g�[���[�ł���A�����_�ł��n���\���E�t�H�[�h�剉�̒��ł͂����Ƃ����̍����A�]�����ׂ��f�悾�Ǝv���B�X�g�[���[�̏ڍׂ͏Ȃ����A�����f������ɍs�����Ƃ��ɁA�L��ȓc�����i�̒��Ŕ[�������݂���V�[���Ɏg��ꂽ�ȁiBuilding The Barn�j�������痣�ꂸ�A���傤�ǃI�[���h�t�B�[���h�ɂ͂܂���������Ƃ�����A���̃X�g�[���[�Ɖ��y�̂��߂ɁA�����Ɏ����ɂƂ��ċM�d�ȉf��ɂȂ��Ă���B�^�C�^�j�b�N�̂b�c���Љ�����������ŁA���̂b�c�������Ă��邱�Ƃ��v���o���A����Љ���B�I�[���h�t�B�[���h�̋��ʓ_�����͓̂�����A�f��̔����ȏ���߂�c�����i���A�����̃I�[���h�t�B�[���h�̉��y�ɃC���[�W���Ă���q�̓I���i�ɍ������ƂƁABuilding The Barn�̂��炵���������A�ǂ��Ƃ͂Ȃ��ɃI�}�h�[����n�[�W�F�X�g�E���b�W�̃C���[�W�ɋ߂������Ă���B�b�c�͉f����J���炩�Ȃ�x��āA�X�O�N�ɓ��{�Ŕ������ꂽ�B��ȉƂ̓A���r�A�̃������X�ŗL���B
�X�y�C���̃P���g�n�̉��y�����t����V�l�O���[�v�B���A��i�E���u���ƌĂсi���z�̃O���[�v�Ƃ����Ӗ��炵���j�A�A���o���^�C�g���́u�����v�Ɠ��{�Ղɂ͂��Ă���B���{�Ղ̑тɂ́u�}�C�N�E�I�[���h�t�B�[���h����^�������̃P���g�E�~���[�W�b�N�W�c�v�Ə����Ă���B�����A�P�Ȗڂ̓{�C�W���[��The Songs of the Sun�̌��Ȃł���A�I�[���h�t�B�[���h�̃`���[�u���[�x���Y�V��The Inner Child�ł͂��̃O���[�v��Rosa Cedron���������R�[���X���I���Ă���B���C�u�ł������Əo�����Ă���B�i�����A���̃o���h�S�̂����C�u�ɎQ������Ƃ������킳���������B�j�X�y�C���ƃP���g�ƃC���[�W�����X����Ȃ��C�����邪�A���̃A���o���͂܂��ɃP���g���y�W�Ƃ������i����W�܂��Ă���A���{�l�����X�y�C���̃C���[�W�Ƃ͉������ɂȂ��Ă���B�����I�[���h�t�B�[���h�����ꂽ�t�@���ɂƂ��Ă͏��X���̐���オ��Ɍ����āA�����f�B�̂悳�͔F�߂Ȃ��������������Ȃ������Ă��܂���������Ȃ��B����The Songs of the Sun�̌���O Son Do Ar�́A�i���{��ɖ�Ɓu���̉��v�ƂȂ�炵���j�I�[���h�t�B�[���h�łɕ����邱�Ƃ̂Ȃ��ǂ��������Ă���A�����m�炸�ɒ�������AThe Songs of the Sun�̕ʃo�[�W�������Ǝv���Ă��܂���������Ȃ��B�I�[���h�t�B�[���h���̗p���Ȃ������t���[�Y���������Ƃ��ł��A�\���y���߂�B�I�[���h�t�B�[���h�����̋Ȃ��u���z�̉́v�Ƃ����^�C�g���ɂ����̂́u���z�̃O���[�v�v�̋Ȃ�����Ƃ������Ƃ��낤���B
���l�b�T���X�̃{�[�J���Ƃ��Ă��̐l�͌��\�L���B���̃\���Ƃ��ĂX�O�N�ɔ������ꂽ��i�B���̃^�C�g���ȂƂ��ăI�[���h�t�B�[���h�̃��[�����C�g�V���h�E���R�s�[���Ă���B�S�̓I�Ƀ|�b�v�ȋȒ��ŁA���l�b�T���X�̃C���[�W����͂����ԈقȂ�A�v���O���b�V�u�̃C���[�W�͔����B�������A�S�̓I�ɂ����Ȃ�������Ă��āA�ƂĂ������₷���B���ă��[�����C�g�V���h�E�����A���Ȃ̃C���[�W�������Ȃ����ƂȂ��A���Ɏ����̃C���[�W����荞��ł��čD�ӓI�ɒ�����B���̌�R���T�[�g�ł��K���̂��Ă���炵���B�l�͂��̐l�̐��́A�}�C�N��Incantations�Ő_��I�ȃ��H�[�J�������Ă����}�f�B�E�v���C�A�̐��ɂǂ��ƂȂ����Ă���悤�ȋC�������āA���̃��[�����C�g�V���h�E�̓}�f�B�E�v���C�A���̂��Ă���悤�ȍ��o���o�����B
�T���E�u���C�g�}���Ƃ������l�\�v���m�̎�B�������̐l�̎��͑S���m��Ȃ��������A����b�c�X�̃q�[�����O�~���[�W�b�N�R�[�i�[�ɂ����Ƃ���A�˔@�}�C�N��Voyager�Ɏ��^����Ă���uWomen
Of Ireland�v�̏����{�[�J�����@�[�W�������������āA���ꂪ�܂��ƂĂ��f���炵���X�̐l�ɕ����čw����������B�uWomen
Of Ireland�v���̂��̂��A�C�������h�`���Ȃ�����A�}�C�N�̃R�s�[�ƌ����킯�ł͂Ȃ��̂����A�ƂĂ��f�G�ȉ̐��ł���A�̎����p��ɂ�鎩��ŁA�ƂĂ��ǂ��o�����B�܂������Ă���킩�������A���̃A���o���̃v���f���[�X��Enigma�̍�i�Ɋւ�������Ƃ̂���Frank
Peterson�ł���A�^�C�g���Ȃ�Eden�͂����ɂ�Enigma���[�h���B���ɂ��^�C�^�j�b�N��My
Heart Will Go On���C�^���A��ʼn̂�����A�J���T�X��Dust In The Wind���R�s�[������A���肾������B�����A�ʂ��ŕ����Ɠ��{�̗̉w�Ȃ̉̎肪�l�̃q�b�g�Ȃ��̂����A���o���݂����Ȋ������o�Ă��Ă��܂��͓̂�B
STYX�͂V�O�㖖����W�O�N�㏉�߂ɂ��Ȃ蔄�ꂽ�o���h�ŋL�����Ă���l���������낤�B���b�N�n�ł͂��邪�A���v���O���F������A���̃A���o���͂ǂ���R���Z�v�g�F���������Ƃł��悭�m���Ă���B���������傤�Ǒ�w�����������ŁA�ꎞ�����ɂȂ����B���̃A���o���͍ł��悭���ꂽ��i�����A�����ɍł��ۂ����ėD�ꂽ��i���Ǝv���B�Ȃ������ł��̍�i���Љ�邩�Ƃ����ƁATubular Bells �V���Ă��ĂӂƁA���̃X�g�[���[�W�J�Ƃ��̃p���_�C�X�V�A�^�[�Ƃ̓W�J�������ɂƂ��Ă悭�������������A���炽�߂Ă��̍�i���ĕ]���������炾�B���݂����p���_�C�X�V�A�^�[�̉h�͐������X�g�[���[�������������̍�i�͂قƂ�ǂ����h���[���ł���A�`����AD1928�̃��C���t���[�Y�����ԕ���The Best Of Times�ƃ��X�g��AD1958�ŌJ��Ԃ���Ă���B����Half-Penny, Two-Penny ����A.D.1958�̗���̃��h���[�͍��ł��g�k�����邭�炢�̑f���炵�����ꂾ�Ǝv���B���̓W�J��Tubular Bells�V���āA���炽�߂Ă��̍�i�ɐe�ߊ������������B�Ō�ɏ��i��State Street Sadie�����Ă���̂��}�C�N�ɋ߂����̂�������B���������Ƃ�������������Ǝv�����A�����ɂƂ��ẮA���̍�i�Ǝ��ɏq�ׂ�Jackson Browne���D�����������n�����������炱���A�}�C�N�ɍ��̂߂荞��ł���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B
�W���N�\���E�u���E���ƌ����قƂ�ǂ̐l��Running On Empty,
Late For The Sky���\��ɂ�����ł��낤���A�����Ƃ��Ă͂��̍�i�������Ƃ���ȃW���N�\���u���E���̍�i�B�}�C�N���D���ɂȂ�܂ł̓W���N�\���u���E���Ɉꎞ�͂܂��Ă����BRunning
On Empty�̑O�ɂ����邱�̍�i�͏����̃W���N�\���u���E���Ƃ��Ă̓��b�N�F�������A���܂荂���]�������������Ă��Ȃ��悤�����A���̊y�ȂƓW�J�͑f���炵���Ǝv���B�}�C�N�Ƃ̊֘A���͂Ȃ��ƌ����Ă�������������Ȃ����A�����ȊO�ɂ��A�����N��\���Ă��鏬�q������W���N�\���u���E���D���ł���A����Hold
Out���D�����Ƃ����̂��āA����͉�������ɋ߂����̂�����̂�������Ȃ��Ǝv���Љ���B���ł����܂ɂ��̍�i���Ɗw������̑z���o���h�邩��A�����ɂƂ��Ă͑O�ɏЉ��ParadiseTheatre�Ƌ��ɖ��i����ɂ�������i�B�����A�ŋ߂̃u���E���͂b�c���Ă͂�����̂̂���ȂɍD���ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���M�q�Ƃ����l�ɂ��Ă͎����͂قƂ�ǒm��Ȃ����A���[�����C�g�V���h�E���J�o�[���Ă��邾���ł���CD���w���B���̐㑫�炸�̉̂����Ƃ��킢���W���P�b�g�ŁA�A�C�h���n���Ɗ��Ⴂ�����������A�Ȃ��Ȃ��̎��͔h�炵���A�J�o�[�ȂƃI���W�i�����~�b�N�X���Ă��邱�̃A���o�����S�̓I�Ɉ��S���ĕ�����B���āA���[�����C�g�V���h�E�����A�Â��ȃC���g������n�܂�A����グ�Ă����o���[�h���ɃA�����W���Ă���A�Ȃ����ȏ�[�������d�オ��ɂȂ��Ă���Ǝv���B�p��̔������������肵�Ă��邵�A�����郀�[�����C�g�V���h�E�̃J�o�[�̒��ł��A�����Č���肷�邱�ƂȂ��t�@���ɂ͂����߁B
Kokia�Ƃ������{�����V���K�[�ɂ�郀�[�����C�g�V���h�E�̃J�o�[�����^����Ă���V���O��CD�B������̃��[�����C�g�V���h�E�͗��M�q���@�[�W�����Ɛ����ŃA�b�v�e���|�ŁA�I���W�i���Ɣ�r���Ă����n�[�h�ȃA�����W�ƂȂ��Ă��邪�A���̐l�̑f�G�Ȑ������̃n�[�h�ȃA�����W�Ƃ��܂��~�b�N�X����Ɠ��ȃ��[�h�����܂��������o���A�Ƃ��Ă��悢�d�オ��ɂȂ��Ă���B�I���W�i���̂Q������������ŁA�}�C�N�̑��̋Ȃ��J�o�[���Ă��炢�����Ȃ�B�����߁B
Radio Edit / Extended Version / Nova Mix (club version) / Space Mix (less vocal version) / To France
�ڍׂ͂悭�킩��Ȃ����A�����V���K�[�ɂ��To France�̃N���u���@�[�W�����ɂ��J�o�[�B���̐l�̍�i������������A�V���f�B����[�p�[��Time After Time�l�ɃJ�o�[���Ă���V���O��������B������̂ق����]���ɂȂ��Ă���悤���B���̃V���O����To France�ƂȂ����킯�����A���̑I���̊���悭�킩��Ȃ��B�Ȃ͌��Ȃ̏�I�C���[�W�����S�ɏ����������h��ȓW�J�ɂ��N���u�~�b�N�X������A�����߂�����̂ł͂Ȃ��A�P�Ƀ}�C�N�̑�\�Ȃ̃J�o�[������Ƃ����ɂ����Ȃ��B�������A�ŋ߂̃}�C�N�̃V���O���̃~�b�N�X��肩�͂܂����ʂɒ�����ق����Ƃ͎v���B
Sweet is the Melody / The Dance You Choose / Rise Again / Moonlight Shadow / Medley : Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World / Out of the Woods / Driftwood / Some Days / Once in Every Life / Love So Rare / Getting Dark Again / To Say Goodbye to You / The Island / The Gift
2002�N�āA���[�����C�g�V���h�E�̐������e���r��CM�ŗ���o���A�}�C�N�t�@���ɏՌ���^����Ƃ��������i�H�j���N�������B�L���m���̃v�����^�[��CM�Ƀ��[���C�g�V���h�E�̃J�o�[���̗p����A�̂��Ă���͎̂12�̏����Ƃ����̂������������B����͂��̃f�r���[�A���o���B������[�����C�g�V���h�E������ړ��Ăɓ��肵���̂����A�A���o���S�̂̃��x���̍����ɂ���ɋ������ꂽ�B�S�̂ɃJ���g���[���Ɏd�オ���Ă��邪�A���̉̏��́A�Ȃ̃��x���͍����W���P�b�g�ʐ^��12�̏������̂��Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B���[�����C�g�V���h�E�����J���g���[���ɃA�����W����Ă���Ƃ����A�̏��͂ƁA�Z���X�̂悢�A�R�[�X�e�B�N�M�^�[�A�t�B�h���ƃI�[�P�X�g���̃A�����W�������ɗZ�����Ă���A�}�C�N�t�@���ɂƂ��Ă���a���������B���[�����C�g�V���h�E�̃J�o�[�̒��ł����x���̍������̂Ƃ����邾�낤�B
Mr. Sandman / Surfin' U.S.A. / Bright Eyes / Lord Of The Rings / The Wizard / Spread Your Wings / Mordred's Song / Black Chamber / The Bard's Song / Barbara Ann / Long Tall Sally / A Past And Future Secret / To France / Theatre Of Pain
�z�[���y�[�W�����Ă�����������������Љ���������A���o���B�w�r�B���^���o���h�Œ����̂悤���������͂܂������m��Ȃ������B����̍Ę^�ƃJ�o�[�W�ɂ��A���o���ŁA�ʏ�Ղɂ���ׂ��Ȃ�|�b�v�Ń����f�B�A�X�ɂȂ��Ă���炵���B���̒��Ń}�C�N��To France���J�o�[���Ă���̂��ʔ����B�j�����H�[�J���ɂ��A�����Ă��n�[�h��To France�͌��ȂƂ͑傫�����̈�ۂ��قȂ��Ă��邪�A����͂���Ŋy����������B����ȊO�̋Ȃ��w�r�B���^���Ƃ͂�����ƈႢ�A�����₷���Ȃ������B
����܂��Љ�����A���o�����ł���lj����ĎQ��܂��B�����ɂȂ������ł��������߂��Ă���������b�c���������܂�����A���[�������肢���܂��B