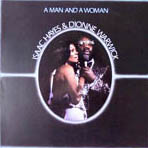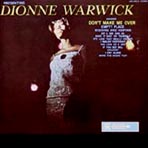
PRESENTING DIONNE WARWICK(SCEPTER)1963
バカラック=デイビット・コンビと組んで世に出た最初のレコード。今ではエレガントなロッカ・バラードにしか聞こえない「Don't make me over」も聞いた時レコード会社の重役がアタマを抱えたというから、これは当時としては非常に過激なレコードだったはず。R&Bと言い切るには泥臭いところがなさ過ぎるし。
ディオンヌの歌唱もまだまだ野性味たっぷりで瑞々しく、後年のマイルド過ぎて流れていってしまうという「完璧すぎるがための欠点」もありません。「ジップ・ア・ドゥーディー・ダー」なんて元気がよくてパンチが効いている。他人の曲の「アンラッキー」で後半テンポが急変するところに、はやくもバカラックの野心が。バカラック・ナンバーとしては、後にサーチャーズが取り上げた「This empty place」等、やっぱりソウル色が強いざっくりしたものが目立ちます。個人的なベスト・トラックは「I smiled yesterday」
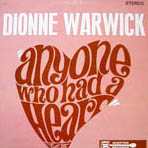
ANYONE WHO HAD A HEART(SCEPTER)1963
のっけの「Anyone who had a heart」から、前作とは声が別人のように違っていて驚かされます。ディオンヌの歌手としてのソフィスティケイションを目的として、バカラックがかなり無理があるところまでキーを上げたために、ソウル色は消えて新しい歌唱法になっているのですが、まだディオンヌもそれになれていないのか、ところどころニュアンスが消えて、カマトトアイドルのようになるのが苦しい。
「This empty place」「Don't make me over」「I cry alone」といった前作からの再演曲を聞いてもその変化は明らか。そんな訳で歌はまだまだ過渡期といった感じですが、「Please make him love me」のぐっとフェミニンになっている歌声は結構いい感じ。
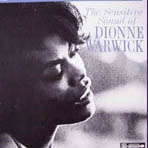
SENSITIVE SOUND OF DIONNE WARWICK(SCEPTER)1965
前二作のような試行錯誤の上、その後のディオンヌのトレード・マークになるシルキーでマイルド(悪くいうとパンチも毒もない)な歌唱法が花開いたと思われるのがこのアルバム。
マイ・フェア・レディ誕生にはしゃぐヒギンズ教授のごとく、バカラックもいつもより多めにオリジナル曲を書き下ろしています。それがまた、全部が難易度が高い曲ばかり。「ベイビー・イッツ・ユー」を彷彿とさせるシャラララ・コーラスが入る「That's not the answer」も、「So long Jonny」パターンのイントロから想像もつかないようなメロディ展開をする「is there another way to love you」もいいけれど、この盤はシックな魅力の「それは言わないで」に尽きる。特に、間奏でミュート・トランペットとユニゾンでスキャットするところは、何度聞いてもヤられます。
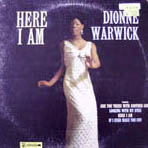
セプター期で、泥臭い意味でジャズっぽいアルバムといえばこれでしょうか。ラストがガーシュインの「I love you Porgy」、ディオンヌ自身がピアノを弾く「This little night」はニュー・オリンズ・ジャズ風味ということで、『ショウ・ボート』のようなミュージカルの音楽を彷彿とさせます。
バカラックの曲も、ゆったりとした水面を渡っていくような美しいバラードと、ドラマティックな盛り上がりを見せるステージ映えしそうなものの二本立て。チューバがコミカルなアクセントをつける「Long day,short night」、ラブリーな「Window wishing」がいい。暑い日の昼下がりに聞きたいような盤。
どうでもいいけれど、ジャケの半目のディオンヌの顔とポーズはすごいものがありますね。「化粧前だから撮すナー!」とカメラマンを制しているんでしょうか。
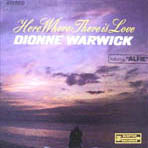
HERE WHERE THERE IS LOVE(SCEPTER)1967
ジャッキー・デシャノンによる名唱で名高い「世界は愛を求めている」ですが、最初ディオンヌは「あたしゃこんな歌、歌わないわよ」と却下したそうです。デシャノン版の後に吹き込まれたと思われるこのアルバムでのバージョンでは、オリジナルの印象深いフレンチ・ホルンのフレーズを抜いてハープを入れているのですが、差をつけようとしたのかディオンヌがかなりの高い音程で歌ったため、残念ながらゴスペル的なスケールが消されて、かなり表現が平坦なものになっています。
他にもダスティ・スプリングフィールドが歌った「I just don't know what to do with myself」も高音にシフトしたため、「白人ソウル歌手よりソウルが下手な黒人シンガー」という欠点が早くも露呈した結果に。
逆に非バカラック曲の「I never knew what you were up to」の雰囲気がいいだけに惜しく、「絶対コントロール下の歌姫」の難しさを感じさせます。最後のカントリー・バージョンの「風に吹かれて」の唐突さはご愛嬌。
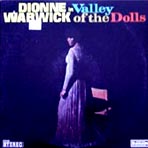
VALLEY OF THE DOLLS(SCEPTER)1968
バカラック=デイヴィッド=ワーウィックのトリオのひとつの到達点であるところの代表作、「サンホセへの道」が収められているところからも分かるように、この組み合わせの円熟期の作品。
非バカラックものとしては、『人形の谷間』のテーマ曲のカバーが彼女の代表曲のひとつとなり、それを受けてか同じ原作者のノヴェルの映画化作品『ラブ・マシーン』のサントラでもバカラック=デイヴィッドのプロデュースで主題歌を歌っています。
エレガントにボサにアダプトされた「ビートでジャンプ」は残念ながらバカラック・アレンジではないけれど、「As long as there's an apple tree」「Walking backwards down the road」という隠れた名曲あり。
後、詩を読んでいない多くの人が誤解してますが、「サンホセへの道」って「サンホセまでドライブ」っていう楽しい曲じゃなくて、夢やぶれて故郷に帰る人の歌なんですよね。
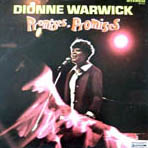
PROMISES,PROMISES(SCEPTER)1969?
タイトルの通り、同名ミュージカルからの三曲を軸として作られたアルバム。でもバカラック本人によるアレンジは三曲ににとどまり、他の曲はピーター・マッツとドンセベスキーが担当しています。
聞きどころは、非常にステージ映えしそうな下世話に華やかなマッツ仕事。セベスキーとは実はあんまり相性がよくありません。ホーンとはよく合うけれど、チェンバロとかのバロッキンな小道具に耐えるには、ちょっと健康的過ぎるきらいが。
私的ベスト・トラックは「Yesterday I heard rain」
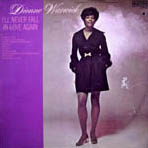
I'LL NEVER FALLIN'LOVE AGAIN(SCEPTER)1970
この頃からダブルジャケットに。プロダクションとしてはそろそろ飽きられてきた頃だけれど、結構底力を見せていて、いい曲多数。サビが冒頭に来る一曲目の「The wine is young」から持っていきます。
後にステファニー・ミルズはカバーする「Loneliness remember what happiness foget」は本家の方が電子オルガンが入っていてタイト。「Paper Mache」は偽ボサの傑作です。ラストはなぜか「マイ・ウェイ」を高らかに歌い上げちゃっているんですけれど‥。

オリジナルとしては、セプターでのラスト・アルバム。バカラックがアレンジも含めて全部手がけたのは四曲。
あまり有名でない曲としては、非常にドラマティックな出だしで始まる「Check it time」と、ペダル・スティールのほのぼのとしたカントリー調のイントロから一転して二転して三転してと、つかみどころのない展開を見せる「The green grass starts to glow」があります。面白くはあるけれど、共に間延びしていて完成度は低く、バカラックがちょっと行き詰まっているのが見て取れます。このちょっとゆるい感じが『失われた地平線』につながって、とんでもない失敗を引き起こすのですが‥。
後にセルメンがブラジル’77時代に取り上げる「Walk the way you talk」はさすがにタイト。他ではマーティ・ペイチがなかなかいい仕事をしています。でも全体的な印象はちょっと散漫かな。
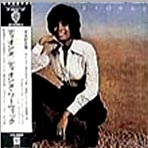
セプターからワーナーに移った秘蔵っこのために、まるではなむけのようにバカラック=デイヴィッドがプロデュースした版。これが三人で作った最後のレコードに。
非常にゆったりとした曲の多いレコードで、ちょっと影が薄いところもあるのですが、私は割と好きです。バカラックの曲としては、唯一キャッチーな「If you never say goodbye」、非バカラック曲としてはレスリー・ダンカンの「Love song」が印象に残ります。
この後、『失われた地平線』が失敗して、バカラックのモチベーションが下がって音楽の世界から部分的にリタイアしようとしたため、契約破棄をめぐる醜い争いが起きてトリオは空中分解。それを知っていると裏ジャケットの仲がよさげなスリー・ショットが悲しい。
A MAN AND A WOMAN/ISAAC HAYES & DIONNE WARWICK(ABC)1973
黒いバカラック的な資質を持つ歌手とのジョイント・ライブ二枚組。非常に豪華な組み合わせですが、コンサートというよりディナー・ショウ感が漂います。
バカラック・ファンの聞きどころはメドレー二つ。「I just don't know what to do with myself〜Walk on by」はスローに落として掛け合い形式で。
ジミー・ウェッブの「恋はフェニックス」に「I say a little player」のフレーズが差し挟まるパターンは、アン・マレーとグレン・キャンベルがやったパターン。

最後に一緒に仕事してから約12年。久々にバカラックと組んだのはエイズ基金のためのオールスターによるテーマ・ソングという華々しい舞台だった。スティービー・ワンダーのハーモニカによるイントロがあまりに印象的なディオンヌ&フレンズ名義の「愛のハーモニー」は、もともと『ラブINニューヨーク』のサントラでロッド・スチュワートが歌ったもの。グラディス・ナイトにエルトン・ジョンと他のメンバーも豪華で耳をひく。
更にアルバムでは、共作で当時バカラック夫人だったキャロル・ベイヤー・セイガーのバージョンがヒットした「愛は果てしなく」をカバー、三曲の新曲をバカラックに書き下ろしてもらっている。どれもメロウなこの頃のバカラックらしい、いい曲だけれど、それ以上にスティービー・ワンダーが書いた曲がバカラックっぽいのがおかしい。

DIONNE SINGS DIONNE(Victor)1998
何というのか、「いい」というより、「面白い」90年代企画盤。
女子必殺歌手のエル・デバージとの「リーチ・アウト・フォー・ミー」のデュエットには、まんま「ベスト・オブ・マイ・ライフ」なコーラスでエモーシュンズが参加。サルサの「サンホセ」はクラブプレイ可。
聞きどころは多いけど、今回は何と言っても悪ガキラッパー軍団を従えての「世界は愛を求めてる」ヒップ・ホップ・バージョンにはっちゃけたものが。しかもその「ヒップ・ホップ・ネイション」の立て役者が、かつてディオンヌ(ラップは憎しみを呼び起こすから反対よ!という迷惑な運動をしていた)にデビューアルバムのメジャー発売を妨害されたドック・パウンドのクラプト。二人に何があったのか。
原曲の歌詞の持つゴスペル的世界観を無理矢理ブラック・コミュニティの団結に当てはめて、服役経験のある(者もいる)メンツが「ディオンヌおばさんと同じ道を行くぜ」とか言ってるのを聞くと、愛の夏は遠くになりにけりと思います。笑ったのはマイク・ジェロニモのラップの「俺にドラッグをくれよ、愛っていうやつをな」(大爆笑)