
Out of the woods/The George Shearing Quintet(Capitol)
2001年一発目の収穫物。私は『ロココ・ジャズ』とかラロ・シフリンの『マルキ・ド・サド』とか、バロック・ジャズに弱いんだってば!
ラウンジィなピアノのジョージ・シアリングのために、当時新進ヴァイブ奏者だったゲリー・バートンがバロック風味の曲を書き下ろして作った、なんて私を殺す気か!って感じ。「J.S.バップ」とかタイトルからして楽しい。そして「ダブル・サンバ」という曲の小粋さときたら!シアリングが弾くハープシコードもなかなかです。

Birth of the cool/Miles Davis(Blue Note)
「マイルス・アヘッド」より更にこっちの方が私は好きかも!言わずと知れた室内楽編成ジャズの名盤が、件のルディ・ヴァン・ゲルダーの24ビット・リマスタリング・シリーズから紙ジャケで登場。クロード・ソーンヒル楽団から発想を得ているだけあって涼しすぎるけれど、夏の夕暮れよりは冬の室内の方がピンときます。ジョン・ルイスがMJQを生み出すきっかけになったというのも納得のすかし加減もいい感じで。
「ミロのビーナス」という曲は、聞くたびにアブストラクト・アートの隣でポーズを取るドヴィマというヴォーグ・モデルを思い出します。何故かは知らないけれども。

Jutta Hipp Quintet(Blue Note)
同じ頃RVGシリーズから再発されたこちらはアナログで入手。ブルーノート、男子必携盤といえばリー・モーガンの『サイドワインダー』、女子なら『ヒッコリー・ハウスのユタ・ヒップ』っていうのは私が勝手に決めたことだけれど、彼女のブルーノート・デビュー盤であるこちらは、ジャケからして乙女っぽいでしょ。つうかゴスっぽい。
ドイツから来米した時はバップの嵐で、クールな奏法の彼女はとまどったという話だけれど、意志の強さを感じさせるタッチの鋭さと瑞々しさには、少女の頑な心に呼応する何かがあると思います。

High winds White sky/Blues Cockburn(Columbia)
この間の大雪はすごかったね。電車から見る雪の東京は美しかったですよ。そして、雪に降り込まれた日に聞きたいナンバーワン・レコードといえば、これとジョニ・ミッチェルの『逃避行』でしょう。中ジャケの寒そうな景色までよく似ているし。
ダイアモンドダストのように弾けるクリアーなギターの音色に彩られた素晴らしいシンガー・ソング・ライター・アルバム。胸に染み入ります。

Waterbeds in Trinidad/The Association(CBS)
祝・CD再発。私がアルバムを全部持っている唯一のグループのラスト。デビューした時は全員スーツだったくせに68年頃はサイケで、70年代を迎えるとメンバーの髭率100%になっちゃうそのフットワークが好き。スタイルがないともいえますが。
このラスト・アルバムはもはやソフトロックではないけれども一番好きなアルバムで、ロック出身でもフォーク出身でもこのように洗練されたフォーク・ロックは作りえないと思います。特にタイトなリズムと荘厳で迫力あるコーラスで攻める「Snow
Queen」のカバーは見事で、オリジナルのシティを超えたかも。

Going Home/Geoge Fame(Epic)
同じシリーズで今回再発されたこちらの方が、ソフトロック・ファン向きではあります。「yeah-yeah」でお馴染みモッドなジョージー・フェイムの意外なポップ・アルバム。しっとりと物憂げなクラシック・フォーの「Stormy」のカバーや、「ビートでジャンプ」パターン使いまくりのテディ・ランダッツォ作「Happiness」なんてギャル殺し。
でもやっぱりこのレコードの魅力は、裏ジャケットの自転車疾走シーンに見られるような「男の子っぽさ」だと思うんですけれど。声質そのものがブルー・アイド・ソウルなボーカルに軽くノック・アウト。
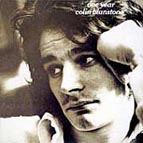
One Year/Colin Blunstone(Epic)
エピック再発といえば、これも忘れるわけにいかないでしょう。元ゾンビーズのボーカルのファースト・ソロ・アルバム。ポール・マッカートニーが書きそうなポップな名曲揃いですが、ナイーヴでアンニュイな声のため全編霧がかかったようなミステリアスで上品な雰囲気に包まれています。
ティム・ハーディンのボッサ調名曲「Misty Rose」の数多いカバーの中でも、ここに収められているバージョンはベスト。間奏に入るマイケル・ナイマン調の室内楽的ストリングス(引用はモーツアルトなんだろうけれど)は何度聞いても素晴らしい。
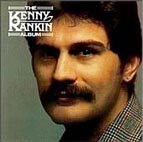
The Kenny Rankin Album(Warner)
最近数寄屋橋のハンターに行くと、そのたびにお店が縮小していて悲しい。歌謡曲EPで気になるものを探しに行ったのだけれども、「店主も最近見かけないし、この店ももう長くないかもしれない」と考えて、サンプル盤コーナーからこちらを捕獲してきた。
ケニー・ランキンのこの76年盤は、「グルービン」のメロウなカバーで知られているけれども、私的なハイライトは「Here
comes the Rainy day」と「When sunny gets blue」。ドン・コスタの繊細でまろやかなアレンジとランキンのマイルドな歌声が相まって、極上のAORナンバーに仕上がっています。全然ジャジィじゃないのが笑えるが。

Querelas do Brasil/Quarteto em cy(Philips)
更に「ワールド」の棚でこちらを発見。七百円。キズ盤表示だけれども、ハンター検盤なので素人にはどこにキズがあるんだか分かりません。ユニオンなら「A-」の盤質。やっぱり侮れないよ!ソルト・ウォーター・タフィだってここで入手したんだから。
バイーアの四人姉妹として有名な彼女たちですが、この70年代半ばの再結成盤では既に二人メンバー・チェンジしています。それでも、甘い草の香りがする風が吹き抜けていくような至福の四重奏は健在。ジョルジュ・ベンやカエターノのモダンな曲もおっとりと品よくこなしてくれます。春の気配がするよく晴れた朝に聞きたいレコード。

Singles & More/L→R(Polydor)
L→Rは様々な意味で非常に気の毒なバンドだった。ホワイト・ドゥーワップ〜アンダース&ポンシア〜ビリー・ジョエルの系譜に属する、「日本人好みの洋楽」を書くイタリア系アメリカ人ソングライターのような黒沢健一の作家性は正確には評価されていない。この芸風の先達には伊藤銀次と杉真理がいるが、彼の方が職人的に曲作りが上手く、女の子がキュンとするタイプの声のボーカリストだった。小沢健二が郷ひろみの後継者なら、黒沢健一はチェッカーズ時代の藤井郁弥の正統な後継者だったのである。
このポリスター時代のベストはラジオジェニックないい曲満載。バックの音にセンスがないところはこの際目をつぶろうじゃないか。