ハリソン・フォードとミッシェル・ファイファーは大学教授の夫と元チェリストの妻という人も羨むカップル。しかし、娘を大学の寮にやってから、妻は奇妙な物音や現象で霊の気配を感じるようになる。やがて夫の浮気と意外な真実が明かされる‥というホラー・サスペンス。
スタジオの力が絶大で、作品の質を決める要素があまりにも多様なためハリウッドにおいては通用しにくい「作家主義」を適応できる数少ない映画監督を挙げろとといわれたら、私は迷わずにロバート・ゼメキスの名前を挙げます。
そしてゼメキスの特色のひとつとして、「エピソードの情報が多い→あれもこれもと詰め込んだあげく走り出す映像のドライブ感」というのを挙げておきたい。予定調和的な空想科学少年小説であるはずの『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でさえ、マイケル・J・フォックスが過去の世界から現代に帰ってくるまでにクリアしなければいけなかった難関が異様に多かったのを思い出してもらいたい。
その作家性が魅力として生きた最たる作品はデビュー作である『抱きしめたい』だったと思います。で、盛んに「ヒッチコック調」といわれる今作はどうなのかというと、話の母体がシンプルであるのに対して、シチュエーションがやたらと過剰に多い。しかも画面が走りません。
大学都市郊外のがらんとしたお屋敷で孤独に心を蝕まれていく妻の様子も描かなくてはならないし、幽霊映画として現象を積み重ねてじわじわ怖がらせるようなこともしなくてはならない。
夫の浮気疑惑も解明しなくてはいけないし、死んだ愛人の行方も探さなくてはならない。本人も秘密を抱えているし、ミッシェル・ファイファーは一人で大忙しです。おまけに不安を煽るためだけに隣家の殺人疑惑なんて挿話が入るしね!『ラブ・セレナーデ』『女と女と井戸の中』のミランダ・オットーが、迷惑な言動のお隣さんに扮していてはまり役ではあります。
そんな風にいろんな要素をそれなりの格調の高さを保とうとしながらさばいていくのにいっぱいいっぱいで、割と肝心なところがおざなりになっちゃったような気がします。
例えば、ミッシェル・ファイファーが「大学教授の妻」で元はアーティストであるという設定は、本来ならもっと丁寧に描かれるべきところではあるはず。自己実現の道を閉ざされたのが理由で娘(連れ子というのもポイント)を溺愛・子供が巣立っていったために自分の空洞感と向き合わざるを得なくて神経過敏に、という経過を心情を交えて追わないと、最後の彼女の行動はすごく唐突に見えます。
ラスト二十分は次から次へと!サスペンス・スリラーで監督がやりたかったであろうシーンの連続なのですが、その多さにお腹がいっぱいになって何だかどうでもよくなってきちゃうんですよね。結果としては冗漫。
そして「ヒッチコックが五十年代にやりたかったのに出来なかったオチ」については、まあ、役者不足ですよねどう見たって。でもその感想を分かち合うためにも観ることをお勧めしておきます。
パンフレット→ロバート・ゼメキスの作家論(きちんとしたものがあって然るべき)
スーベニール→シルバーのペンダントトップ・ファイファーが隣家のために用意したバラとワインが入った籠(ウェルカム・スーベニール)
リファランス→『レベッカ』『崖』(アルフレッド・ヒッチコック)
おじさんの結婚式とおばあちゃんが意識不明で倒れるところから始まる一家の一夏を、末っ子の少年の視点から小津調で描いた「アジアン・エクスプローテーション映画」。
そりゃ、悪くないけれどエドワード・ヤンがこんな映画を撮る必要がどこにあるのか疑問で。ヨーロッパの映画祭じゃ受けますよ、それは。でも『エドワード・ヤンの恋愛時代』や『カップルズ』が好きな私としては、台北という都市環境を活かしたアーバンな映画を作って欲しいんですよ、彼には!
お母さんは新興宗教にはまり、お父さんは初恋の女性と再会して揺れ動き、お姉ちゃんはマンションで隣の女子のボーイフレンドに惹かれて急速に大人になっていく・というのも、ちょっと図式的過ぎるのでは。超好景気時代に作られた『恋愛時代』に比べて、ただいま台湾は絶不調の不景気だという経済状況は各エピソードに反映されていますが。
ただ、ティーンの描き方なんかは相変わらずイヤミじゃなくて上手。後半の、「母と娘で一人の男を取り合いそれが殺人事件に発展」という展開はベタだとしても。あと、デートの選択肢として当たり前に「クラシック・コンサート」があるのっていいよね。
音楽の使い方は効いていて、お父さんが勤める会社に仕事をもちかけられる日本人ゲーム・デザイナーイッセー尾形と彼が意気投合するのが、カーステレオから流れるオペラのアリアがきっかけだったり、カラオケ・バーで「上を向いて歩こう」と共にドビュッシーの「月光」を弾いてしまったりするところなんかはよいです。イッセー尾形はみじめなサラリーマン、と思いきや外国映画では希有な「上品な人格者の日本人」を演じています。
一瞬だけバカラックの「ベイビー・イッツ・ユー」もかかるし、家族が暮らすマンションの壁にはビートルズの『ハード・デイズ・ナイト』のジャケットがかかっているし。「台湾安保世代映画」ともとれなくもない。のでしょう。台湾でもこの世代は苦労が多くて大変ね、ということを知るためだけにでも観ることをお勧めしておきます。
パンフレット→香港台湾経済事情を含むリチャード・クーのレビュー
スーベニール→「後ろ向きのポートレイト」が撮れるプリクラ
リファランス→『冬々の夏休み』(ホウ・シャオシェン)
今年のトホホ賞。「泣ける泣ける」と試写状で煽ってあるから私はね。愚かにも『ラブソング』みたいなものを期待していったんですよ。
主人公は目が見えない・口がきけないという二重苦を背負いながら、それでもけなげに明るく生きている青年。同じ病院で働いている見習い看護婦のセシリア・チャンが好きだけれど言い出せずに、夜、こっそり彼女の部屋の近くでサックスを吹いて愛情表現するにとどめている。そんな彼が不慮の事故で死んで天国に行ったら特典で一週間だけ地上に帰ることが許されてでも別の人物の姿のためにセシリア・チャンには彼だということが分かってもらえず、
とかこれ以上は書かなくてもいいようなストーリーでも演出次第でどうにでもなるんだけれど、最後の最後までどうにもならないんです。男性陣に一人も美男子がいないのも悲しい。
「流星群って夜空が流す涙だったのね」って言われても。セシリア・チャンは常盤貴子風美人で好感は持てます。彼女の清楚な魅力を堪能するためと自分の心の純真さをテストするためにも観ることをお勧めしておきます。
パンフレット→「香港では試写で十人に九人は泣いた」ということがウリだそうなので、「泣いた人のコメント」を総ざらいして欲しい。そして私には分かりにくい主人公男子(本業はミュージシャン)の魅力と人気についての詳細な説明を
スーベニール→六角形の箱入りのグミ・塩入りのレモン・ソーダ・主人公と流星のエピソードにちなんで点字による星座表
リファランス→昨年ヒロスエと堂本剛でやってたドラマ
「主婦の願望もの」というジャンル映画ってありますよね、家族を離れてリフレッシュ休暇→自分探しと一時の恋→「新しい私」になって家族のもとに帰っていく、みたいな。これはまさに定石通りの映画。何だかうまくいってない家族旅行の最中にツアーバスに乗り損ねて、思いつきでベニスに行ってしまう主婦バナ。イタリアでは昨年のナンバーワン・ヒットだとか。
ただ、主婦の解放感を誘うはずのベニスの風景が全然出てこないのですよ。写るのはひたすら小汚い裏町だけ。「私にも出来ることがあったんじゃん!」と勤め始める花屋さんだって、一面の色・色・色みたいな画面にすれば官能が伝わるのに、そういうシーンが一切なし。
なりゆきで自分のアパートの一間を提供してくれることになったブルーノ・ガンツのために、毎晩持って帰ってくる花束もちゃんと映さない。去っていくときに生けるチューリップさえも! それでガンツは愛に気がつくって設定なのに!「チューリップ休暇」と宣伝している割には、あんまり生かしてないじゃないですか。
そのガンツですが、イタリア語を吹き替えなしで喋っているのは立派だとしても、しょぼくれ過ぎています。ときめきません。つくづくマルチェロ・マストロヤンニが抜けた穴はでかい、でかすぎる、底なしだと思いました。どんなにみじめな人生を背負った役でもにじみ出てくるあの色気がないと、ああいう役はダメですよ。
そんなわけで、従来の設定をもう一回ひっくり返して主人公がベニスに帰っていくラストも、「家庭を捨てて愛に生きた」というよりは、「別のボランティアを始めました」という感じで残念。でも、イタリアって厳格なカソリック国だから、それくらいのエクスキューズがないとあのオチは許されないのかも。フランスでもないと結婚後の恋愛ってたいへん!ということを実感するためにも観ることをお勧めしておきます。
パンフレット→映画では描かれなかったベニスの観光スポット案内とおいしそうなレストランガイド&ホテルガイド
スーベニール→チューリップの花束
リファランス→『特別な一日』(エットーレ・スコラ)
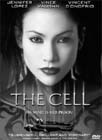 他人の深層心理の世界に入り込んで治療を試みる心理学者チームに、警察から意識不明の連続殺人犯が預けられる。命の危険が迫っている女性の居場所を聞き出すために、ジャニファー・ロペスが演じる女性心理学者が彼の意識世界へ。という新感覚スリラー。
他人の深層心理の世界に入り込んで治療を試みる心理学者チームに、警察から意識不明の連続殺人犯が預けられる。命の危険が迫っている女性の居場所を聞き出すために、ジャニファー・ロペスが演じる女性心理学者が彼の意識世界へ。という新感覚スリラー。
ジェニファー・ロペスがどう見ても学者に見えないとか、犯人役のビンセント・ドノフリオがいかに熱演しようとも、本来ならロペスを助けに行く王子様であるはずの刑事役のヴィンス・ヴォーンの方がナチュラルに不穏とか、謎解きサスペンスのドラマがおざなり過ぎない?とか、最後にロペスがやったことは安楽死で倫理問題に引っかかるから、あれ以降の研究続行は不可能でしょうとか、本当に映画としてダメダメなんだけれど、私、この作品はなんだかかばいたい。
リアルに作り込めば作り込むほどキッチュになるCG技術を、どのようなイメージを再現するのに使うのか、という問題に対するある提示として。現代美術の中で最もスキャンダラスな一面を元ネタに活用しています。悪夢がダミアン・ハーストなのはまだしも、清い心がピエール&ジルなのには大爆笑。バービー人形でボンテージや、腸を引きずり出す拷問を描いた受難画なんて誰かやっていたよね?
結果としてはうまくいってないし、石岡瑛子の衣装も大げさで一番よくないところで勝負している感じではあるけれど、「BT」と「芸術新潮」読んでます、みたいな層には是非見に行って欲しいし、楽しく悪口を言って欲しい。
なにせ、仕事から離れて安眠したいと思っているジェニファー・ロペスが見るビデオが、『ファンタスティック・プラネット』ってのが可笑しいでしょ。もちろん、安眠なんか出来ずに悪夢を見るんですよ。元ネタを羅列するためにだけでも、観ることをお勧めしておきます。
パンフレット→悪夢のリソースになった各現代美術作品の紹介と森村泰昌によるレビュー
スーベニール→白い帆船の模型・ラバースーツ・脱色バービー・セット・中に美人死体が浮かぶスノードーム
リファランス→『プロスペローの本』(ピーター・グリーナウェイ)