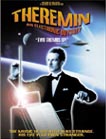 私は昨年リディア・カヴィナのコンサートに行ったくらいだから結構テルミンは好きで、クララ・ロクウェルもテルミン博士も名前は知っていたのですけれど、ドキュメントもマーヴェラス。科学とアートとテクノロジーが一体になっていた、「みんなが大好きなロシア」がニューヨークで花開く。
私は昨年リディア・カヴィナのコンサートに行ったくらいだから結構テルミンは好きで、クララ・ロクウェルもテルミン博士も名前は知っていたのですけれど、ドキュメントもマーヴェラス。科学とアートとテクノロジーが一体になっていた、「みんなが大好きなロシア」がニューヨークで花開く。
テルミン博士は「見る価値のある」本物の奇人で、テルミンをはじめとする彼が作った様々な奇妙な楽器を見ているだけで楽しい。彼の絶対的な体現者であったのが若き日のクララ(ややチュルパン・マハトーバ似ロシア美人)
その座を奪ったのが、「ダンスで音階を奏でる楽器」に挑戦した黒人ダンサーだったというのもすごい。身体性に弱いからね、理系男子は!
しかもロシア当局に連行されて、その後長い間行方知れずだったテルミン博士をクララは愛し続けたのだから純愛。モーグ博士の「自分のテルミンを弾いて欲しい」オファーを断って、テルミン博士が作ったオリジナル・テルミン、ガジェットとしてでなく、真に音楽的な楽器としてのテルミンにこだわり続ける彼女。でも、小学生の夏休み課題的な「手作りテルミン・キット」にはまって、後にムーグを生み出すモーグ(本当の発音はこう)博士の理系男子魂にも泣ける。やっぱりね、自分の名前がついたブツのひとつも残さないとね、理系男子は!
ハイライトはブライアン・ウィルソンのインタビュー、ではなく90年代に入ってのテルミン博士とクララの再会シーンなのだが、「私は決してあなたのテルミンを売りませんでした、あなたが私に作ってくれた愛しいテルミンですもの」と泣けるクララの台詞にも、その後の人生があまりに激動だったテルミン博士は「ふがふが」と答えるのみ。でもいいの、テルミンは空気をふるわし続けるのだから。
「テルミン」という楽器を知ってる人、知らない人、マッド・サイエンティストが好きな人たちに、是非観ることをお勧めします。
スーベニール→近づくと回り出すバースデイ・ケーキ
リファランス→『地球の静止する日』
この映画については、『プレミア』の10月号及び『オリーブ』、自分の著作でも述べているので、もうほとんど言うことないんですけれど、まだ少女のヘレナ・ボナム・カーターは本当に可愛い!と思います。特に近年の『ファイト・クラブ』や『猿の惑星』でしか彼女を知らない世代に是非とも観て欲しい!あの太い眉!あの瞳!令嬢らしい尊大さ!傲慢さ!それすらもチャーミングに見せる身のこなし。本当にキラキラ。二十歳の女の子はこうでなくてはいけません。
ちなみに「完全版」というのは、何がかつて公開されたバージョンと違うかというと、男どもの水遊びのシーンがのびてかつボカシがなくなっただけということです。でもま、「官能性」に関する映画だからそれもまたよし。
やっぱフィレンツェに死ぬまでに一回は行きたいと思っている方々、既に行った方、たった今二十歳の乙女である皆様、かつて二十歳の乙女だったことがある皆様に是非観に行くことをお勧めします。
スーベニール→日傘
リファランス→『ハワーズ・エンド』
ウラジミール・ナボコフの「ディフェンス」の映画化作品。1929年、チェスの世界トーナメントにやってきた天才・アレクサンドル・ルージンは、令嬢ナターリアに一目で恋をする。結婚を誓う二人だが、ルージンのかつての興行主だったヴァレンチノフが現れてプレッシャーをかける裏工作をしたために、アレクサンドルは精神のバランスがおかしくなっていく。
マルレーン・ゴリスという監督は、前作のヴァージニア・ウルフ『ダロウェイ夫人』もそうだったけれど、「センシュアルな文学作品をフツーの文芸映画としてパッケージ」するのにたけている人みたい。あの、ナボコフの身体感覚がそのまま言語化されたような張りつめた雰囲気は一切なしです。というか、ナボコフのそういう部分を映像化出来た映画作家はいないのだけれども。
そうでなくても、チェスがテーマなのだから、精密に出来ている元・天才少年が愛と陰謀のためにバランスが狂っていくところを試合になぞらえて、詰め将棋みたいに構成しないとダメなのに。チェスというゲームを視覚化するという気がまったくないので、かわいそうな社会不適合者にボランティア精神で付き合う女の話にしか見えないんですよ。
それならそれで、絵空事でもいいから、アレクサンドルが一目惚れする令嬢にもっと美人を選ぶべき!何の間違いでエミリー・ワトソン?彼女の方が精神のバランスおかしくなるタイプに見えます。タトゥーロは相変わらず上手だけれど、もともとこの映画の主題の捉え方が平坦なため、天才の狂気で観客を瞠目させるには至らず。
過去のロシア・パートとイタリア・パートの書き分けもきちんと出来ていないので、アレクサンドルにとってガラスのチェス盤が何を象徴しているのかが曖昧なまま。ていうか、多分監督その人が分かっていないんですね。
それでもイタリア観光映画としてはよく出来ています。一部にヴィスコンティの城を使っていて、ロケハンはばっちり。風景が美しい文芸映画が好きな人には、普通に観に行くことをお勧めします。
スーベニール→クリスタルのチェス駒
リファランス→『ボビー・フィッシャーを探して』
子供時代、アベルは神に祈った。こんなひどい教師がいる学校は火事にして下さいと。神は願いを叶え、アベルは火事でたった一人の親友を失った。
大人になってからは、愛する少女の気まぐれで罪に陥れられた。しかし、アベルは自分が救われると信じていた。戦争が始まり、彼は戦地に送られるが、ひょんなことからナチスの将校に気に入られ、働くことに。
アベルはドイツの士官学校に送られた。そこは彼にとって天国だった。彼が愛する美しい子供達がひとつの目的のために働き、幸せに暮らしている。アベルは、村から子供達をさらってきては、士官学校に送り込む。それが彼らの幸せと信じて。
アベルはやがて、自分が何をしているか気がついたが、少年達はもうアベルの言うことを聞いてくれなかった。
シュレンドルフの監督、カリエールの脚本、そしてミッシェル・トゥルニエの原作。間違いはないはずだ、本来なら。
でも、不思議なくらい映画は膨らまない。厳しい自然を捉えるカメラは平坦で、プログラム・ピクチャー向き。マルコヴィッチの演技も奥行きがない。ナイマンの音楽は大仰で慎みと独創性に欠け、画面に合わないこと著しい。いっそ、オペラを使えばよかったのに。
もっとテンポを落として、少年たちに対するアベルの狂おしい執着を、それ故に魔物と化す欲望を丹念に描かなくてはクライマックスへと至るカタルシスが生まれないのに。
それと映画とは直接関係ないけれど、もう浅田彰に解説書かせない方がいいと思うの。映画見としての彼は特別さえた嗅覚は持っていないし、今回も「少年愛」をやたらと避けて通ろうとしたが故に毒にも薬にもならないようなことしか書けていません。
『ブリキの太鼓』コンビとしては経歴の蛇足としか思えない作品ではあるけれど、カリエールらしい悪趣味なジョークはところどころで楽しめます。カリエールの一連の作品(『パパズレてるぅ!』『まじめに愛して!』)が好きな人には、観に行くことをお勧めします。
スーベニール→カナダに関する絵本
リファランス→『ブリキの太鼓』
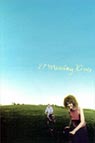 この映画については、「プレミア」の八月号でレビューを書いています。ちょっと時間がたってしまったけれど、バックナンバーを探して読んでもらえると嬉しいです。
この映画については、「プレミア」の八月号でレビューを書いています。ちょっと時間がたってしまったけれど、バックナンバーを探して読んでもらえると嬉しいです。
日蝕と月蝕に襲われたある夏、グルジアの小さな村での出来事。町の広場に停めた客船。浮気な人妻。その夫の軍人。彼女がバレエを公民館で踊ると、銀粉の雨が降り注ぎ、男達はひざまずく。『エマニエル夫人』が初めて映画館でかかる。閉め出されたおじいちゃんに孫は「もっと大きくなったら観られるよ」となぐさめる。村人たちは情事に励む時に例の主題曲を口ずさむ。村に赤毛のシビラがやって来る。自然児で反逆的、すぐに裸になってしまう少女。大人達に眉をひそめられる困った娘。ブーツとショートパンツと紺のセーラーカラーのブラウス。ミッキーはシビラに恋をしたけれど、シビラが恋をしたのは、ミッキーの父で男やもめのアレクサンドル。夜、ひとり天文台で星を見る彼のために、ネグリジェのまま自転車で町を急ぐ。悲しい時は目にピンポン玉をあてて、世界を見ないようにする。それでも、シビラは長い手足をはためかせ、少年の人生から永遠に走り去っていってしまう。
西瓜味胸キュン・ロマンスである本作は、大らかで水気をたっぷり含んでいるため、多少大味なところもあります。一言でいうとゆるい。それでも、ナナ・ジョルジャーゼが描く無茶な初恋ってどうにも私にはツボみたい。『ロビンソナーダ』で恋した男のために狩猟用の銃で娼婦を追っ払うのにも感動したけれど、やたらとモテるアレクサンドルのとこに女が来ると、戸棚に隠れて体当たりアターック!とか、裸になって夜這いをかける!とか、シビラの暴走っぷりに惚れました。
しかし、本人にインタビューしたところ、実物はもっとクールでぶっきらぼう少女だった‥というか、シャルロット・ゲンズブールとかぶり過ぎていて、今後の展開にやや不安が。25歳年上のボーイフレンド(この映画の撮影監督)と共に来日したロリータっぷりはあっぱれだけれど、どっちかっていうと「年令なんてただの数字じゃない」娘とみたね。
そんなわけで、今後フィルモグラフィーを重ねるとしても、このように美しい野生の鹿のような彼女に逢えるかどうかは分からない。そのはかない美を堪能するためにも、是非とも観ることをお勧めします。
スーベニール→マルクスの「資本論」
リファランス→『ロビンソナーダ』