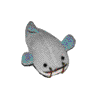 琵琶湖を丸ごとつめこんだ
琵琶湖を丸ごとつめこんだ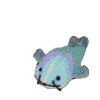
琵琶湖博物館はスゴイぞ!
昨年10月、草津市の烏丸半島に琵琶湖博物館がオープンした。琵琶湖をテーマに、古代から現代に至るまでの自然史や歴史を紹介している博物館なのだが、琵琶湖という入れものを、自然科学から人文科学まで総動員して表現する様は、なかなか素晴らしい。琵琶湖の水生物を紹介するために、水族館を丸ごと1個博物館のなかに放り込んでしまったり、上下水道が完備する前の農村の暮らしを見せるために、館内に民家を一軒移築してしまったりと、なかなか気前のいい博物館である。
遥か100万-40万年前から琵琶湖に隔離され、独自の進化を遂げた琵琶湖固有の淡水魚。縄文〜平安の土器が完全な形のまま発見されている湖底遺跡からの出土品。琵琶湖の水運を担った丸子船の復元模型。琵琶湖に浮かぶ沖島の漁業の様子と島の四季の食卓。里山や田んぼにおける微生物の働き。昭和40年代後半から盛んになった合成洗剤追放運動のあらまし。などなど実に多岐に及ぶ展示が琵琶湖という一点で結ばれて総合的に展開している。個別のテーマを追いたい人、琵琶湖全体を把握したい人、どちらにも対応している。
この博物館のユニークな点は、“琵琶湖歴史博物館”とか“琵琶湖自然史博物館”といった具合に普通に考えられる文系理系のごとき枠組みで切らずに、琵琶湖そのものを、本来の「博物」館のもっているオールジャンルを包み込むという強みで、すっぽりと丸ごとおおったことにある。博物館の長所がフルに活かされている施設といってもいい。
水族館好きの筆者にすれば、琵琶湖博物館は、普通の水族館だけを見ているときに感じる物足りなさを、補ってくれる。常々、水族館を見ていて、魚がそこに「いる」というだけで終わっている点に不満を感じてきた。その魚のいる海や湖というのは、どんなところなのか。どういう環境の中で育ち、また進化してきたのか。その魚は、地元の漁業や民俗行事とどう関わってきたのか。ここは、そのようなもう一歩踏み込んだ展示を見せてくれる。
滋賀県でいう「琵琶湖」に相当するものは、各地域ごとにもあるだろう。博物館や資料館、水族館、植物園などが提携しつつ、それを表現するというスタイルをとれば、各地域毎に、この琵琶湖博物館のような魅力ある施設がつくれるのではないか。関東に住む筆者としては、21世紀になって「葛西臨海水族園」が老朽化した暁には、ぜひ「東京湾博物館」を建てて欲しいものである。
◆CONTENTS◆MUSEUM◆
PUBLISHED
BY
 博物月報NETWORK
博物月報NETWORK
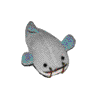 琵琶湖を丸ごとつめこんだ
琵琶湖を丸ごとつめこんだ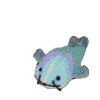
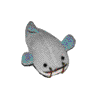 琵琶湖を丸ごとつめこんだ
琵琶湖を丸ごとつめこんだ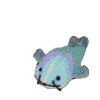
 博物月報NETWORK
博物月報NETWORK