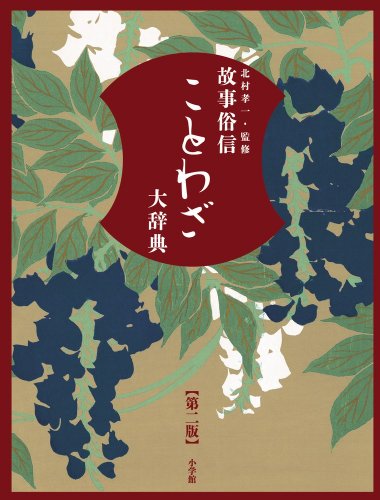まず気にかかったのは、幼い子どもたちがこのことわざを耳にしたときの反応で、たいていの子が顔をほころばせ、目を輝かせる。ことわざに関心をもち、文字どおりの意味の裏に何があるのだろう、と期待しているのではないだろうか。
『毛吹草』には「さるも木からおつる」で収録され、江戸時代には「おつる」の形が主流であった。当時のことわざを連ねた歌謡で、このことわざの後に「つるつる…」と囃すのは、滑り落ちる形容とともに、同音を繰り返し笑いを誘ったものであろう。
韓国にもほぼ同じことわざがあるのは、どうやら近代になって日本から持ち込まれたもののようだ。
ネットの連載エッセイは、「“猿も木から落ちる”と子どもたちの笑顔」 を書いた。(2025/5/15)
★地球温暖化の影響なのか春の天候も不安定で、気分もおのずから上下する。旬の魚や野菜もすっかり様変わりして、戸惑うばかり。かつて故郷では、その日に海でとれた魚を市場で買い、野菜は主に庭先から食べる分をとってきていたが、現代の東京暮らしでは望むべくもない。いつのまにか社会全体が金に換算できない貴重なものをすっかり失っていることに、愕然とする。「昔はよかった」ではなく、進行中のこの趨勢を何とかしなくては、とあらためて思う。
ネットの連載エッセイは、「“寝耳に水”の水とは?」 を書いた。寝耳に入るのは、冷水ではなく、大水(おおみず)の押し寄せる轟音、危急を知らせる鐘や叫び声といってよい。(2025/4/14)
★ことわざ学会の2月例会で「昔話“話千両”(話買い)のことわざをめぐって」と題して報告した。この昔話は、桃太郎や一寸法師ほどの知名度はないが、南は沖縄から北は青森まで広く流布し、バリエーションも多い。基本的なストーリーは次のとおり。貧しい男が妻を家に残して都会に出稼ぎに行き、相当な金を稼いで故郷へ帰る際に有り金をはたいて“話”を3つ買う。この“話”は、「急かば回れ」や「柱のないところに宿とるな」、「大木の下より小木の下」などのことわざだけで、何の説明もないのだが、帰りの道中の危難を逃れるのに役立ち、二度までも命拾いする。ようやく帰りついた男が家のなかをうかがうと、妻が男に寄り添っている様子で殺意をいだくが、最後の“話”の「短気は損気」を思い出し、よく確かめると、用心のために頭を剃った母だった(あるいは人形だった)というオチがつく。ことわざを巧みに折り込み、聞く者を飽きさせない構成に感心するが、危機をかいくぐる際に重要な役割をはたす「柱のないところに宿とるな」、「大木の下より小木の下」が、従来のことわざ辞典にはほとんど収録されていないことに注目して、今回の報告をまとめた。
ネットの連載エッセイは、「“三度目の正直”は幸運といえるか」 を書いた。(2025/3/9)
★日頃推理小説を読むことはあまりないが、ロイ・ヴィカーズに「ことわざと利潤」という短編があると聞いて、翻訳を読んでみた(平山雄一訳『フィデリティ・ダヴの大仕事』国書刊行会、2011)。読みやすい訳で、ヒロインのフィデリティ・ダヴの魅力がよく伝わってきてファンとなったが、作品全体のキイとなる肝心のことわざが「泥棒を捕らえて縄を綯う」と日本語のものに置き換えられていて、印象がぼやけた感はいなめない。タイトルの訳にもやや違和感がある。原文はすぐには見られなかったので、他の訳(厚木淳訳「聖ジョカスタの壁掛け」、エラリー・クイーン編『完全犯罪大百科 悪党見本市』上所収、創元推理文庫、1979 ※改題は編者によるものという)を参照してみた。後者の訳では、「その諺は−−正確に引用することはできませんけど−−馬が盗まれたあとで馬小屋の錠をおろす、というようなことです」とフィデリティが語っており、これなら作品全体のモチーフも納得できた。ここでは、読者の推理小説を読む楽しみを妨げないためにこれ以上書かないが、ことわざの翻訳のあり方を考える上でもなかなか興味深いものがあった。
ネットの連載エッセイは、「“二度あることは三度ある”と庶民の生活感覚」 を書いた。(2025/2/6)
★2025年の正月はどこにも出かけず、ことわざ学会(および前身のことわざ研究会)の古い会報を拾い読みしたり、DVDでこれまた古い映画「アフリカの女王」を観たり、ユーチューブで少数言語の会話を聞いたり……久しぶりにのんびりした日々を過ごした。ぐずぐずしているようだ(否定はできません)が、案外こういう時間が大切なのではと思ったりした。
そんななかで、イタリアの児童文学者ジャンニ・ロダーリの『緑の髪のパオリーノ』(内田洋子訳、講談社文庫)をたまたま目にし読んでいくと、「古いことわざ」という短編に出会った。ある町に、少し不便ですが、落ち着いた建物がありました。年を取ったことわざが引退して休むところです、という場面設定からして面白い。関心がある方は翻訳をご覧いただくことにして、印象的な一節だけ引いておこう。「年寄りのことわざたちは、仲間の言うことと反対のことを言うのが得意なのです。」
新年の初仕事は、ネットの連載エッセイで、「暗喩が生きる“一寸先は闇”」 を書いた。(2025/1/11)
★2024年は、残暑というには暑すぎる晩夏が尾を引き、いいかげん草臥れた。快適な秋は短く、紅葉を楽しむのも慌ただしく冬に突入し、なかなか体がついていけない。
思い返すと、去る9月には、千野明日香著『ミニマムで学ぶ 中国語のことわざ』(クレス出版)が刊行され、シリーズ6冊が完結した。10年ほど前に企画し監修したもので、最初の英語・フランス語・韓国語の刊行から7年余、ようやく肩の荷をおろしたことになる。各言語の著者・ネイティブの協力者、版元の皆様に感謝したい。
気がつくと歳末目前。このところ“ことわざフォーラム2024”(12月8日、シンポジウムで「災害伝承としてのことわざ」を報告)、地球ことば村のサロン(12月11日、井上逸平氏との対談)と人前で話すことが続き、オーバーワークぎみだが、暑い時期でなくてよかったと思う。
フォーラムでは、村山貢司氏(気象予報士、花粉症の専門家)の講演に衝撃を受けた。地球温暖化で従来の天気俚諺が通用しなくなるのはある程度予測できたが、大災害になると「遠い親戚より近くの他人」は通用しない。隣人も被害を受けるだけでなく、大都市では国や自治体の避難所や備蓄が不十分で、まったく頼りにならないのだという。具体的なデータに基づく話で十分に説得力があり、まさに心胆を寒からしめるものがあった。
監修を引き受けた北澤篤史著『マンガでわかる すごい!ことわざ図鑑』(講談社)が12月17日に無事刊行された。(2024/12/19)
★ともかく暑い夏が続く。東京では35度になっても驚かず、熱帯夜の連続も日常となってきた。気温だけでなく海水温も上がり、魚や獣の生息域も大きく変動している。ヒトだけが従来と同じように生きていけるはずはない、と直感的に思う。
災害とことわざについて考えるうちに、気象に関連することわざの裏には多くの災害体験があることにあらためて気づいた。そういう意味では、「寝耳に水」も災害伝承の一つといってよい。新たに注目したのは「尾崎谷口宮の前」で、ことわざ集やことわざ辞典にはほとんど収録されておらず、文献ではいまのところ大正末期が初出のようだが、地方誌をみていくと、新潟以西の広い地域(九州・四国の一部を含む)の山の民の間で古くから口頭で伝えられていたことが少しずつわかってきた。まだ調査の途上だが、中間報告を「災害伝承としてのことわざ」として『青淵』8月号(905号)に掲載した。
ネットのコラム(7回目)は、 「“犬も歩けば棒に当たる”の二つの意味」について書いた。(2024/8/14)
★昨2023年の春、「寝耳に水」の用例を探求することから、その本来の意味は、睡眠中に耳に水を入れられて驚くことではなく、気がついたら洪水が身近に迫っていて驚き、慌てふためくことであったことを明らかにすることができた(『青淵』892号にその成果の一端を紹介した)。また、現在では、「水」を文字どおりの水と解し、洪水とかかわりなく事情をまったく知らずに驚くことの比喩として用いるのが大勢となっているが、元来の意味・用法も消滅したわけではなく、近現代にも根強く残り、災害時に再認識される場合があることもわかってきた。この事例をみると、ことわざの意味は、テキストを見るだけではわからないことが少なからずあり、丹念に用例を探求し、広い視野からとらえ直すことの重要性をあらためて感じている。
今年は災害とことわざについてさらに探求をつづけ、災害時のさまざまな言い伝えについても、もう少し具体的に考えてみたい。
ネットのコラム(6回目)は、 「“地震雷火事親父”のレトリック」について書いた。(2024/5/20)
研究環境も大きく変わり、国会図書館などのデジタル化が格段に充実し、自宅にいながら大量の文献情報にアクセスすることが可能になった。古い書籍だけでなく、近現代の雑誌や論文、私家版なども(一部は国会図書館まで見に行くか、コピーを依頼しなくてはならないが)かなりのものが公開されるようになったので、大学に所属しなくても十分に研究のレベルを維持できるようになったといえよう。
さらに、国文学研究資料館のデジタル画像データベースを活用すると、同じ古典籍でも短時間で複数の写本を参照することもある程度できる。外国語の書籍へのアクセスもさまざまなルートで可能なことは、多くの方が実感しているところだろう。
ことわざという、庶民のきわめて広い言語領域を対象とする在野の研究者にとっては、たいへん有り難い環境がととのってきた。
ネットのコラム(5回目)は、 「“好きこそ物の上手なれ”の眼差(まなざ)し」について書いた。東京は、先週後半から急激に温度が上がり、晴れると初夏の日射しとなった。(2024/5/2)
★今年の春は天候の変動が激しく、夜間に強い風が吹いて目覚めることも少なくなかった。体調も波があり、例年よりも花粉アレルギーが気にかかった。
昨年の“ことわざフォーラム2023”で「ことわざの音声と響き」をテーマにし、ワークショップで朗読を企画したこともあって、ことわざの音声面にあらためて注目している。グレマス(Greimas )が『意味について』で言及していたことを思い出し、末尾の「諺と格言(ディクトン)」(赤羽研三訳、水声社)を再読した。
ネットのコラム(4回目)は、 「“花より団子”に込められた思い」について書いた。東京のソメイヨシノは今日明日にも開花するようだ。(2024/3/28)
★駿河台の“山の上ホテル”休館のニュースを目にし、かつて件のホテルで口述筆記のアルバイトをしたことを思い出した。大手出版社がこぞって世界文学全集を出していた時代で、半世紀以上も前のことになる。慶応大学仏文科の若林眞先生がジッド(ジード)の翻訳を口述され、私が原稿用紙に筆記していた。帰りにはよく文庫専門の古本屋に立ち寄ってギリシャ喜劇の本を1冊買い、読み終わるとまた買うことを何度か繰り返したから、3週間近く通っただろうか。馬事公苑に近いご自宅で、最終回の筆記をしたこともかすかに覚えていた。その後、何年かして小説を書かれたと耳にしたが、タイトルも知らないまま時が過ぎた。今回、これを機会にとネットで調べ、『海を畏れる』と知り、地方の古本屋に注文して入手した。郷里の佐渡と研究者として暮らす東京、それぞれの死者と生者が交錯する、ユーモアと深みのある小説で、毎晩1章ずつじっくりと読んだ。
ネットで連載中のコラムの3回目は「“鉄は熱いうちに打て”の常識を見直す」を書いた。(2024/2/29)
★2024年の幕開けは元日の能登半島地震、翌日は羽田の航空機事故とつづき、2022年のウクライナ戦争、2023年のイスラエルのガザ侵攻もいまだに停戦もならず、心穏やかに過ごせない日々が続いている。
1月も下旬となり、気を取り直して仕事に集中する。昨年はリハビリからのスタートだったことを思い返し、いま自分にできることをやるしかないとあらためて思う。
「ことわざ・慣用句の百科事典」サイトのコラムが連載となり、2回目は「“暑さ寒さも彼岸まで”の背景」を寄稿した。(2024/1/26)
★2023年も残りわずかとなった。トラブルもあったが、多くの方にご支援いただき、おかげさまで体調も徐々に回復し、研究を再開し継続できたことを感謝したい。
ネットの「ことわざ・慣用句の百科事典」に寄稿を求められ、正月にふさわしいものがよいと思い、江戸時代の夢合わせ関連文献を参照し、コラム「初夢と“一富士二鷹三茄子”」を書いた。(2023/12/22)
★コロナで旅行できなかった年を除いて、長年夏は北海道で過ごしてきたが、今年は東京にいて、ともかく暑い。「温暖化ではなく沸騰化」というのも決してオーバーではない猛暑続きで、かなり参っている。昼は何とか冷房でしのげるが、24時間冷やすと体が悲鳴を上げるのは当然であろう。
エッセイ「“寝耳に水”をめぐって」を『青淵』892号に掲載した。 スペースの関係で用例は江戸時代のものにかぎっての紹介となったが、今回はいつも以上に反響があって、どうやら今後も研究を続ける意欲がわいてきた。(2023/8/10)
★昨年はさまざまなことがあって、しばらく研究から遠ざかっていたが、2023年3月、ことわざ学会の例会で「“寝耳に水”をめぐって」と題して久しぶりに報告した。このことわざは、江戸初期から用例があり、いまもよく使われるが、その由来については二つの説がある。文字どおり寝耳に水を入れることと解して、奇抜な比喩だとする説(鈴木棠三氏など)と、寝耳に水が入ることは現実にはごく稀で不自然であり、「水」は洪水の音だとする説(金子武雄氏など)である。私は、比喩はかならずしも現実そのものである必要はないとして、前者に近い立場であったが、この数年間にさまざまな面から疑問が生じ、しだいに洪水説のほうが妥当ではないかと考えるに至った。ただし、金子氏の洪水説は、理論的にそのほうが自然であるという推論で、具体的にこの説を裏付ける用例が乏しく、説得力が十分とはいえない。そこで、江戸時代にさかのぼって、ことわざの「水」が洪水をさす用例を探索した結果を報告したものである。結論として、夜間の豪雨による洪水をさして用いられた例が江戸前期から認められ、この用法が一部では近現代まで根強く残っていたことが判明したのだった。(2023/3/20)
★コロナ禍の先行きがなかなか見えず、ようやく下火になってきたかと思うと、また感染者数が増大している。とはいえ公共図書館は、たとえば文京区立図書館の場合、座席は二分の一から三分の二ほどに制限されているが、着席時間の制限がなくなり、だいぶ使いやすくなったのはありがたい。他方で、大学図書館は、どうやら全国的に依然として外部の者の入館を認めないようで、どうにも困ったものである。
困ったものといえば、小学校の給食では、対面しないように座り、黙食がいまも続いているという。こんなに不自然なことが2年半も続くと、この時代の子どもたちに将来深刻な影響があるのではと、心配になってくる。
困ったもので済まされないのは、ロシアによるウクライナ侵略。かつてロシア語を学んだ後期高齢者は、その惨状を繰り返し画像で見せられ、己の無力さを思い知らされる毎日だ。それにしても、プーチンの論理とこれに従うロシア国民の姿はかつての日本帝国を想起させるものがある。また、昨日までプーチンやトランプのポチだった者が、何の反省もなく、この機に乗じて「核の共有」や軍事費の倍増、憲法改正を画策するのもいい加減うんざりだ。(2022/7/3)
★気がつくと2021年も師走半ば。コロナ禍はいまだ収束せず、日常生活でもさまざまな制約が残っている。人々が自由に集うこともむずかしく、昨年に続き、今年の“ことわざフォーラム”もリモートを併用して開催した(12月4日、杏林大学)。やってみると、リモートにはもどかしさもあるが、海外でも視聴できるなどのメリットがあり、対面とは別の可能性も感じられた。
時期は前後するが、10月に学研プラスから刊行された金田一秀穂監修『小学ことわざ・四字熟語辞典』改訂第2版にコラム「世界のことわざ」(105項目)を執筆した。かつて共同監修した『日本と世界の おもしろことわざ』の記事をベースにしているが、用法を確認して、多くは書き換える結果となり、イラストも一部改めた。今年は、『世界の ふしぎな ことわざ図鑑』に加え、“ことわざフォーラム”のテーマも「子どもとことわざ」だったから、子どものことを考える年であった。(2021/12/13)
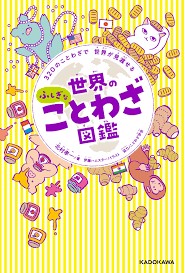 ★一昨年(2019)から取り組み、昨秋原稿を書き終えていた『世界の ふしぎな ことわざ図鑑』(KADOKAWA)が今月ようやく刊行された。子ども向けの本で、見開きの右ページで日本のことわざに用例を付してイラスト入りで解説し、左ページには類似の外国語のとわざを3つずつ挙げてコメントを加え、構成と文章は自分なりに工夫してみた。80の日本のことわざに外国語のものが240項目で、合計320項目。いまふうの賑やかな装丁とイラストで、ちょっと気恥ずかしいが、子どもたちは歓迎してくれるようだ。子どもにわかりやすく、やさしい文章で書くことは、自分の頭の中を整理することにつながり、得がたい経験をしたと感じている。
★一昨年(2019)から取り組み、昨秋原稿を書き終えていた『世界の ふしぎな ことわざ図鑑』(KADOKAWA)が今月ようやく刊行された。子ども向けの本で、見開きの右ページで日本のことわざに用例を付してイラスト入りで解説し、左ページには類似の外国語のとわざを3つずつ挙げてコメントを加え、構成と文章は自分なりに工夫してみた。80の日本のことわざに外国語のものが240項目で、合計320項目。いまふうの賑やかな装丁とイラストで、ちょっと気恥ずかしいが、子どもたちは歓迎してくれるようだ。子どもにわかりやすく、やさしい文章で書くことは、自分の頭の中を整理することにつながり、得がたい経験をしたと感じている。非常事態宣言の中で160点に及ぶイラストを描いていただいた伊藤ハムスター氏と、粘り強く編集・制作を進めていただいたKADOKAWA編集部の丸岡希実子さんに深く感謝したい。また、外国語のことわざについては、中村禮子氏(シンハラ語)や多くのことわざ学会会員にご協力いただいたことを記し、あらためて感謝の意を表したい。(2021/8/26)
★その後、都内の区立図書館は徐々に閲覧できるようになったが、時間制限があったり、机はあっても椅子がなかったりするところもある。都立中央図書館や国立国会図書館は抽選制で、座席数もかぎられている。私のようなインディペンデント・リサーチャー(在野研究者)にとって何より痛いのは大学図書館が外部の者に閉ざされていることで、原典を確認する作業は絶望的なことも少なくない。イベントやスポーツ観戦の制限もかなり解除されてきているのに、なぜ図書館の本の閲覧が極端に制約され続けるのか、まったく理解できない。図書館でクラスターが発生した事例でもあるのだろうか。ライブラリアンの声も私にはまったく聞こえてこないが、どこかで声をあげているのだろうか。(2020/10/08)
★都内の公共図書館は完全に休館し、近隣の大学図書館も5月の連休明けまで休館となっている。原稿執筆に支障が出るのはいうまでもないが、いまは自宅でできることをやるしかない。
昨秋、〈ミニマムで学ぶ〉シリーズが2点刊行されて、年明けからことわざのミニマムについて質問されることが何度かあった。ことわざのミニマムに関心のある方には、広い視野からリテラシーの問題としてとらえた次の論文を一読されることをお薦めしたい。
鈴木雅子「外国語学習者の“文化リテラシー”−−日本人学習者に対するデンマーク語のことわざを一例に」(IDUN −北欧研究−、23号、2019)
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/71770/
上記の大阪大学のサイトからダウンロードして閲覧できる。(2020/4/16)
★コロナウィルスで区立・都立の図書館が事実上閉鎖され、仕事がたいへんやりにくくなっている。ネットで申し込めば借り出すことはできるが、本をまったく見ずに予約するのはひどく効率が悪い。辞典類をその場でちょっと確認することもできない。ウィルスのリスクを避けたいのは誰でも同じだが、一律に閉鎖するのはいかがなものか。(ただし、一部の区立図書館は閲覧可能との情報もある。)(2020/3/10)
★9月25日に、ミニマムで学ぶシリーズのドイツ語とスペイン語の2点がクレス出版から同時刊行された。少し時間がかかったが、いずれも各言語の専門家がネイティブの協力を得て執筆したもので、期待に違わぬ内容と親しみやすさを兼ね備えている。監修者として、シリーズの5点がそろったことで、少しほっとしている。(2019.10.17)
★近年は、紀要類でも印刷されず、PDFのみというものも多くなっている。他の方からそうした形式の論文をお知らせいただき、私自身も2017年に日本大学文理学部人文科学研究所で講演したことを思い出した。講演を文字に起していただき、校正した記憶はあるが、その後音沙汰がなかったもので、検索したところ、HPにPDFで掲載されていることが判明した。(2019/6/11)
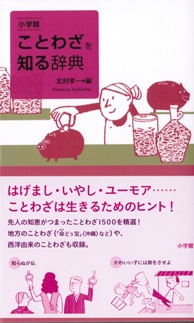 ★『ことわざを知る辞典』(小学館)を上梓した。用例は原則として近現代の文献からとり、わかりやすい記述で、親しみやすい本になるように心がけた。基礎的なデータは『故事俗信ことわざ大辞典』第二版に基づいているが、その後の研究成果もかなり反映できた。コンパクトな辞典だが、基本項目100は1ページとし、コラムも10あって、ある程度自分の見方を示せた気がしている。また、100点をこえる谷山彩子さんのイラストは、ふんわりと穏やかな中にユーモアがあり、楽しい。ご協力いただいた皆様にあらためて感謝したい。(2018/11/20)なお、この本は次の版元サイトで試し読みできる。(2019/1/4)
★『ことわざを知る辞典』(小学館)を上梓した。用例は原則として近現代の文献からとり、わかりやすい記述で、親しみやすい本になるように心がけた。基礎的なデータは『故事俗信ことわざ大辞典』第二版に基づいているが、その後の研究成果もかなり反映できた。コンパクトな辞典だが、基本項目100は1ページとし、コラムも10あって、ある程度自分の見方を示せた気がしている。また、100点をこえる谷山彩子さんのイラストは、ふんわりと穏やかな中にユーモアがあり、楽しい。ご協力いただいた皆様にあらためて感謝したい。(2018/11/20)なお、この本は次の版元サイトで試し読みできる。(2019/1/4)★ことわざ学会の学会誌『ことわざ』8号が刊行された。学会創立十周年記念号で、会員によるエッセイを特集している。いずれも、論文だけではわからない執筆者の個性が感じられ、興味深く読ませていただいた。(2018/4/28)
★2018年5月5日、5回目となる「いろはかるたを楽しむ会」を殿ヶ谷戸庭園で開催する。今回は、〈加賀のいろはかるた〉にスポットを当て、お話しするとともに、〈いろはかるた貼交図〉からかるたを作って遊ぶことにした。〈いろはかるた貼交図〉につては、このHPの「いろはカルタ」のなかで「加賀の庶民文化を伝える一枚刷り」として取り上げているので、ご参照いただきたい。(2018/4/26)
★昨秋から「ことわざ資料書誌−−江戸期を中心に」と「江戸期未収録ことわざ索引」をHPで公開することを検討し、11月にテスト版をアップしている。前者は、数多く刊行されたことわざ資料集のうち江戸期の資料をを中心にタイトルなどで書誌情報を検索できるもの、後者は加藤定彦・外村展子編『俚諺大成』(青裳堂、1989)に未収録で、目についたものを五十音順に収録したもので、ツールとして活用いただくことを願っている。。ささやかなものだが、ある程度の実用性はあるかと思う。テスト版なので、トップからやや入りにくい形になっているが、関心のある方は、お問い合わせいただきたい。(2018/1/22)
★10月以降は何かと慌ただしく、気がつけば、はや大晦日。この間、11月25日には、ことわざ学会創立10周年記念の「ことわざフォーラム2017」に参加、11月30日には日大文理学部人文科学研究所で「ことわざの魅力とは」と題して講演、12月9日にはNPO地球ことば村のサロンで「ことわざを見直す」と題してお話しするなど、珍しく外に出ることが多かった。少し疲れたが、ことばやことわざに関心の高い皆様に出会い、いろいろと学ぶことができ、大いに感謝している。(2017/12/31)
★4月から完全なフリーとなり、どの程度仕事がくるのか見当がつかなかったが、初めてのところから意外に多く声をかけていただいて、むしろ忙しくなっている。PR誌や女性週刊誌の取材に応じたり、関西のテレビ局に呼ばれたり、出版関係でも新しい企画が進行することになった。今週は、犬の雑誌の新年号企画で、犬に関することわざ特集の監修を依頼され、そうか来年は戌年かと、あらためて気づかされた。(2017/10/5)
★1月に仕事場を整理し、蔵書の大半を処分した。執筆に支障が出るのではと少し懸念したが、案ずるより生むが易しで、公共図書館のお蔭で何とかなっている。パソコンで依頼すると、翌日には区内のどの図書館の本でも見られるので、専門書は別として、文学書や一般書はほぼカバーできる。こまめに借りたり返したりで、運動不足の解消にもつながり、一石二鳥で、たいへん有り難い。(2017/5/30)
★3月末で、学習院大学非常勤講師の任期を終えた。2005年度から担当し、途中2回2年ずつ休み、延べ8年間、ドイツ文学科の研究室にお世話になり、基礎教養科目「言語と文化−−ことわざの世界」を自由に講義させていただいた。週1コマの授業だが、保阪良子先生はじめ多くの方々のご協力を得て、学生とともにさまざまなことを学ぶことができたと思う。関係者の皆様、そして学生諸君にあらためて深く感謝したい。(2017/4/1)
★しばらくHPに手を入れていなかったが、「いろはカルタのページ」に「宮城道雄の童謡〈いろはかるた〉」を掲載した。そのほか、HPの体裁で気になるところなどを順次訂正している。(2017/3/3)
★中断していた地球ことば村HPの連載エッセイ「ことわざの世界」を再開し、「若い時は二度ない」を掲載しました。これからは月に1回程度、ことわざに関連した短いエッセイを書いていくつもりです。(2017/3/1)
 ★ここ3年ほど取り組んできた〈ミニマムで学ぶ〉シリーズの第1弾3点が、クレス出版から刊行された。企画からかかわり、監修を手がけたもので、「フランス語のことわざ」は大橋尚泰氏、「韓国語のことわざ」は鄭芝淑氏、「英語のことわざ」は北村孝一がそれぞれ執筆している。ことわざを論理的にとらえるとともに、感覚的にも自らのものとするための試みで、異文化理解のツールとして活用されることを願っている。(2017/2/28)
★ここ3年ほど取り組んできた〈ミニマムで学ぶ〉シリーズの第1弾3点が、クレス出版から刊行された。企画からかかわり、監修を手がけたもので、「フランス語のことわざ」は大橋尚泰氏、「韓国語のことわざ」は鄭芝淑氏、「英語のことわざ」は北村孝一がそれぞれ執筆している。ことわざを論理的にとらえるとともに、感覚的にも自らのものとするための試みで、異文化理解のツールとして活用されることを願っている。(2017/2/28)