・キャンティ物語/野地秩嘉 幻冬社
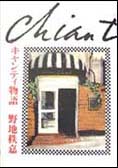 入会してみたいサークルはどこ?と誰かに問いかけられたら、私は迷うことなくブームズベリーとボサノヴァを生み出したナラ・レオンのサロン、そして60年代の『六本木野獣会』と答えます。これは野獣会をはじめとする東京おしゃれ人脈のサロン的存在だった頃のレストラン「キャンティ」をめぐるドキュメンタリー。
入会してみたいサークルはどこ?と誰かに問いかけられたら、私は迷うことなくブームズベリーとボサノヴァを生み出したナラ・レオンのサロン、そして60年代の『六本木野獣会』と答えます。これは野獣会をはじめとする東京おしゃれ人脈のサロン的存在だった頃のレストラン「キャンティ」をめぐるドキュメンタリー。
伯爵家出身で粋な遊び人だった川添浩史と、美的センス抜群で冒険心に富む梶子の恋から生まれた社交場のきらびやかさは目もくらむばかり。
二人がアズマカブキをヨーロッパに持っていった時はジャン・コクトーにカミュにマルロー、ル・コルビシェやジャン・マレーといった面子が囲み、キャンティ帰りに三島由紀夫と川端康成は「ムゲン」でディスコダンスに興じる。貴公子レーサーだった福沢幸雄がヨーロッパから買って帰ったレコードをかまやつひろしの村井邦彦が聞いて小洒落歌謡曲を作り、とびきり美しい不良少年少女である加賀まり子や大原麗子、ジェリー藤尾が集う‥。
ああ、この時代の六本木に行きたかった! 「お金があって大人」ではないと不良になれなかった時代に!って、冷静に考えると自分はどっちの条件からもはじかれちゃうんですけどね。その麗しい時代の終焉を告げるのが、息子のプロデュースによるミュージカル『ヘアー』の日本公演だというのは何やら象徴的です。ヒッピー誕生によって不良は特権階級じゃなくなったのでした。
・さよならの城/寺山修司 新書館
 昨年大変に好評を博した「20才シリーズ」ですが、20才の乙女の本棚には間違いなくこの本がなくてはいけません。「ええー、天井桟敷の人でしょお?」というなかれ。こんなにお洒落な本もそうそうないのですから。
昨年大変に好評を博した「20才シリーズ」ですが、20才の乙女の本棚には間違いなくこの本がなくてはいけません。「ええー、天井桟敷の人でしょお?」というなかれ。こんなにお洒落な本もそうそうないのですから。
再発編集本が出ていますが、オリジナルは判型と宇野亜喜良挿絵でうつむき乙女度2割増(このフレーズ盗作)。そういや、この本のマリー・ローランサンの詩の翻訳は、小西康陽によって夏木マリの詞に転用されているのに誰も指摘しないのは何故?
メランコリックなのに瑞々しい、詩ともエッセイとも童話ともいえない素敵な問わず語りの数々。吉永小百合が20才になった記念に書かれたラジオドラマの脚本の素晴らしさといったら!ヒロスエには寺山修司がいなくて気の毒だった。「テーブルの上の二つの小さな恋愛論」(このタイトル!)は「三島由紀夫レター教室」が好きなあなたはしびれること間違いなし。
著者二人のプロフィールである「宇野亜喜良小辞典」「寺山修司小辞典」も必読。時代のヒップなスターらしく決め決めのポートレイトに「これから手がけてみたい仕事は映画演出、歌舞伎台本、競馬オーナー、恋愛」「爵位を買う制度が欲しい」等、両者ともすかしまくっています。
それにしてもこの時代の新書館フォア・レディース・シリーズのラインナップはすごいね。安井かずみの『空に近い悲しみ』にレモンちゃん時代の落合恵子乙女エッセイ(また一日がはじまるわ あのかたにあえる!)。ちょっとコンプリートしたくなります。
・ファッションの鏡/セシル・ビートン 田村隆一訳 文化出版局
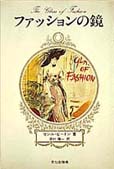 30年代からの『ヴォーグ』仕事その他でお馴染みのカメラマンにして映画美術家、ファッション紳士の自伝的ファッション文化史研究書。実は装丁はセンスなしだけど中身は最高!という『マイ・フェア・レディ日記』(キネマ旬報社)を紹介する予定でいたのだけど、こっちを読んでしまったからにはプッシュせざるをえません。昨年ゲットして最も楽しんで読んだ一冊。行間から白粉や香水の匂い、衣擦れの音が聞こえるような本物のお洒落本です。
30年代からの『ヴォーグ』仕事その他でお馴染みのカメラマンにして映画美術家、ファッション紳士の自伝的ファッション文化史研究書。実は装丁はセンスなしだけど中身は最高!という『マイ・フェア・レディ日記』(キネマ旬報社)を紹介する予定でいたのだけど、こっちを読んでしまったからにはプッシュせざるをえません。昨年ゲットして最も楽しんで読んだ一冊。行間から白粉や香水の匂い、衣擦れの音が聞こえるような本物のお洒落本です。
本人による優美で特徴的なイラストも満載。実力的には二流だけどその奇抜なファッションによって記憶される舞台女優やココット(高級娼婦)、パーティギバーだった貴婦人達などリアルお洒落リーダー達の奇抜にして美しいスタイル描写には思わずため息が漏れます。
余談ですが、着飾ったココットたちがオペラのバルコニー席で劇場の主役だったというのは、歌舞伎座の花道脇を芸者が占めていたというのと同じだなと思いました。ちなみに昨年のグレイ二十万人コンサートの最前列は花形キャバクラ嬢が占めていたそうです(大泣)。
ファッションという消費物に魂を捧げた人たちへの力強い讃歌。現在のところ私の座右の書です。
・どこまで行けばお茶の時間/アントニイ・バージェス サンリオSF文庫
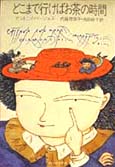 『時計じかけのオレンジ』原作者唯一のジョブナイル。サンリオの中でも高価なプレミアがついている文庫本ですが、千円までなら出して損はないと思います。表紙と挿し絵の飯野和好イラストがいかにも80’sフレーバー。
『時計じかけのオレンジ』原作者唯一のジョブナイル。サンリオの中でも高価なプレミアがついている文庫本ですが、千円までなら出して損はないと思います。表紙と挿し絵の飯野和好イラストがいかにも80’sフレーバー。
歴史の授業中にうとうとしていたエドガー少年がみるみる内に小さな分身になって、本体を教室に残したまま、机の上にコンパスで開けた穴をつたって大冒険というまさしく男の子版『不思議の国のアリス』。ナンセンスでペダンティックなユーモアと物語展開もとてもよく似ています。
何よりも出てくる登場人物たちや町の名前が、全て少年と同じく頭文字がEであること、更にはイギリスの小中学生たちが授業で習う事柄があらゆるところに散りばめられているところがイギリス的。
でもこれ、授業中に半眼で男の子が見ている夢だと思うと納得出来ちゃうんですよ。単語だけで頭の中に入って来るんでレム睡眠に作用するという。イヤだなあ、相対性理論に苦しめられる授業中のうたた寝(笑)。おまけに午後の授業でお腹が空いているものだから、エドガー少年はしょっちゅう「お茶、お茶、スコーン、スコーン」って言ってるんですね。
そんな訳で本家ほどドープではないにしろ、翻訳でも(この手のものって原文の方が言葉遊びが楽しいのだろうから)かなり楽しむことが出来ます。
・地下鉄サム/ジョストン・マッカレー 創元推理文庫
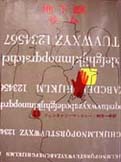 オシャレ表紙が目印のこちらは、『怪傑ゾロ』の人が生み出した泥棒小咄集。戦前から日本では人気のシリーズだということ。
オシャレ表紙が目印のこちらは、『怪傑ゾロ』の人が生み出した泥棒小咄集。戦前から日本では人気のシリーズだということ。
ニューヨークの地下鉄を根城にするベテランで名人芸のスリのサムと、彼を逮捕しようと追い続けるクラドック刑事の物語。と聞いて、今、あなたは何を思い浮かべました? 男気サスペンス? 『ルパン』? どちらも外れ、答は「落語」です。
というのはですね、ニューヨーク育ちのサムは原文では恐らくブルックリン訛りで話しているはずなんですが、それが全部江戸弁に解釈されているんですね。「これはクラドックの旦那、またぞろでここで旦那のまずいつらを今日もおがませられんですけい?」「よしておくんなせえ! あっしゃぁ、もう何も言うことはござんせん」って、一体どこの物語なのやら。
もちろん、対する刑事も「川上の別荘送り」「ここが年貢の収め時よ」が決まり文句。地の文からして「水商売の朝寝坊、といっちまえばはなはだ殺風景だが」なんて調子なんですから、全編に渡っていなせだねぇ。いやー、これは翻訳の乾信一郎氏のお手柄です。
・魔性の森/ハーバード・リバーマン 角川文庫
 ずっと欲しかった文庫をようやく経堂の古本屋で手に入れました。『黒いアリス』を入手したのもこの町だし、さすが植草甚一先生のお膝元ですね。『ブレアウィッチ・プロジェクト』を観たその日に読み始めたらシチュエーションが似ているんでちょっとびっくり。
ずっと欲しかった文庫をようやく経堂の古本屋で手に入れました。『黒いアリス』を入手したのもこの町だし、さすが植草甚一先生のお膝元ですね。『ブレアウィッチ・プロジェクト』を観たその日に読み始めたらシチュエーションが似ているんでちょっとびっくり。
舞台はニューイングランドの森深く。自分たちが相続した土地の測量をするために、古くからその土地に住む男女七人がやって来るのだけれど、森を知り尽くしている測量人が発作で意識不明になったために森から出られなくなるというのがあらすじ。何がすごいって、この「森から出られなくなる」というプロット一本で四百ページ持たせちゃうその力業がすごい。
楽観的なピックニックまがいの冒険が、いけどもいけども外にたどり着かないという不条理によって暗転していく様が実にスリリング。むき出しになっていく各人の本性と隠されていた因縁だらけの相関図によって、いたたまれない人間ドラマも繰り広げられます。
「森は気が向いた時に人を食う」というフレーズが出てくるけれど、実際西洋人は森を切り開いて自然を征服することによって文明を築いてきた訳だから、飼い慣らせなかった「森」は恐怖なのね。異端者は全て森に追いやってきた訳だし。そこらへんも踏まえておかないと『ブレア』やこの本のじわじわと迫り来る恐ろしさは吟味できません。
時間軸をずらして話をシャッフルしたのか、実際に時空が歪んでしまったのか曖昧なラストは好き嫌いが分かれるところだけど、何故測量人だけが森で迷うことがなかったのかというミステリーは解決してあるんで私的には満足でした。
・仲よし手帖/長谷川町子 姉妹社
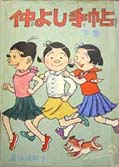 さて、めずらしくマンガのご紹介。これは『サザエさん』でお馴染みの著者の知られざる傑作。松子さん・竹子さん・梅子さんという仲良し三人娘が繰り広げるお茶目な女子高生ライフには心が和むこと請け合いです。
さて、めずらしくマンガのご紹介。これは『サザエさん』でお馴染みの著者の知られざる傑作。松子さん・竹子さん・梅子さんという仲良し三人娘が繰り広げるお茶目な女子高生ライフには心が和むこと請け合いです。
実は初版年度と初出が不明なため、昭和何年頃の日常なのか分からないけど、お正月ボケで新学期早々遅刻しそうになった松子さんがリンタク(人力車タクシー!)で学校に駆けつけていたりするところを見ると、太平洋戦争前と考えて間違いがないのではないでしょうか。それとも戦後にも走っているのかリンタク。くわしい方の情報求む。もちろん授業にどうにか間に合った松子さんの顔は羽根突きの際のスミで汚れているのね。
半七捕り物帖に夢中になって探偵ごっこをしたり、「ブロンディ」に出てくるような特大サンドイッチを調理実習で作ったり、修学旅行で行った京都で舞妓さんのサインもらったりと昭和乙女生活を満喫。この上品なユーモア感覚が好きなら、もちろん傑作『サザエさん打ち明け話』はマストです。