・もう森へなんか行かない/エドゥアール・デュジャルダン 鈴木幸夫 柳瀬尚紀訳 都市出版社
 ずーっと欲しかった本を、ファーストネット通販でゲット。インターネットって素晴らしい。
ずーっと欲しかった本を、ファーストネット通販でゲット。インターネットって素晴らしい。
1887年にフランスで発表されたこの小ロマンは大して評判にならず、そのまま文学の歴史の渦の中に消えるはずだった。しかし1921年に、かつてこの小説を手にした若造が、その手法をサンプリングして大成功を収めるや否や、思わぬスポットライトを浴びることになる。
実はこれ、ジョイスの『ユリシーズ』の元ネタ本だったりするんですよ。一旦はモードから外れて忘れられますが、60年代にもう一回ヌーヴォー・ロマンの流れでペーパー・バック化されて再評価。マラルメやユイスマンも絶賛する内的独白界の知る人ぞ知るフリーソウルねた。トライブ・コールド・クエストのサンプリングで有名になった入手困難なマイナー盤だと思ってくれればいいです。
そんなことを知らなくても、恋してパリに佇むディレッタントな男子の意識の流れを追いかけた小説はとにかくキラキラで楽しいったら。
「時、場所、四月のたそがれ、パリ、陽の沈みかける明るい夕べ、単調なもの音、白い家並み、かげる木の葉。たそがれはいっそう甘美に、ここにいること、歩いていることのうれしさが。街並み、人のむれ、そしてずっとかなたにひろがる大気に、空が。パリがまわりで歌い、もやにかすんでみえるいろいろなかたちのなかに思考をやわらかくふちどる」
長々と引用してしまったけれど、全編こんな感じで、白ワインのような花の芳香混じりのパリの春の宵が、呼吸するたびに胸の中に流れ込んでくるよう。だけど、恋して両思いだって話のはずが、実は主人公の一人芝居でいいようにアッシーメッシーとして奉公させられてたかられてるだけだということが判明、最後の最後に大失敗というオチになっちゃうあたりは大爆笑の巻です。
翻訳はもちろん柳瀬尚紀、装丁は堀内誠一でカバーを外してもマーヴェラス、どこかが復刻すれば青春クラシックになること間違いなしなのに!と思います。
・サンディエゴ・ライト・フット・スー/トム・リーミィ 井辻朱美訳 サンリオSF文庫
 サンリオSF文庫の中でも入手困難といわれている短編集を近所の商店街の古本屋でゲット。最初は目を疑いました。「まず市場に出ない」って話で、四ケタの値段の噂があるというのに‥。でも欲しかったのはサンリオマニアだからではなく、『沈黙の声』を読んででこの作家に惚れたから。
サンリオSF文庫の中でも入手困難といわれている短編集を近所の商店街の古本屋でゲット。最初は目を疑いました。「まず市場に出ない」って話で、四ケタの値段の噂があるというのに‥。でも欲しかったのはサンリオマニアだからではなく、『沈黙の声』を読んででこの作家に惚れたから。
カンザスの田舎町にやってくる「本物のフリークスと魔法使い」がいるサーカスを舞台に、ブラットベリ風ファンタジーと見せかけてテーマは処女破瓜という「夏・体験物語」を描いたこの作家は、一つの長編といくつかの短編を残して急逝してしまったのだ。こちらはネビュラ賞を受賞した表題作をはじめとする短編をまとめたもの。
リーミィのファンタジーの大きな特徴は、セックスの匂い。ティーンエイジャー達が初めての行為で体験するエクスタシーという「小さな死」によって鮮やかに切り取られた生がここにある。人混みで見つけた世にも美しい天使を監禁する男の物語「ハリウッドの看板の下で」、元祖『バスケットケース』の「デトワイラー・ボーイ」といった傑作短編をセックスの要素から切り離して考えることは難しい。性の匂いを感じさせないジャック・フィニィ風の小話になると、この人の持つ輝きは急に色あせてしまう。
田舎から家出してきた15才のジョン・リーが、絵を描く年上の娼婦に出会って最初で最後の恋に落ちる「サンディエゴ・ライト・フット・スー」は、カポーティの『遠い声、遠い部屋』に負けず劣らず胸を締めつけるアメリカ好みの「エンド・オブ・イノセンス」のストーリー。タイトルからしてもう、ね。キラーでしょう。ラスト、二人の愛を成就させようとして失敗した娼婦の手紙が泣かせます。泣きます。泣きました。
・わが家のメニュウ/瀧澤敬一 暮らしの手帖社
 なんでもないアイテムで最高のお洒落が出来ることを映画で女の子たちに教えてくれたのはイデス・ヘッド。では日本のイデス・ヘッドは?というと、畑違いではあるけれど、私は花森安治じゃないかと思うのです。ビバ『暮らしの手帖』。
なんでもないアイテムで最高のお洒落が出来ることを映画で女の子たちに教えてくれたのはイデス・ヘッド。では日本のイデス・ヘッドは?というと、畑違いではあるけれど、私は花森安治じゃないかと思うのです。ビバ『暮らしの手帖』。
装丁家としての花森安治ワークスはどれも鋭く愛らしく、古本屋で狙っている方も多いんじゃないでしょうか。私もその一人。東京創元社版世界推理小説集のレタリング使いとか参るよね。これは私が数多い暮らしの手帖社本の彼女のワークスの中でも最高峰!と考えているもの。まるでマティス。1955年の初版をやはり近所の商店街の古本屋(前述の本を入手したのとは別のところ)で五百円で手に入れました。
内容は『暮らしの手帖』お得意の、観光客ではなく住民としてパリに居着いた人の生活細々エッセイ。だけれども、著者が何者かは皆目分からず。奥さんがフランス人という以外、本業に関する情報はまるでのってないんだもの。情報を求む。
パリよりも巴里と記す方がしっくりとくる、哀愁を帯びたシャンソンの歌声とマロニエの花の匂いが流れる下町風景を感じさせてくれる文章はとても素敵。おいしそうなエッセイが多い『暮らしの手帖』だけれど、これもご多分に漏れず、食事描写のところで胃を締めつけてくれます。
・僕たちの錆れた心が嘘みたい/柴田真紀 角川文庫
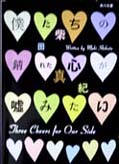 一部フリッパーズ・ギターのファンの中でマスト本と話題、「地球の引力に抗う18才の天才少女詩人」の93年詩集文庫。
一部フリッパーズ・ギターのファンの中でマスト本と話題、「地球の引力に抗う18才の天才少女詩人」の93年詩集文庫。
コンテンポラリー・プロダクションによるページ・デザイン! 「ロングヘアー・カット/もつれた恋と髪」「魅惑のスペース・トラベル」といったタイトル! 「パステルバッヂは引き出しの中に置いといて/もうアノラックには何も付いていないあの歌みたいに」「いつまでもビートニクな僕たち/真夜中のフラワー・トークで/喋りすぎた君たちには わからないだろう」 アズテック・カメラとフリッパーズ・ギターとヘアカット100と(中略)プライマル・スクリームとレザーカッツとスタカンに捧ぐ! お姉さんは壁に頭叩きつけちゃいます。
しかし、手放しで賞賛するほど恥知らずにはなれず、躍起になってけなすほど野暮なことはしたくなし。いくらなんでも屈託なさすぎるとは思うけれど、これも90年代前半という時代の貴重なスーベ・ニールではあると思います。
何よりも、古い欧米雑誌グラビアをカラーコピーして切り張りしたり着色したりしてそのまんま使い、というCTPPのかつての芸風は「権利問題」とか無粋なことを言う輩(あ、失言)が出てきて以降、封印されてしまったものなのでそれだけでも懐かしい。古いワープロ字体を貼っつけたようなデザインは、高校時代ミニコミ同人誌を作っていた人々の涙を誘うことでしょう。というか、93年当時、これとそっくりな同人誌を作っていた高校生だった人たち、いるでしょう? 手を挙げないと名指しするわよ! それにしては表紙デザインがCTPPではなく杉浦康平というのが謎。
さてこの柴田真紀さんですが、今は漫画家さんだという話です。若気の至りって誰にでもあるよね。
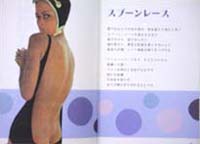 |
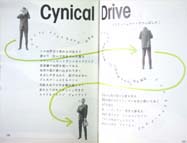 |
・ボクの音楽武者修行/小澤征爾 新潮文庫
 さて、フリッパーズ・ギターといえば、「オリーヴで連載していたオザケンのエッセイが好きだったのに、単行本化されないのかしら?」と首を長くして待っている女子の皆様に朗報。文体とメンタリティーがほぼ一緒で、ダッフルコートを着たポートレイトまでがそっくりの随筆集があります。オザケン伯父(ああ、世界のオザワになんてこと!)26才のエッセイ集がそれ。
さて、フリッパーズ・ギターといえば、「オリーヴで連載していたオザケンのエッセイが好きだったのに、単行本化されないのかしら?」と首を長くして待っている女子の皆様に朗報。文体とメンタリティーがほぼ一緒で、ダッフルコートを着たポートレイトまでがそっくりの随筆集があります。オザケン伯父(ああ、世界のオザワになんてこと!)26才のエッセイ集がそれ。
恐い物知らずでスポーツマンでめちゃくちゃ才能があってハンサムで強気で、夢だってなんだって平気な顔で叶えてしまうワンダーな男の子の青春と冒険がここに。
「欧米で生活したいにゃー」と思い立って、スポンサーつけて日の丸入りのスクーター一台持って貨物船に乗り込んで、行った先でたまたまやっていた指揮者コンテストに飛び入り参加して優勝してバーンスタインに認められてニューヨーク・フィルの副指揮者になっちゃうんだもの。お金もないけれど女子とは平気でデートして、「美人もよく目についたが、気おくれなど全然感じない。大げさに言えば、美人が皆ぼくのために存在しているようにさえ思えた。音楽に対してもそうだ」。選ばれた輝きを持つ人でなきゃいえないよね。
渡辺貞夫の『僕自身のためのジャズ』とかピーター・バラカンのソウル入門編『魂の行方』とか、「音楽がある男子青春記」って傑作が多いよね。欧米の日本男子といえば、伊丹十三の『ヨーロッパ退屈日記』もお忘れなく。