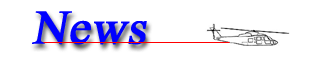|
3月中旬、東北、上越、近畿地方で立て続けに山火事が発生、ヘリコプターによる空中消火が行われた。
バケットを吊り下げたヘリコプターがグラウンドに降りる姿や、山中で消火を行う様子などが連日テレビのニュースで放映され、この消火活動は全国に知られることとなった。
宮城県
3月17日午後、丸森町廻倉の次郎太郎山で山林火災が発生。
火は18日になって次郎太郎山の北部、南部の斜面数カ所に広がった。
町役場前広場に臨時ヘリポートが設置され、ヘリコプター計18機が夜明けと同時に飛び立ち、中型ヘリが消火剤を、大型ヘリは阿武隈川や松ケ房ダムから取水して、空中から消火活動に当たった。
地上でも計800人が消火活動を展開した結果、昼すぎに一旦は鎮圧状態となったが、その後、警戒中のヘリコプターに搭載したセンサーが消火後の山肌で熱源を感知。午後4時まで空中からの消火活動を続け、夜に入ってからも自衛隊員、消防団員らが警戒活動を続けた。
兵庫県
3月19日午前、宝塚市切畑の長尾山周辺で山林火災発生。
同日午後、県や神戸、大阪、京都の各市、奈良県の各防災ヘリと、自衛隊大型ヘリ8機が上空から消火に当たった。しかし火は夜通し燃え続け、夜間中断していた消火活動は20日午前5時に自衛隊ヘリが偵察飛行、午前7時から8機で消火活動を再開、地上からも消火を行った。
滋賀県
3月19日午後1時ごろ、滋賀県日野町鎌掛の山中で火災発生。
消防車や県の防災ヘリコプターなどが消火に当たり、火は午後2時半ごろに鎮火した。
長野県
3月21日午前10時ごろ、長野県松本市浅間温泉の東側にある墓地付近の山林から出火。
現場はJR松本駅から北東に約5キロ、温泉街の近く。
松本広域消防局や自衛隊など約1200人が出動し、ヘリコプター9機が上空から消火活動にあたった。
この他、他の2県でも山火事が確認されている。(消防ヘリの出動は未確認)
以上、おりからの強風と乾燥で5日間のうちに立て続けに各地で山火事が発生。
消防・防災ヘリが大挙して出動、これに自衛隊も加わり空中消火を実施、地上部隊と連携して鎮火するという緊迫した事態となった。 (以上は読売新聞、毎日新聞、時事通信社より一部引用)
2002/03/24
この後、山林火災は岐阜、四国、東京・多摩と、全国的な規模で発生。
これをうけて行政側も、「初期段階のうちに消防・防災ヘリを呼ぶように」との消防・防災ヘリの積極的な活用を呼びかけている。
また「防災ヘリや自衛隊の要請は大げさではなかったか?」というマスコミの問いに答え
ある市長は「この措置により一人の死傷者も出さずに済んだ。大げさ過ぎる位で良かったと思っている。」とコメントしている。
今までは出動基準、指揮命令系統が明確でなく、大きな災害になったケースが見受けられたがが、最近では迷うことなく出動要請が出来る体制が整い、
災害を最小限に押さえることに役立っている。
ハード(防災ヘリ)だけでなく、ソフトウェア(活用の仕組み)もようやく追いついてきて、我が国の防災体制は着実に整備されつつある。
2002/04/21 加筆
コメント
阪神淡路大震災の際は種々の理由から効果が疑問視された空中消火であったが、山火事に於いてはいかに効果を発揮するかを、実証したといえよう。
この模様はテレビニュースで放映されたが、一般の人々にとっては、空中消火は馴染みの薄いものであり、もうもうと煙を上げる中、小さなヘリコプターが空中消火を行う様子は一見頼りなげに見え、まさに「焼け石に水」のように感じたかも知れない。
しかし、機数を増やし反復して消火剤を投下すれば消火が可能であることが、このことを通じてよく分かってもらえたのではないだろうか。
災害が起これば、各地の消防・防災ヘリが集合、市や県の枠組みを越え相互に協力、ことに当たる。
小サイトでも取り上げた緊急消防援助隊全国合同訓練など、このような訓練は各地で行われているが、こうした訓練を通じ、その協力体制は既に整ってきているといえよう。
今回の場合、自衛隊との協力もうまく行き、さらに効果が上がった。
また消火だけではなく、ヘリコプターからの画像伝送、センサーで状況を詳細に把握するなど、ヘリコプターの持つ特性をうまく活かしながら、空陸一体となった消火活動が功を奏した。
今後、このような教訓を活かして益々の協力体制を維持して欲しいと思う。
しかし、忘れてはならないのは今回の山火事の原因は自然発生だけではないということ。
長野では墓参の線香の燃え残りとも言われるし、滋賀では草を燃やしていたところ風にあおられ、山のすそ野に燃え広がったという。 まさに「マッチ一本、火事のもと」。
火災予防は先ず、我々一人一人の心がけであることを充分認識する必要がある。
2002/03/24
最後に
上記、記事掲載後、某消防・防災航空隊の方からコメントを頂きましたので掲載致します。
|
林野火災の防御に関してヘリの第一目的は延焼阻止です。
特に規模が大きくなればなる程、地上隊の入山による直接消火は必要不可欠となりますが、道無き山を切り開きながらのホース延長や可搬式ポンプを運ぶのには大変時間がかかります。
又火災による風向きの変化は予想が付きにくく退路を絶たれた場合、非常に危険である為、我々航空隊は延焼阻止ラインを設定して反復注水し、地上隊の進入路の確保と時間稼ぎをします。
勿論火炎が上昇するようなポイントにはこれも飛び火防止の為、注水する場合もあるのですが、もっぱら直接火を消す為では無く間接的に燃え止まりを作成する事に留意していると言えるでしょう。
終局的にはどのような火災でも地上隊無くしては消えないのです。
一見華やかな活動に見られがちな空中消火活動でも戦術的にはサポートであり、地上部隊の労力こそ本当の賞賛に値すると思うのです。
|
実際に消火で危険なフライトに従事しながらも「地上部隊の労力こそ本当の賞賛に値する」とおっしゃる、その謙虚な言葉にプロとしての高潔な精神を感じざるを得ません。
煙が立ち込め、山特有の気流の悪さと、火勢による上昇気流の中で、機体をコントロールし、消火剤を投下するのはまさにプロの技といえるでしょう。命を賭して消火に当たった消防・防災航空隊員をはじめ、パイロット、そして、常に機体を万全の体制に保ち、またある時はダウンウォッシュでずぶぬれになりながら、消火バケットへの給水を支援するなど、第一線の要員として活躍するメカニックの方々、各関係者に心から敬意を表したいと思います。
皆様、本当にご苦労さまでした。今後の安全飛行を祈念致します。
2002/04/21 加筆
|