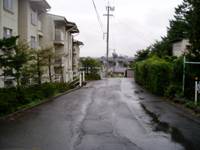|
|
||||||
|
||||||
| 2005.10.5金沢宿に引続き歩いたが、この日も前日と同じように雨に悩まされた。 朝からの雨で、全身衣服がビッショリ濡れただけでなく、資料もびしょびしょで見ることも難しかった。 3泊4日で天気のよい日を狙っての旅であったが、4日も天候の安定を望むのは無理かもしれない。 この日で、甲州街道の終点の中山道との合流点(下諏訪宿)に到達し、旅は終了となる。 この甲州街道は、国道20号線などでいたるところで寸断され、かつ旧道の案内標識が極端に少ないため、 路頭に迷うことがしばしばで、とても難解な街道であった。 これから甲州街道を旅する人にとって、このホームページが少しでも役立ことができたらうれしいと思う。 |
||||||
| 基本的経路 | ||||||
| 20号線→一般道→20号線→一般道→197号線(茅野駅前)県道152号線→一般道→20号線→一般道(諏訪市)(上諏訪) | ||||||
| (終点下諏訪宿)142号線(諏訪大社下社秋宮)一般道(下諏訪町)一般道(上諏訪駅東側)一般道←20号線←一般道 |
||||||
|
||||||
| 宮川坂室信号から20号線の弓振川にかかる橋(写真右)を渡り、 橋から約200mの板室バス停で20号線と別れ、左の細い道に入る。 |
||||||
|
||||||
| 200mほど行き、道なりに右折し20号線と平行に進み団地を通る(写真左)。 団地外れで右折し坂(写真中)を下り、20号線との突き当たりの丁字路で左折し20号線と合流して進む。 |
||||||
|
||||||
| すぐ中央道高架下を潜り、新田中バス停前を通り進む。 |
||||||
|
||||||
| 20号線を約500m行き、宮川信号三叉路(写真左)を右折して20号線と別れ、 JR中央線ガード下(写真中)を潜り、宮川下信号交差点を左折して上り坂を進む。 |
||||||
|
||||||
| 右側の宮川小学校脇の上り坂(写真右)途中で、ガードレールが切れたところで左折する。 坂(写真左中)を道なりに下りJR中央線ガード下を再び潜り、 |
||||||
|
||||||
| 丁字路を右折(写真左)して、2つに分れるところ(写真中)の右の道を進み、 信号十字路を右折して県道197号線を進む。 |
||||||
|
||||||
| すぐ先の上川にかかる上川橋を渡り、北へ進み茅野市街地を進む。 濡れた道路に写る景色は、芸術的にさえ見える。 |
||||||
|
||||||
| 茅野駅前のベルビアビル西側を進み、左に諏訪神社参拝道の大鳥居を見て、 県道152号線に入り、その先の茅野駅西口三叉路で、左手の道を進む。 |
||||||
|
||||||
| 高台の道(写真中)から左手に雨に曇る山並をて進み、上原信号変則5差路で20号線に合流して、 信号を直進する。 |
||||||
|
||||||
| 雨の20号線は単調で、左に葛井神社(写真左)の長い参道を見て、進む。 この20号線のどこかで旧道は右に入ることになり、用心深くその入口を探して歩き、 上原頼岳寺信号の次の十字路の、右角に「甲州街道 渋沢小路」碑を発見し、 20号線と別れて右折して進む。 ただ石碑が新しく半信半疑で、小路の途中にある上原郵便局で「旧甲州街道」であることを尋ねる。 JR中央線ガード下(写真右)を潜り、坂を道なりに上る。 |
||||||
|
||||||
| 上り切ったところで、右からの道に斜めに合流(写真左)し、左折する。 合流点の三角地帯に、石燈籠と甲州街道と大門街道の分岐を示す大小の道標がある。 |
||||||
| 上諏訪宿:全国に広がる諏訪信仰の中心諏訪大社上社の門前町で、江戸時代は高島藩城下町としても発展した。 城下町だったために大名などが泊まる本陣や脇本陣などはなく、問屋だけがおかれていた。 諏訪大社は、全国に1万以上の末社があり、諏訪湖南側(諏訪市)の上社本宮、上社前宮、諏訪湖北側(下諏訪町)の下社秋宮、下社春宮の4つからなる形態をとっている。 |
||||||
|
||||||
| 道標から約150mのところで、茅野市から諏訪市に入る。 雨に濡れた道(写真左)は妖艶で、昔のたたずまいを思わせる建物、頭部をすげ替えたような常夜燈。 |
||||||
|
||||||
| 白壁土蔵、情調ある通り、巨大常夜燈。 この辺りは既に上諏訪宿のはずで、その名残があちらこちらにあるのだと思う。 |
||||||
|
||||||
| その先の十字路のど真ん中のゴミ置き場の陰に、 これぞ甲州街道という「左江戸みち 右大明神江」と刻まれた巨大道標。 道標を反対側から見ているので、進行方向では左折し諏訪湖へ下る坂道が「大明神江」となる。 この辺りに来ると、朝からの雨で資料はビッショリ濡れ、書き込みができないだけでなく、 肝心の筆記用具のボールペンが予備を含めて全てどこかに落としてしまい、道中メモ記録不能。 |
||||||
|
||||||
| 十字路を直進し、霞ヶ崎入口信号(写真左)を進み、 右手に御柱祭で参道石段を登りながら柱を引き上げるので知られている足長神社(写真左中)前を通り、 普門寺町内を進むと左側のブロック塀上の、慈愛ある青銅製仏像が迎えてくれる。 |
||||||
|
||||||
| やがて道は下り坂となり、細久保地内に入り左からの道と合流(写真左)して右折する。 上諏訪宿はせいぜいこの辺りまでと思う。 人通りのないバス通りを進み、右側に武津公民館前の道祖神を見て、先へ進む。 |
||||||
|
||||||
| 道は20号線と合流(写真左)して右折し、200mほど進み清水1,2丁目信号丁字路を直進する。 丁字路の右の狭い小路の入口のところに、 |
||||||
|
||||||
| 大清水が湧き出ている(写真左)。この辺り一帯は大清水が湧き出るので町名も「清水町」という。 小路を奧に進み、道なりに左折、右折して、神社前の道にも清水流れていて、御膳水と刻まれている。 地元の人はこちらの方が上流で尊いというが碑は新しく、歴史的には入口の方が価値ありそう。 |
||||||
|
||||||
| 20号線に戻り、昔風商家の建物(写真左)、古そうな建物が並ぶ道を進み、 元町信号交差点で2つに分れるところでは、20号線と別れ右の道を進む。 |
||||||
|
||||||
| 分れ道の三角地帯に、「角間町十王堂跡」碑が建っている。 角間川にかかる木下橋(写真中)を渡り、諏訪二丁目地内通りの雨に濡れた道を進む。 川底にははなにやら突起物が並んでいるが、汚れ防止対策? |
||||||
|
||||||
| 右側に江戸時代に建てられた高国寺、左手に高くパラポラ鉄塔、右側に手長神社鳥居。 来る途中にあった四賀の足長神社と手長神社は別々の地にあるが元は夫婦神で、 地元の人々からは諏訪明神さまより古い神として祀られている。 |
||||||
|
||||||
| その先の丁字路で直進し、JR中央線上諏訪駅の東側の諏訪一丁目地内の通り(写真左)をしばらく進み、 湯の脇2丁目の赤い屋根のところの2差路を右折する。 |
||||||
|
||||||
| 次の2差路(写真左)を右折し、湯の脇公民舘のところの分れ道は、右手の急坂は温泉寺へ通じ 旧甲州街道は左の坂道(写真中)を上り、湯の脇一丁目(写真右)を東、北、北西と道なりに進む。 |
||||||
|
||||||
| 高台の道は大和3丁目の地内を進み、左手遠くにセイコウエプソン、 右側に先宮神社、城北小学校入口前を通り過ぎて、大和2丁目の通りを進む。 |
||||||
|
||||||
| 大和1丁目に入り、左側に非常に古式な常夜燈、 左手にエプソンの別の工場が見える辺りで、諏訪市から下諏訪町に入る。 |
||||||
|
||||||
| 結構アップダウンの激しい高台の道を進み、 左側に上諏訪宿と下諏訪宿の間の、江戸時代の面影がそのまま残る茶屋がある。 江戸時代に高島藩の御用商人をしていた橋本屋が建築したもので、行灯にその名がある。 ここは黒澤明の映画のロケ地にもなったことで知られている。 その先の右側の塀に掛けられた道標には、次のように記されている。 柿蔭山房(この上50m) 「左承知川橋(1600m) 右甲州街道茶屋跡(200m)」 柿蔭山房(しいんさんぼう)は、文化文政の頃(1815〜20年前後)に建てられたもので、 アララギ派歌人島木赤彦の住んでいた家。 |
||||||
| 下諏訪宿:中山道の第29次の宿場町で、正しくは「下ノ諏訪」と呼ばれていた。 その後1610年(慶長15)甲州街道が下諏訪まで延長された甲州街道の終点となった。 諏訪大明神の門前町として、高島藩の城下町として発展し、 諸大名の参勤交代、公家、旅人の重要な宿場町でもあった。 温泉のある宿場町としても有名。本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠屋40軒。 |
||||||
|
||||||
| さらに進み、左手下方に諏訪湖(写真左)を展望でき快晴であればさぞかし美しい景観と思う。 その先の右側に甲州街道最後の江戸から53番目の一里塚跡碑。 説明版には、あと1kmちょっとで中山道に到着するとある。 その少し先の右側の石垣に、甲州街道承知川にかかっていた橋石が貼り付けられている。 一枚石で重量は約13トン。 1561年(永禄4)武田信玄が川中島の戦いのおり、諏訪大明神と千手観音に戦勝の祈願をし、 社殿と三重塔の建立を約した。 しかし戦いに敗れ帰途この橋を通過しようとしたが乗馬はガンとして動かず、 信玄は先の約束を思い出し馬上より下りてひざまずき「神のお告げ承知仕り候」と申しあげ帰国した。 以来承知川と呼びこの一枚石の橋を承知橋と呼ばれるようになったという。 なおこの一枚石の煉瓦模様は信玄の埋蔵金の隠し図とも言われてきた。 |
||||||
|
||||||
| その先の十字路(写真左)を直進し、坂道を下り諏訪大社下社秋宮前まで道なりで進む。 下社秋宮は、上社前宮・本宮、下社春宮と並び、全国諏訪信仰の総本社。 諏訪大社標柱の右側参道を通り鳥居へ向かう。 |
||||||
|
||||||
| 鳥居の前(写真右)から左折して境内沿いに進み、 道なりに左折するコーナーに番屋跡碑が立っている。 左折して進み約30mのところで左からくる県道142号線と合流(写真左)して、 |
||||||
 |
||||||
| さらに約30m進んだところの丁字路(写真左)が中山道との合流点で、 中山道は丁字路の左から来る道となる。 |
||||||
|
||||||
| 丁字路の右側は、創業300年の聴泉閣かめやの駐車場で、その突き当たりに、 左から「下諏訪宿甲州道中・中山道合流之地」、「綿の湯」、「甲州道中終点中山道下諏訪宿問屋場跡」 の3基の碑が並んでいる。 時は、16:56。ここで甲州街道の旅は終了する。 「下諏訪宿問屋場趾」の碑に、右江戸へ五十三里十一丁、左江戸より五十五里七丁、 正面京都へ七十七里三丁と刻まれている。 江戸から中山道の方がかなり遠回りに感じるが、実際にはせいぜい二里(8km)しか違わないという。 綿の湯の由来:昔上社の神が、化粧水用の湯を綿に湿し「湯玉」にして下社に運び、 その湯玉を置いたところから温泉が沸いたので綿の湯と名づけられた。現在枯れてしまっている。 甲州街道は当初は甲府までで、その後下諏訪まで延長し中山道に接続した。 下諏訪宿は本来中山道に所属し、従ってその紹介は中山道旅で紹介することにしたい。 いずれにしても、雨の降る夕方で写真も満足するものが撮れなかったので、 中山道の旅できたときは、再度取り直しをする予定。 |
||||||
|
||||||
| 本陣跡(写真左):丁字路をそのまま直進するとすぐ右側に、立派な門構えの岩波家の本陣跡がある。 ここはまた1861年(文久元)和の宮がご降嫁の道中、宿泊されたところ。 中山道(写真右):丁字路左手の江戸方面からの中山道。 |
||||||
| これで甲州街道の全てが終了し、JR下諏訪駅からJR上諏訪駅で乗換え、 18:59発特急スーパーあずさ号で横浜へ向かった。 ただ、昨夜の茅野駅からといい、今夜の上諏訪駅からといい、 全身衣服がびしょ濡れで震えている異様な姿を、乗客たちはどのように見たのであろうか? |
||||||
|
||||||
|
||||||