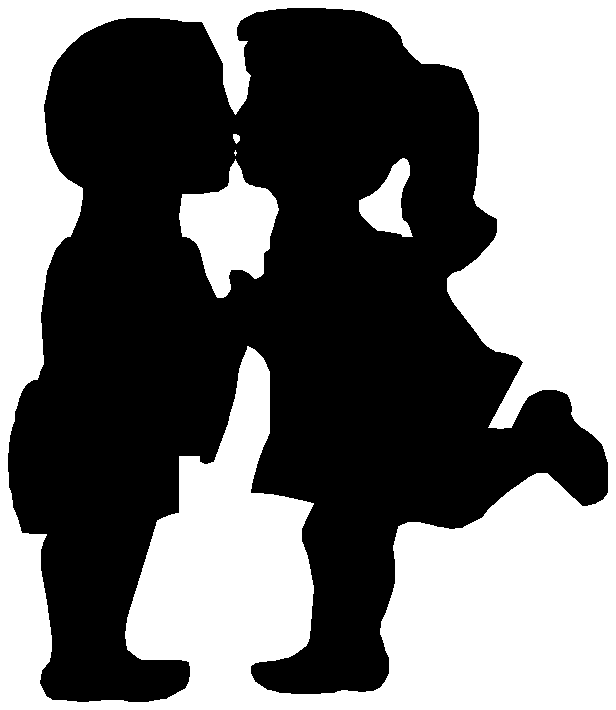|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| この区間は2004.4.12に歩いた。 天候は昨日とは違い、快晴。こういうときは日焼け防止の完全武装で、特に首周りと手には気をつけたい。 昨日に引き続き、北へ北へと向かった。 |
|||||||||||
| 区間の経路 (越堀宿)72号線→一般道(芦野宿)294号線→一般道→294号線→一般道→294号線 ↓ |
|||||||||||
| (旧奥州街道終点)女石←294号線(白川宿)←294号線(白坂宿)294号線←一般道 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 芦野宿:(栃木県那須郡那須町芦野)芦野の歴史は古く、鎌倉時代から集落があり、江戸時代になってからは最盛期には42軒の旅篭があり、芦野氏が4500石の旗本として陣屋を構えていた。 町はずれには昔からいろいろな人たちが訪れ、また紀行文にあらわれる「遊行柳」がある。 白坂宿:(福島県白河市白沢)宿場として栄えたところであるが、現在は東北線の駅からも遠く寂れた町となっている。戊辰戦争では白河攻略の薩長軍と奥羽列藩同盟の諸藩が前哨戦を行った所。 ここには牛若丸を藤原秀衡に引き合わせた金売吉次の墓と伝えられる墓がある。 白河宿:(福島県白河市)白川の歴史は古く、4世紀に白川の関が設置され、神亀5年(728)に蝦夷に対する押さえの白川軍団がおかれた。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
 |
|||||||||||
| 朝早く黒石市街のホテルを出て、コンビニで朝食のオニギリと缶ビールを買い、 黒磯駅前からタクシーで昨夕の越堀宿の征馬之碑へたどり着いた。 多分6時半前後だったと思う。 旧奥州街道の72号線は、このあたりから登り坂の山道になり芦野宿へ向かう。 オニギリとビールで朝食をしながら、まだ固い朝の空気を吸い込んで山道を登った。 確か富士見峠を越えるはずと思ったが、それらしいところはなくいつの間にか過ぎてしまったようだ。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| やがて余笹川の手前の右側に寺小一里塚公園(写真左中)が現われる。 公園はよく整備されていて、復元された江戸日本橋から42番目の寺小一里塚と、 安永4年(1775)建立の馬頭観世音碑(写真右)がある。 この馬頭観世音碑は、富士見峠の頂上にあったのを移したもの。 またこの公園からの余笹川の見晴らしは、特に素晴らしく見晴らし台が置かれている。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 公園の先は余笹川にかかる寺小橋で、ここからの川の見晴らしもまたすばらしい。 橋を過ぎると右手にスズキホルスタインファームがあるが、 鍋掛の牧場で経験した臭いというものは、全くなかった。 臭いがする、しないというのは、牧場管理の問題かもしれない。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 72号線を歩いていると、人通りはないが車が結構通過して行く。 後で聞いた話であるが、この時間帯は通勤の車がそれなりにあるという。 しばらくすると、右の水田の向うに小さな夫婦石神社(写真左、中)が見えてくる。 田の道を歩いて神社に参拝。 |
|||||||||||
| 夫婦神社の由来:昔敵に追われた一組の男女がこの地の大きな石の割目に身を隠したところ、白蛇が2匹現われ巨大な石を動かして追手を追い返した。二人はこのお石様に感謝しこの地に住み暮らした。 その後この石が夜になると互いに寄り添うという話しが伝えられ、いつの頃からか夫婦石と呼ぶようになり、あがめられ神社として祭られるようになったという。 |
|||||||||||
| 72号線に戻り数分歩くと、右側に江戸日本橋から43番目夫婦石一里塚がある。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 山道を下り294号線を横断し正面の細道(写真左)に入り、交差点を左折して芦野宿に入る。 294号線と平行したこの通りは、芦野の宿場通りである。 歩いて行くと右に「奥州道中 芦野宿」の大きな石碑が立っている。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 通りの中ごろの左側に、 芦野宿の旅籠と、また300年の伝統を守るウナギ料理の老舗の丁子屋がある。 ちなみにうな重(特上)2300円はとても安いと思う。 その先の左側には、本陣跡に建てられた近代的デザインの石の博物館がある。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| また通りに面した各家には、屋号の入った台座がおかれて宿場の雰囲気を高めている。 ちなみに屋号は左から和泉屋、屋根屋、紙すき屋。 芦野の町は、よく整備され昔の宿場面影を保存しようと一生懸命努力している様子が伺えてうれしい。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 宿のはずれに来ると、白河方面への案内板が立っている。 矢印に従い歩いて行くと橋の手前の左側に、 赤い帽子に赤い腹掛け、そして赤い口紅をつけた享保2年(1717)建立の大きなお地蔵さんと、 二十三夜塔などの3つの石塔が並んでいる。 この地蔵さんは、宿場の入口(出口)に位置していたので、 災厄を宿内にいれないことや、旅の安全や旅で亡くなった人を供養する役目を果たしていたという。 お地蔵さんの前を通り、奈良川にかかる小さな橋を渡り294号線に出る。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| ここで有名な遊行柳を見物するため寄り道をすることにし、そのまま294号線を横断して、 反対側の「奥の細道遊行柳」案内板の立っている道に入り進む。 無料休憩所の遊行庵の表札の建物の前を通り、数十m行って十字路で左折する。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| すると、右前方の池の向うに大きな緑の木が見えるが、それが遊行柳であった。 しかも池に映えてとても美しい景観を呈していた。 遊行柳は昔から種々の紀行文に現われ、芭蕉や藤村などが訪れたことでも有名である。 入口に左側が「遊行柳」、右側が「上の宮の「いちょう」」と書かれた白杭の間の道を通り、 初めてみる遊行柳(写真右中)。 その脇に「田一枚うえて立ち去る柳かな」刻まれた芭蕉の句碑がある。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| もとの294号線に戻り白坂宿へ向かう。 左側に巨大な「甦る豊郷」と刻まれた石碑。 細かい字でなにやらいろいろ書いてあったが、時間の関係で拝読省略。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 芦野を含めてこの辺りは那須町。 数分歩くと旧奥州街道は左のわき道に入り、峰岸のバス停前の左側に階段がある。 階段の登ると右にべこ石の碑と巨大な牛が横たわったような石(写真右)がある。 べこは方言で牛のことをいい、この石の形が臥牛に似ているのでべこ石といわれた、とのこと。 この碑は寛永年間に芦野宿戸村右内忠恕が建立したもので、 碑文は約3,500文字で道徳について述べられている、という。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 道なりに進み再び294号線に出て歩く。 数分歩いた横断歩道のところで、高瀬・板屋方面に行く分岐する道があるので右折して進む。 人も車も通らない、のどかな道(写真右)をしばらく歩く。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 板屋のバス停を通りすぎ、さらに歩き続けると道はゆるい登り坂になり、 坂の途中の左側に、論農の碑がある。 これはべこ石と同じ戸村右内忠恕が寛永元年に建立したもので、 病害虫の駆除、予防から、飢饉のための備忘録、飢人の看護法など 農民を諭す言句が刻まれている、という。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 坂の頂上の両側の山には、江戸日本橋から44番目の板屋一里塚が当時の面影を残している。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 頂上を過ぎると極ゆるい坂道となり、左側には馬頭観世音などの石碑がある。 板屋から高瀬地区に入り、人家が殆ど見ることができない田園風景を楽しみなが歩いた。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| わき道に入り約45分ほど歩いて、再び294号線に合流(写真左)して進む。 約30分ほど歩くと、左側の駐車場に江戸から45番目の泉田一里塚がある。 那須町には、夫婦石、板屋、泉田の3ヶ所に一里塚が築かれていた。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 一直線の294号線を進むと、左側に削岩の跡の無残な肌の山があり、ふと悲しくなる。 さらに右手には、100m先にふくべ石、初花清水案内標識があり、どんなものかと楽しみに進む。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| しばらくすると右折する山中への道(写真中)があり、ここで294号線と別れて進む。 残念、ふくべ石やらを見ることができない。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 右折すると右側の白壁土蔵のある民家に、明治天皇山中御小休所の立派な石碑が立っている。 わざわざ敷地内、しかも皆の見える入口のところに建立したという、その気持ち理解できる。 山中のバス停を通りぎると、左になにやら立派な建物があるが、どうも新しいようだ。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 約8分で山中の集落を過ぎて、再び294号線に合流する。 10分ほど歩くと道はゆるい登り坂となり、前方の峠の頂上に大きな標識が見えてくる。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 近づいて行くと、右側に那須町の町名塔(写真右)があり、頂上には福島県白河市の標識がある。 この頂上が栃木県と福島県の県境で、当時は下野国黒羽領と陸奥国白河領との国境であった。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 国境を挟んで道路の左側に、境の明神が並び建っている。 栃木県側には、天喜元年(1053)に創立された玉津島神社で衣通姫命を祀る。 ただ当時のものは明治39年12月の火災で類焼してしまった、。 峠を越した福島県側には、住吉神社で筒男命を祀り高台にある。 これは峠が切り下げられたためで、もともとは低い位置にあった。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 峠を越えると294号線はゆるい下り坂となって続く。 峠から200mほど行くと左側に目立つ木のもとに衣がえの清水の立札がある。 芭蕉も立ち寄ったという清水があるということであるが、衣がえとはどういう謂れがあるのだろうか。 福島空港へ38kmの標識(写真右中)を見ながら、ようやく人家の見えるところまで下りて来る。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 294号線の左側に山の神の鳥居(写真左)、馬頭観音などの石碑がなどがあり、 そして白坂宿の入口には、戊辰戦役で長州藩大垣藩士が戦死した地の石碑も(写真右)ある。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 白坂の宿場通りは真っ直ぐで、他と同じように人影は見られない。 通りを歩いて行くと右側に、見事な桜の木が特に目立っていた。 通りのはずれには高台に観音寺がある。 宿場の規模は小さく、昔の面影を残すものは殆どないように思われた。 ただ栃木県側でよく見られた鯉のぼりが、ここでは全然見当たらなかったが、風習の違いなのだろう。 宿を過ぎると、294号線は交差点を直進し南部中学校前を通って山道に入り白河宿へ向かう。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 人家の気配が全くない山道を歩いていると、 右の斜面に小さな馬頭観世音碑が、ひっそりと目立たないようにたたずんでいる。 その先の右には、牛頭観世音碑と馬頭観世音大菩薩碑とが並び、新しい花が供えられていた。 ちなみに建立年は、牛頭が昭和57年、馬頭が文久元年(1861)である。 街道を歩いているとどんなところにも馬頭観世音は必ずあるということは、 昔の人は如何に馬を大切にしていたか、人馬一体の生活をしていたか、 ということが改めて知らされる。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 山道を下り田園風景を通って白坂宿のはずれから25分ほど歩くと、皮籠集落の入口に来る。 入口から約5分のところの左側の桜の木の下に、金売吉次の墓の白い案内板(写真左中)が立っている。 そこから左折して小路を5分ほど行くと、左のひっそりした林の奥に金売吉次の墓がある。 墓は金売吉次兄弟の墓と伝えられているもので、白河市指定重要文化財となっている。 牛若丸(源義経の幼名)を鞍馬山から平泉の藤原清衡のもとに連れたいったことで有名な吉次は 兄弟で承安4年(1174)この地で群盗に襲われ殺された。 里人が憐れに思い兄弟をここに葬り供養したと伝えられている。 石塔は3基あり中央に吉次、左が吉内、右が吉六で、建立は室町時代(1338〜1573)といわれている。 石塔の石囲は、元治元年(1864)7月に建立されている。 なお皮籠の地名は、群盗が吉次から奪った砂金入りの皮籠(かわご)からつけられたもの。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 294号線に戻って進むと、路傍にはお地蔵さん、馬頭観世音、野仏像などが見られる。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 吉次の墓から5分ほど歩いた新白河中央病院前には、「直進 白河市街」の標識が出ている。 もうすぐ最終の白河宿と思うと、つい足取りも軽くなった。 この辺りの地名は「一里段」といい、一里塚があったといわれるが、跡は所在不明。 これまでの登り坂が、ここからの294号線は下り坂となり山間の道を白河宿に向かう。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 一里段から15分ほどのところで282号線を横断(写真左中)し、264号線は直進する。 白河市街まで2kmの標識をみながら、交差点から10分ほど歩いて次の交差点を右折する。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 右折した左角に、戊辰の役古戦場跡がある。 慶応4年(1868)に攻めてきた薩摩の西軍と、守る会津の東軍が戦った激戦地跡で 両軍それぞれの戦死者の碑がある。 北側にある304名の会津戦死者の墓(写真中)。 また、ここには田辺軍次の墓(写真右)もある。 田辺は東軍が敗れたのは、小平八郎が西軍の道案内をしたためと信じ、 斗南藩(青森県)から1ヶ月かけて白坂宿にたどりつき、鶴屋で八郎を斬殺し、自刃した。 八郎の養子直之助が仇の軍次の墓を白坂観音に建てたが後にこの地に改葬された。 軍次は享年21才の若さであった。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 松並の通りを進むと道は丁字路になり、右折すると南湖へ、左折が294号線で市街へ向かう。 九番町(写真左中)、七番町、三番町では谷津田川にかかる南湖橋を渡る。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 二番町、大町会館の前を通って一番町に入ると、前方に白河市役所への標識が出ている。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| その交差点で左折すると白河市の中心部となり、白河の宿場通りとなる。 左が勘定町右が天神町に挟まれた通りで、史蹟や建築物などの宿場の面影は見当たらなかった。 宿場通りを400mほど行くと丁字路になるので、左折しすぐ右折し中町に入り、 奥州街道の終点女石を目指す。 294号線はJR白河駅前を通り、中町を約400m進んで丁字路を右折し、100mほど歩き左折する。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 本町の通りを200m行くと十字路で、直進するのが11号線で294号線は左折する。 横町を約300m行ってJR東北本線のガード(写真左中)下をくぐり、 さらに田町を400mほど進むと阿武隈川にかかる田町大橋(写真右中)にくる。 橋の上から見るとこれまでの川と違い水量の多い川であった。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 橋を渡り向寺の通りを進んでいくと294号線はゆるい登り坂となり、 500m先で4号線に合流の標識が出ている切通(写真右)を通る。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 切通を過ぎると道は下り坂となり女石の集落に入る。 |
|||||||||||
 |
|||||||||||
| 正面に見える「KOMATSU」の大きな看板のところで道は2つに分れ、 左が会津街道(294号線)、右が旧奥州街道で300mほど行くと4号線に出る。 旧奥州街道の終点のはっきりした地点が不明であるので、 独断で分りやすいこの分岐点をもって、終点と決めた。 これで奥州街道の2泊3日の旅は、終了となった。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 道の分岐する手前の左側に、仙台藩士戊辰戦没之碑が建っている。 女石は会津街道(294号線)と仙台街道(4号線)の分起点で、 東軍の最前線基地として激戦が展開された。 明治2年にこの戦いで戦死した150余名の仙台藩士の戦死供養塔が建立された。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 旅を無事終え帰途についた。 立派なJR東北本線白河駅であったが無人改札で、 駅員もどうも1人でこの大きな駅舎と電車の送り迎えをしているようで、 今更のように地方の駅の合理化が進んでいることを、ちょっと複雑な気持ちで知った。 プラットホームに立つと、正面の桜の木の上に復元された小峰城の美しい姿を見ることができた。 終わりよし、といういい気分でいると、電車が入ってきた。 |
|||||||||||
|
|||||||||||