MTRの録音をコンピュータに取り込み、トラックダウンとマスタリングをおこないます。
MTRのエフェクトを使ってマスタリングするので、実際には取り込みとトラックダウン・
マスタリングが一つのプロセスで完了します。気に入らなければこのプロセスをやり直
すことになる。奥が深〜い世界。(^^;;;)
トラックダウン
MTRのパンとフェーダーを適当に設定する。
3点吊りのワンポイントとステージ上のマイクのバランスが問題。
クラシックでは一般に、ワンポイントステレオ録音が基本。最も全体をバランスよく録れ
る一点を探し出すことが大切。全体の定位やホールの奥行きを捉えるのはワンポイントな
らでは。
ステージ上のマイクは、ワンポイントで「足りない音を補う」つもりで使うとよい。
だが全てオンマイクでミキシングしたい誘惑も・・・楽器の音は直接音だけでなく、空間
に反響した音を聞いている。オンマイクをやりすぎると平板な音像になるので気を付けよ
う。(^^;)
各楽器のsoloやハープなど音量の小さな特殊楽器はオンマイクで補助する。この場合も、
オンマイクの直接音とオフマイクの反響音の「つながり」が不自然にならないように。

(写真)左からワンポイントL,R,Vn,Va,Hrp,solo,ChorL,R。右端はマスターボリューム。
マスタリング
トラックダウン時にDPS内蔵エフェクトでマスタリングを行う。
*エフェクトはコンピュータに取り込んでソフトでかけてもよい。
・REVERB>BIG HALL
ホールトーンを補うために「REVERB>BIG HALL」をかけた。プリセット通りでよいが、
場合によりプリディレイ、残響時間等のパラメータを調整する。
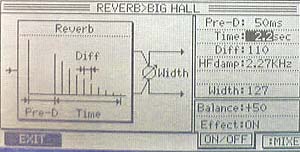
・COMPRESSOR/LIMITTER
DPS16はダイナミックレンジが驚くほど広い。このため時として弱音と強音の落差が
大きすぎたり、歌のフレーズの途中で一音だけ不自然に音量が増えたりする。(演奏に
もよる)より聴きやすくするために「COMPRESSOR」をかけた。
DPS16のコンプレッサーには、一般的なスレショルド、レシオ、アタック、リリースに
加えて「OUTPUT」パラメータもあるので、レベル調整もできる。
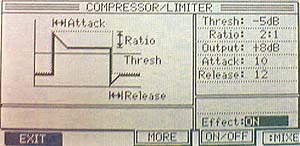
*DPS16 Ver.2から「ノーマライズ」「レベルチェンジ」が加わった。またVer.3では
ビットレート・サンプリングレートコンバーターも加わり、外付けCD-Rに直接焼ける
ようになった。しかし筆者はVer.1.5からアップデートしていないので、コンピュータ経
由で焼く方法を採っている。
コンプレッサーも「奥が深い」世界で、最初はプリセットを試して、深くかけすぎない
ようにする。
*『サンレコ』誌2000年末頃のレビューにもあったが、DPS16のコンプレッサーはす
べらかなかかり具合がすばらしく、音質劣化が少なく自然な仕上がりになる。
コンピュータへの取り込み
オーディオカードとソフト
DELTA Audiophile2496と付属のLogicDELTAを使ってMacに取り込んだ。
DPS16とAudiophileをS/P DIF同軸ケーブルで接続する。同軸デジタルケーブルは、もの
によってノイズが入る製品もあるので、コネクタ部分がノイズ対策の特殊な形状になってい
るものを選ぼう。筆者はノイズのないSONYのビデオ用同軸ケーブルを愛用している。同軸
デジタルケーブルはビデオ用もオーディオ用も共通(75Ω)だ。
M-Audioのカードは抜群のコストパフォーマンスと音質で売れているインターフェイスだ。
上位機種のDELTA1010はプロフェッショナルにも好評だが、ローエンドモデルから24Bit/
96kHz対応なのもうれしい。
Audiophileはアナログ、デジタル、MIDI I/Fが付いており、LogicDELTAがバンドルされて
いる。(MicroLogicAVの2496対応版。LogicAudioPlatinumへアップグレード可能)
Mac用ドライバは若干不安定な部分*もあるが、何度もサポートに問い合わせるうちに使える
ようになった。
*「不安定」とは、マスタークロックを「S/P DIF」にするとサンプリングレートが44.1k
に固定されてしまう、ドライバ設定を保存してもLogicを起動したとたんにドライバ設定が
無効になる、等の症状だ。これらの症状は、DELTAコントロールパネルではなく、Logic上
から直接設定することで解決した。DELTAコントロールパネルはなるべくいじらないで、
Logicから設定できる項目はLogicで設定するとよい。(コントロールパネルで設定するのは
入力ミキサーと、SCMSやエンファシス位だ。)
(写真)Audiophileの「デルタ・コントロールパネル」ミキサー画面
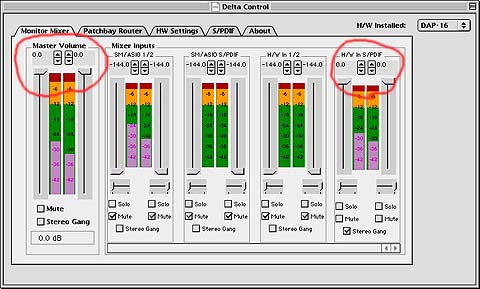
左端「Master Volume」、右端「S/P DIF IN」のフェーダーを上げておく。
*Audiophileのデジタル入力でサンプリングレートを44.1k以外に設定する方法。
LogicDELTAで、まずクロックを「Internal」にしてからサンプルを「48k」「96k」に
設定。それからクロックを「S/P DIF」に変えるとOK。(逆は不可)
また、デジタル入力時はミキサーの入力を「Input3-4」にしておかなければならない。
(写真)LogicDELTAのAudioPreferenceウインドウ
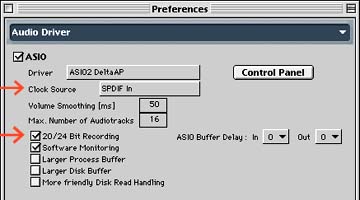
クロックソースをまず「Internal」でサンプリングレートを96000に設定した後、
「S/P DIF In」に戻すとサンプリングレートが望み通りに固定できる。(裏技)
「20/24Bit Recording」にもチェックを入れておく。
(写真)LogicDELTAのミキサーウインドウ・録音中
入力を「Input3-4」(デジタル入力)に設定する。(重要)
CD化するには「AIFFインターリーブステレオ」フォーマットにしておく。(下矢印)
DPS16のプレイボタンを押してLogicの録音ボタンを押す。
アナログ取り込みの方法
別の入力方法として、MTRから直接アナログ16Bit/44.1kHzで取り込むことも可能だ。
サンプリングレートコンバートが不要になるぶん音質的に有利だろうか?
2種類のインターフェイス/ソフトの組合わせで試みた。
(1) Onkyo SE-U55 + YAMAHA WaveEditorTWE
DPS16側を16Bit/44.1kHzと24Bit/96kHzの2通りで録音したものを、USBイン
ターフェイスのSE-U55とTWEでアナログ16Bit/44.1kHzで取り込んだときの音質を
比較してみた。
アナログ16Bit/44.1kHzで取り込んだときも、ソースが24Bit/96kHzのほうが
16Bit/44.1kHzのソースからの取り込みより、明らかに音がよい。24Bit/96kHz
独特の「空気感」がある。つまり、コンサートホールの空間があって、その空間を
満たした空気が響いている、アコースティックな響きが捉えられている。
それに比べると16Bit/44.1kHzソースからの録音は情報量が少なく、響きに乏しく
感じられた。これはこれで、音の芯だけがあってわかりやすい音には違いないのだが。
(2) KORG1212 I/O + Digital Performer
Digital Performer2.72と、ダイレクトサポートのKorg1212 I/OでDPS16から
アナログ取り込みを試みた。カードとソフトの相性は抜群で、設定も簡単。
Digital Performerの録音はなかなかシャープな音質である。が、アナログ取り込
みはS/P DIFデジタル取り込みに比べてどうしても劣ってしまう。デジタルでは正確
に再現できるハープのアルペジオが、アナログでは音の立ち上がりが不明瞭で、不均
等に聞こえるといった具合。S/N比の点てもアナログは不利である。
以上のことから、
(1) 16Bit/44.1kHzでアナログ取り込みをするなら、ソースが24Bit/
96kHzのほうが16Bit/44.1kHzより良い結果が得られる。
(2) 24Bit/96kHzソースから16Bit/44.1kHzアナログ取り込みと24Bit/96kHz
デジタル取り込みを比べると、解像度、S/N比の点でデジタル取り込みの方が
良い結果が得られた。
そこで、次項ではデジタル入力のデータコンバートについてみてみよう。