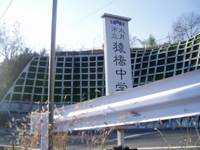|
|
||||||||
|
||||||||
| この区間は、2004.12.14に歩いた。 ただ作成したのは、2005.6であるので、記憶を辿るのに悪戦苦闘している。 2004.8に歩いた中山道が全く手付かずであることを考えると、まだマシということかも知れない。 いつものことであるが、同じ天候の下で同じ時間にデジカメで撮影しても 色彩がバラバラになってしまうということである。 カメラに弱い私には全く不思議なことで、情けないことにどうしたらよいか分らない。 |
||||||||
|
|
||||||||
 |
||||||||
| 野田尻宿の外れの丁字路にある西光寺から左折すると、中央自動車道のガードを潜る。 |
||||||||
|
||||||||
| 旧甲州街道は、正光寺の横の道を直進し,ひっそりとした林の中に入る。 路傍には古い石碑が立ち並ぶ。 |
||||||||
|
||||||||
| しばらくして中央自動車道を横断する。 下を見下ろすと、中央自動車道の交通量が本当に少なく満杯になることがあるのかと思う。 |
||||||||
|
||||||||
| 再度林の中を100mほど通り、県道大月上野原線に出て右折する。 |
||||||||
|
||||||||
| 道端に「嶽 大先達白倉宝行」と刻まれた明治2年建立の大きな富士講碑があり、 その先の石垣の上に日本橋から20里の萩野一里塚跡碑(写真左中)がある。 のどかなゆるい下り坂を淡々として道なりに進み、右手に鳥居もあらわれる。 |
||||||||
|
||||||||
| 坂道を下り続け、右側に現われる中央自動車道の遮音塀に沿って進み その終るところの丁字路で右折し矢坪橋を渡り中央自動車道を横断して、矢坪の集落に入る。 |
||||||||
|
||||||||
| 右側に「大乗妙典日本廻国供養」塔があり、その先で旧甲州街道は県道の右側の矢坪坂を登る。 その登り口に「矢坪坂古戦場跡」案内板が立っている。 1530年(享禄3)相模国北条氏縄軍が甲斐に攻め込み矢坪坂に進み、 坂上の小山田越中守の軍と激戦を展開したところという。 |
||||||||
|
||||||||
| 激戦の跡形も感じられないのどかな風景を楽しみ、坂道は次第に山の中へと進む。 右側に武甕槌神社の鳥居が現われる。 武甕槌命(たけみかづちのみこと)を祀った神社で、武甕槌命はまた建御雷之男神ともいい、 いわゆる天孫降臨で、地上を支配していた大国主神から国土を譲り受けた時の主役を務めた神である。 |
||||||||
|
||||||||
| さらに山道らしくなり、ここが参勤交代の通った旧甲州街道とはとても思えない。 道々には、お茶の供えられた庚申塔(?)や矢坪金毘羅神社参道道標、 |
||||||||
|
||||||||
| 手摺のある山道となり、下を覗くと先ほどの県道が直下となる切り立った崖。 ここは「座頭転がし」という難所であったところで、今でも恐い。 目の不自由な2人が曲がった道とわからずに、前の人の声を頼りにまっすぐ進んだら、 谷底に落ちて死んでしまった、という伝説があるとのこと。 弱者の悲哀に心が痛み、いつものことながら涙もろい。 時には道なき道をかき分けて進み、ようやく松林の前方に青空が見え開けてくる。 |
||||||||
|
||||||||
| 松林を出ると上野原市の新田の集落となり舗装された道が続く。 道なりに進み左からの県道と合流した先の右の斜面に、「これより甲州街道 犬目宿」看板と、 その左に「君恋温泉 これより1.5km」看板。 やはり熟年以上になっても、「恋」と聞くと心がときめく。 |
||||||||
| 犬目宿は、現在の集落より約600mほど下方の元土橋にあったのが、 1712年(正徳2)この地に移転し翌年宿場となった。 本陣2軒、旅籠15軒の山峡の小さな宿場であったが、昭和45年の大火で宿場の大半が焼失した。 |
||||||||
 |
||||||||
| 真直ぐ続く犬目宿の通り。 |
||||||||
|
||||||||
| しばらく行き左手の小高い丘の墓地に、義民犬目村兵助の墓がある。 1833年(天保4)と1836年(天保7)の連続する大飢饉で、代官所に救済を求めたが聞き届けられず 兵助は、甲斐の国に広がった「甲州一揆」を指導した人物のひとり。 小高い丘から遥か遠くにくっきりと富士山の姿。 |
||||||||
|
||||||||
| もとの県道に戻り進むと、バス停「下宿」の脇に木陰にたたずむ牛頭観世音碑(写真左)、 その先の左側に、犬目宿直売所をバックにして平成14年建立「犬目宿」碑。 この建物は公民館で、犬目宿案内板や公衆トイレもある。 進んで行くと左側に、義民 「犬目の兵助の生家」(後の建物)案内板があり、 兵助の「離縁状」などが、この生家「水田屋」に残されているという。 さらに先の明治天皇御小休所址碑のある2階建の上条家が、本陣跡ということであるが見落としてしまった。 |
||||||||
|
||||||||
| 先に進みバス停「犬目」辺りまでが宿の通りのようで、その先で右折して道なりに進む。 しばらく行くと右側の道端には、とてもおおらかな陰陽道祖神、夫婦道祖神。 「←扇山入口 公衆トイレ→」道標とその足元にも小さな同じような道標、 さらに「←扇山 犬目宿→」道標と、道標のラッシュ。多分管轄が違うのでしょうね。 |
||||||||
|
||||||||
| その先で左折するコーナー辺りに、不動尊像と白馬不動尊鳥居。 |
||||||||
|
||||||||
| 左折して君恋坂を登りながら田園風景を楽み、 しばらくして県道の右側の整備されていない側道を進むのが旧甲州街道で、憧れの君恋温泉へ通じる。 |
||||||||
|
||||||||
| 数分歩くと開けた道となり、ふと右手を見るとおじさんが一生懸命玄関の掃除中。 通り過ぎると「入浴・宿泊 君恋温泉」の看板。 さてと見渡してもそれらしき建物もなく、それでは今通り過ぎたのが君恋温泉かと振り返りパチリ。 私の恋は、秘湯の1軒宿でした。 |
||||||||
|
||||||||
| 道はまた山道となり、沢(写真左中)を渡り、沢に沿い歩いて、ようやく県道に出る。 |
||||||||
|
||||||||
| 県道を右折して道なりに坂を下って行くと、 カーブのところにこんもりと盛土された日本橋から21里の恋塚一里塚跡がある。 |
||||||||
|
||||||||
| 県道を7,8分歩いて、山神社の前から県道と分れ右に入り恋塚集落を進む。 恋塚の地名は、東国征伐の帰途にあった日本武尊が 海神の生贄となった橘姫を偲んで思い沈んだことに由来するという。 右側の大きな建物は250年前の建物で馬宿であったという。 さらに進むと木洩れ陽の枯葉の下に石が敷かれている道となるが、ここが旧甲州街道石畳である。 その先で県道と合流する。 |
||||||||
 |
||||||||
| 右折して県道を数分進むと大月市境界標識があり、ここで上野原市から大月市に入る。 |
||||||||
|
||||||||
| 大月市内の下り坂を道なりに延々と進み、時には路傍の野仏群を見ながら、 中央自動車道のガードを潜り、進む。 |
||||||||
|
||||||||
| 大月市内に入り約15分ほど歩き20号線と合流し、右折して下鳥沢宿、続いて上鳥沢宿を進む。 大月市富浜町にある下鳥沢宿と上鳥沢宿は隣接している合宿で、 人馬継立てなどは半月ずつ交替で行われていた。 下鳥沢宿には、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠11軒あった。 宿場通りは交通量は少なく、昔の面影を残す建物もあるが本陣跡などは残っていないようである。 |
||||||||
|
||||||||
| 少し進むと右側に鳥沢小学校があり、この校庭に大月市指定文化財「コノテガワシ」巨樹がある。 根元周囲1.9m、樹高12m、枝張り東西6.3m、南北7.5mもある。 この樹木の辺りに、1里塚があったようである。 その先にJR鳥沢駅標識があり、左手に駅舎(写真中)が見える。 この辺りから上鳥沢宿となる。 |
||||||||
|
||||||||
| 上鳥沢宿には、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠13軒あった。 真直ぐな上鳥沢宿の通りを進むと、下鳥沢宿と同じように昔の面影を残す建物もある。 明治天皇御小休所碑のあるところが本陣跡ということであるが、見落としてしまった。 |
||||||||
|
||||||||
| さらに進み、三栄工業の看板から20号線と分れ、旧甲州街道は右のゆるい坂道を登る。 きれいに舗装された道を進むと、突然貫一お宮スタイルの怪しいシルエット。 私も一度でよいからこんな関係になってみたいと、うらやましく思っていたら、 いつの間にか先ほど分れた20号線に出てしまった。 |
||||||||
|
||||||||
| 右折して20号線(写真左中)を、左手下方に桂川の流れを、東京から89kmの標識を、見ながら進み、 前田商店の真紅の看板から、右の道を進む。 |
||||||||
|
||||||||
| 道なりに4分ほど歩き、小屋の左側から道なき坂道を下り20号線に出る。 |
||||||||
|
||||||||
| 20号線を横断し、前方の中央分離帯にある宮谷橋標識(黄色標識のその先にある)の手前で、 20号線の左側の脇道を下る。 左手下の桂川を眺め、右上の20号線の宮谷橋を見上げながら舗装された道を進む。 |
||||||||
|
||||||||
| 旧甲州街道は桂川岸辺沿いにあるので、左手下の方へ枯葉を掻き分けながら、田を横切りながら下る。 桂川沿いの道に出て進むと、道端に常夜燈などの石碑(写真中)が放置されている。 しばらく歩いて、今来た川沿いの旧甲州街道を振り返る。 |
||||||||
|
||||||||
| 道なりに数分進み、宮谷信号のある20号線に出て左折して進む。 |
||||||||
|
||||||||
| しばらく歩き富浜町から猿橋町に入り、 東町自治会館から50mほどのところで、20号線から分れて右へ入り、右上に猿橋中学校を見て進む。 猿橋宿は、日本三奇橋のひとつの猿橋を有し、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠10軒あった。 分かれてから150mほどのところの左側に、猿橋案内板がありその先の丁字路で左折する。 |
||||||||
|
||||||||
| 左折すると目の前に、深い渓谷をなす桂川にかかる猿橋(写真左)が現われる。 長さ31m、幅3.3mの木橋で、渓谷が31mと深いため橋脚がたてらず、 両岸から張り出した四層のはね木(写真右中)によって支えられている、珍しい構造の橋である。 猿橋は昭和7年に国の名勝に指定され、また安藤広重の「甲陽猿橋の図」にも紹介されている。 猿橋は日本三奇橋のひとつで、他に岩国の錦帯橋があり、 3つ目は、徳島県祖谷のかずら橋、木曽の棧(かけはし)、栃木県大谷川の神橋などと言われている。 猿橋は、奈良時代に架橋されたが, 「推古帝(600年)の頃百済人の志羅呼が、猿が藤蔓(ふじつる)をよじり断崖を渡るのを見て橋を造った。」 という伝説がある。 |
||||||||
|
||||||||
| 猿橋を渡り20号線に出て、右折して進む。 この通りが猿橋の宿場通りであるが、当時の面影や史蹟も全く残されていないようである。 右手に中央自動車道を眺め、右側の桂川にかかる橋を前を通り、左方のJR中央線猿橋駅を過ぎると、 20号線は道なりに左折する。 |
||||||||
|
||||||||
| その左折するコーナーの右手に新しい阿弥陀寺石柱があり、この辺りに一里塚があったという。 周りには南無阿弥陀仏や道祖神の古い石碑がある。 |
||||||||
|
||||||||
| 左折して20号線を進むと、右手下方には桂川の悠久の流れ。 50mほど歩き自動車販売センターで20号線と分れ右の道に入り、東京電力新駒橋寮敷地へ進む。 |
||||||||
|
||||||||
| 寮の前に、「東京送電水力発祥の地」碑がある。 明治40年(1907)に駒橋発電所から、東京に初めて水力電気が送られた。 |
||||||||
|
||||||||
| 発電所の巨大な送水管の前を通り左折して坂道を登り、JR第五甲州街道踏切を渡り、進む。 なおこの辺りの旧甲州街道は、中央線や発電所の建設で多くが消滅しているようである。 |
||||||||
|
||||||||
| 踏切から50mほどのところで一旦20号線に出てすぐ、右の道(写真左)を20号線と並んで進む。 この通りは駒橋の宿場通りとなる。 駒橋宿は、本陣・脇本陣ともなく、旅籠4軒の極めて小さな宿場であった。 通りには宿場の面影は全くなく、久し振りに出会う文政5年(1822)建立の秋葉大権現常夜燈。 約300m行き20号線と合流すると、突然「奈良子」という珍しい行き先のバスが通り過ぎて行く。 20号線を300mほど進み魚駒商店手前から、右斜め道に入りJR中央線駒橋跨線橋へ向かって進む。 正面には、大月市のシンボル岩殿山が陽に映えている。 同じ時間帯に撮影しても、空の色が白くなったり青くなったりするのは、腕がよすぎるせい? |
||||||||
|
||||||||
| ここで20号線をそのまま50mほど行き、高月橋入口信号のある丁字路の三嶋神社に寄り道をする。 2006年に創建1200年を迎える由緒ある神社で、大月総鎮守となっている。 この境内に、「大槻回四十五尺」と刻まれた石碑があるが、 大槻とは大きなケヤキの意味で「大月」の地名の由来となったという。 余談であるが、三嶋(三島)と名のつく神社は全国で約2万社もあるというから、ビックリである。 |
||||||||
|
||||||||
| 旧甲州街道に戻り、駒橋跨線橋を潜り中央線沿いに西へ進み、 ブロック舗装のさつき通り商店街を通り、大月郵便局前を通り過ぎ、 右手にJR大月駅を見て直進して道なりに進み、20号線の大月二丁目信号に出て右折する。 この辺りから宿場であったようである。 大月宿は、1669年(寛文9)駒橋宿場から分れた宿で本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠2軒あった。 |
||||||||
|
||||||||
| 20号線を30mほど進み左側に大月市役所、 さらに進み左側の「明治天皇御召換所阯」碑がある滝口商店のところが本陣跡となる。 道の反対側にある駐車場辺りが脇本陣跡のようだ。 |
||||||||
|
||||||||
| その先の陸橋(写真右)の下は、富士急の線路。 |
||||||||
|
||||||||
| 正面に見える大月橋東詰信号の丁字路交差点は甲州街道と冨士道との追分で、 富士道(富士山参詣道)は、大月宿が起点となる。 直進が桂川にかかる大月橋を渡る20号線、左折するのが富士道の139号線。 東詰の左側の小さな広場には中央の祠の右に道標が3つ立っていて、左から順に 「左富士街道 右甲州街道」、「左ふじのみち 右甲州道中」、「左富士の道 右甲州道中」(写真中) と刻まれている。 かつての甲州街道は右折して川岸へ降り、下流の笹子川の合流点に近いところで橋を渡ったという。 現在は道がないので、大月橋を渡って進む。 大月の宿場は、この辺で終わりとなる。 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||